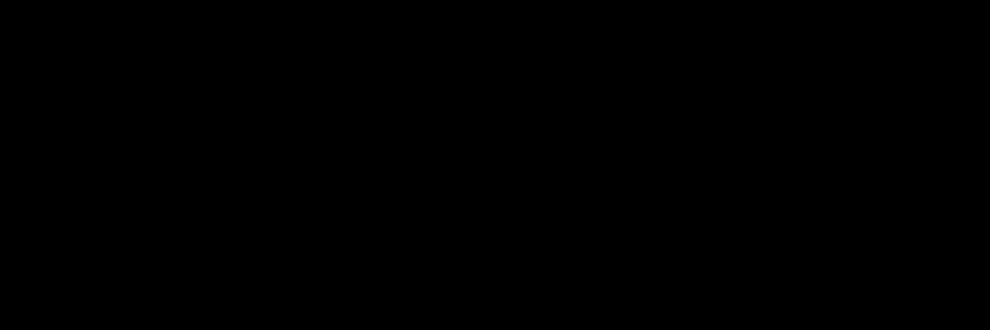NTRハーレム番外編 在原七海が竿役おじさんのモノになる話
「レヴィ9、目標地点に到達しました」
草木も眠る丑三つ時。マイクに乗るギリギリの音量で、レヴィ9――在原七海は囁いた。
彼女がいるのは、つい最近建てられた一軒の豪邸のすぐ近く。
政治家たちの怪しい動きの裏に、アストラルが絡んでいる疑惑がある……そんな情報を基に、七海は真新しい邸宅に潜入を試みていた。
彼女は非公開政府組織である情報局特別班、通称「特班」に所属するエージェントの一人だ。兄である在原暁ともども、学生の身でありながら人知れず犯罪者を日夜追っているのだ。
七海の報告を受け、彼女の上官にして育ての父でもある在原隆之介は、お決まりの文句を返す。
『レヴィ9、周囲の状況は』
「特に異常はありません。人や物資の流れも変化なし」
『ふむ。こちらに気付いていないのか、それとも誘っているのか……いずれにしても油断するなよ』
「了解」
一つ、息を吐く。当初は外からの調査だけだったにも拘らず、潜入まで行うことになるとは、七海自身考えてもいなかった。
その「外からの調査」というのも、七海が担当した任務だ。その結果、いくつか不思議な点はあるが、クロであると断定できる証拠はない……そう結論付けられたはずだった。
しかしながら、ここ以外に探りを入れることが可能な情報源がない、という状況に行きつき、彼女は潜入を余儀なくされた。
「でも、どうしてわたしだったの? こういうのって、お兄ちゃんの方が向いてると思うんだけど」
『レヴィ9、任務中だぞ。……あいつは後々大きなヤマが控えていて、今は動かせないんだ。だからそっちに回ってきた。悪いな』
「それじゃしょうがないね……ウチ、いつも人手不足だもんね」
七海は音もなく立ち上がる。視線の先に巨大な邸宅を見据えると、覚悟を決めたように一つ頷いた。
「いつでも行けます」
『では、任務を開始する。異常があったらすぐ報告するように。いいな』
「了解。レヴィ9、行動を開始します」
通信を切ると、七海はそろそろと移動し始めた。あらかじめ目星をつけておいた裏口に回り、解析済みの電子錠を解錠する。
そうして彼女は、巨大な城の如き威容の豪邸へと足を踏み入れた。
そこが、一度入れば逃れられぬ魔窟であるとも知らずに。
(セキュリティの解除成功……うん、上手くいった)
警報装置がまた一つ解除される。月明かりだけを頼りに、七海は真っ暗な家の廊下を進んでいく。
豪華な造りに比して、備えられたセキュリティは一般的な家庭と同レベル。彼女にしてみれば簡単なものばかりだ。
故に、当然の疑問が湧いてくる。
(本当にこんなセキュリティで、機密を守る気あるのかな?)
おおよそ重要な情報を保管しているとは思えないほどに警備は手薄。この程度のザルなセキュリティでは、いくらでも盗んでくださいと言っているようなものだ。
彼女の脳裏にチラつくのは、罠の可能性。わざと隙を見せてこちらを誘き出そうとしている――そうでなければ、ただの間抜けだ。
故に七海はより慎重に、奥へ奥へと進んでいく。
だが彼女は気付いていない。そこに足を踏み入れた時点で、既に勝敗は決しているという事を。
やけに扉が多い廊下の、その中間地点。事前調査でアタリを付けた目的地のうち、最初に怪しんだ部分と寸分違わず同じ場所。ほんの少しだけ、光が漏れ出している部屋があった。
そこに近付くにつれ、何か甘ったるい匂いが彼女の嗅覚を支配し始める。
やがて、その扉の向こうから、くぐもった叫び声が七海の耳に届いた。
「……ぉぉっ、おぉぉぉ……」
(えっ!? なに、何の音!?)
恐怖でたまらず彼女は足を止めてしまう。だが、その発生源こそが彼女の第一目的地であるのだ。
後回しにすることも考えたが、意を決して扉を開けた。
少し考えれば分かる事だった。
扉の隙間から漏れる光があるという事は、その部屋には高い確率で誰かがいるという事である。
人がいる部屋に侵入するというのは、彼女の制服に備えられた光学迷彩の存在を以てしてもリスクが高すぎる行為だ。
七海とて、それが分からぬ馬鹿ではない。
だが、肺まで満たすかのような不思議な香りが、彼女の判断を鈍らせた。
彼女が吸い込んだそれは、部屋の中で行われる情事によって振りまかれた、あらゆるメスを発情させてしまう淫香であったのだ。
それを嗅ぎ続けた時点で、彼女の運命は決していた。
ほんの少し、視界が通る程度に扉を開けて、中を覗き見る七海。
部屋に鎮座する巨大な寝台の中心部、そこにあったのは。
「お゛お゛ぉぉぉぉぉぉっ♡ お゛っ♡ お゛っ♡ お゛ほぉぉぉぉぉっ♡」
四つん這いになりながら獣のように喘ぐ美少女と。
「ふぅぅぅ、来海のマンコ締まり良すぎだぞぉ」
そんな美少女の尻に後ろから腰を打ち付ける、醜く太った一人の男。
その男の名前は、七海も知っていた。
片丘太志。普通の家に生まれ育った、どこにでもいる普通の男。
(ああぁぁ……お取り込み中失礼しました……)
まさか情事の最中とは思わず、内心で謝る七海。
だが、視線はベッドの上の二人から外せないでいた。
人の声とは思えぬほどの嬌声。乱れる髪。その痴態を見ていれば、それがどれほど気持ち良いのかが分かってしまう。
何故なら、七海も一人の女であるから。兄である暁と何度も身体を重ねたことがあるからこそ、分かる。その少女は、快感によがり狂っていると。
だが、何がその少女をそこまでさせるのか。彼女と交わっているのは、醜い贅肉で腹をでっぷりと肥やした冴えない顔の中年男性。そんな人物とするセックスの何が気持ちいいのか、七海には想像できない。
しかし、答え合わせの時間がやってきた。男は動きを止め、腰を打ち付けたまま身体を震わせた。
かれこれ数分間もそうしていたが、やがて男は数歩後ろに下がる。
ズルズルと女陰から引き抜かれたモノを見て、七海は目を丸くした。
(何、あれ……暁君のより、ずっと大きい……♡)
男の股間にあったのは、彼女が知る男の象徴とは一線を画す代物。太さも長さも、彼女が恋する兄のそれと比べて数倍以上はあるペニスであった。
先刻までの少女の乱れように、七海の中で辻褄が合ってしまう。
(あんなの入れられたら……絶対気持ちいい……♡)
無意識のうちに、七海の手が自身の秘部に伸びていく。タイツに包まれたそこを指でなぞると、これまで感じたことのない快感が彼女を襲った。
(嘘っ♡ 暁君でするより、ずっと凄いっ♡)
最早人目を憚る余裕もなく――あるいは、光学迷彩があるからと油断していたのか。七海の指遣いは、どんどん荒っぽく、激しくなっていく。
布越しになぞるだけでは足りない。直接、膣を掻き回したい。彼女の全身を焼き焦がさんなかりの熱情は、七海の理性をあっという間に刈り取っていく。
(欲しいっ♡ おっきなおチンチンでおまんこズポズポホジりまくって欲しいっ♡ 指だけじゃ物足りないよ……♡)
故に、気付けなかった。
自身の秘部からなる水音が、誤魔化しの利かない音量になっていたことも。
それを聞きつけた刺客が、背後に立っていることも。
「あは、敵陣でオナニーとは不用心ですねぇ」
驚愕で飛び上がりそうになる七海。だが、彼女は更に衝撃を受けることになる。
虚空から、別の声が聞こえてきたのだ。
「なかなか高度な隠蔽術を使っているようだけれど、残念だったわね。妾たちには、アナタを感知する方法があるのよ」
滲み出るかのように、狐の面を持った少女が何もない空間に現れる。少なくとも、真っ当な方法で実現可能な芸当ではない。即ち、
(やっぱり、アストラル――)
「というわけで……一名様、ごあんなーい」
「抵抗してもいいけれど、命の保証はないわ。それだけ覚えておいて」
歯噛みしながら、七海は迷彩を解く。姿を現した少女の両腕を、二人の刺客はゆっくりと引いて、男の元へと誘う。
だが彼女はそんな状況下でも、身体の火照りを抑えられなかった。
まるで……この後の展開を想像して、興奮しているかのように。
連れてこられた少女を見て、男はふごふごと鼻を鳴らした。
「うひょー、可愛いねぇ。もしかして、この子が?」
「はい。最近太志さんの周りをうろついていたスパイです」
「へぇ……」
下卑た欲望に塗れた視線が、七海の全身を舐め回すように上下する。
普通なら嫌悪感で吐き気すら催すであろうそれすらも、今は七海の興奮を高める材料でしかない。
「それで、どうするのかしら。この子、アナタに抱いてもらいたいようだけれど?」
「ほう? というと?」
「あっ、それはっ」
七海が慌てて言葉を遮ろうとするが、もう遅い。
「この子、部屋の前でオナニーしてたわよ? アナタたちのセックスを食い入るように見ながらね」
「ワタシが後ろに立っていることにも気づかないほど熱心に、です。太志さんも罪な男ですねぇ、あは」
「ほほぉ」
それを聞くや否や、男は七海の股座に手を伸ばした。恋人がいる女性として、組織の一員として、今すぐ跳ね除けねばならないその手を――七海は、抵抗せずに受け入れた。
予想通り、クチュリという水音。
「もうびしょ濡れじゃないか」
「……っ♡」
羞恥を煽る言葉が、彼女の興奮を更に高めていく。
「よし、決めた。この子もオジサンの女にしちゃうぞぉ」
男が宣言するのを、どうやら他の女たちは分かっていたようだ。
「そう言うと思ってましたよ」
「ええ、そうでなくては太志じゃないもの」
穏やかな、しかしどこか淫靡な笑みを浮かべた少女たちは、邪魔をしないよう隣室へと消えていく。
「さあ、こっちに来なさい」
男に腕を掴まれ、ベッドに仰向けで寝かしつけられるまで、七海は一切抵抗していなかった。
彼女の思考を支配していたのは、彼女の前でずっとその威容を誇り続けていたペニスのことのみ。
タイツとショーツに包まれた七海の股間に男が顔を埋め鼻を鳴らすその最中も、彼女はセックス以外に何も考えられなかった。
(はやくっ♡ はやくはやくはやくっ♡ あのおっきなおチンチン欲しいっ♡)
やがて男は、タイツもショーツも脱がし、七海の下半身を丸出しにさせる。恥じらいに顔を赤らめる彼女の表情が、男の劣情を誘った。
「それじゃお待ちかねのチンポ、たっぷり味わわせてあげるからねぇ」
男は無遠慮に七海の両足を掴み、股を広げさせる。ペニスの先端が、七海の秘裂と触れ合った。クチュクチュと音を立てて、焦らすように穴の周りを擦る。
(すご……間近で見るとよくわかる……♡ お兄ちゃんのよりずっと大きくて……♡ ……お兄ちゃん? そうだ、わたしにはお兄ちゃんが――)
そこでようやく、恋人のことを思い出した七海。これまでの思い出が一気にフラッシュバックし、兄に対する罪悪感と男に対する抵抗感が辛うじて生まれた。
「あっ、あのっ! やっぱりここまでにっ」
「もう遅いよぉ、ふんッ!!」
なけなしの抵抗を、男は意にも介さなかった。一息で、最奥までペニスを突き入れる。
「お゛ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉっ!?♡」
たった一突きで、七海にとっての「男」は塗り替えられた。
未知の快感に彼女は目を白黒させる。兄の形しか知らない膣穴が、中年男のペニス用に無理矢理押し広げられていく。
兄としていたセックスが、お遊びであったと否が応でも思い知らされる。
「うおぉ、キッツ……これは開拓のし甲斐があるぞぉ」
「へ、何を……お゛ぉっ♡」
男はゆっくりと抽送を始めた。亀頭が最奥を突く度に、最愛の兄との思い出がひび割れ、消えていく。
「お゛っ♡ お゛っ♡ やだっ♡ やだっ♡ お兄ちゃんがっ♡ いなくなっちゃうっ♡ お兄ちゃんのことっ、思い出せなくなっちゃうっ♡」
「前の男なんて忘れさせてやるッ、ふんッふんッ!」
顔も知らぬ兄に対抗心を燃やしたのか、中年男の腰遣いはより激しさを増した。
「う゛お゛ぉぉぉぉぉぉっ♡ お゛っ♡ お゛っ♡ ひぐっ♡ うっ、ぐぅぅっ♡ う゛ぅぅぅぅぅっ♡」
兄としていた時とは比べ物にならないほど大きな快感が、津波のように七海を襲う。男のピストンは兄と比べて乱雑だったが、大きく張ったカリや竿が性感帯を余すところなく抉り、撫でるため、兄とでは得られないエクスタシーへと七海を追い込むのだ。
(ダメっ♡ イったら終わるっ♡ お兄ちゃんのこと完全にどうでも良くなっちゃうっ♡ それは絶対ダメっ♡ でも――)
「イっ、ぐっ♡ イぐイぐイぐイぐっ♡ ふっ、ぐぅっ♡ お゛っ♡ お゛っ♡ お゛っ♡ お゛ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ♡」
絶頂に至るまいと我慢していた七海だったが、所詮は無駄な抵抗だった。中年男のペニスに最奥をゴンゴンと殴られ、牙城はあっさりと崩されてしまった。
「う゛お゛っ♡ まってっ♡ いまイってるっ♡ イってるのにっ♡ い゛っ♡ あ゛っ♡ あ゛っ♡ あ゛ぁぁぁぁぁぁぁぁっ♡」
男は七海の絶頂などお構いなしにピストンを続ける。過剰な快感が彼女の脳内でスパークするように弾け、知性をドロドロに溶かしていく。
「お゛っ♡ お゛ぉっ♡ ……んむぅっ!?♡」
獣のように喘ぐ七海に、中年男の太った身体が覆い被さった。そのまま顔を合わせて唇を重ねると、七海の口内に舌を捻じ込んでいく。
「んむぅぅっ♡ ちゅるるる、ぢゅぅぅぅぅぅ♡」
(――あっ、これ、ダメ♡ ……もう、暁君なんてどうでもいい♡ おじさんのこと、好きになっちゃう♡ すき♡ すきすきすきっ♡)
「んんっ、むぅ……♡ しゅき……♡ おじしゃん、しゅき……♡」
声に出せば、ますます想いは「本当」に変わっていく。彼女の最愛の恋人は、かけがえのない時間を共に過ごした義兄ではなく、眼前の冴えない中年メタボオヤジになってしまった。
「しゅき、らいしゅき……♡ もっと、もっと……♡」
蕩けた瞳でおねだりする七海の顔が、男の性欲を無自覚の内に煽る。
「ぐふふ、オジサンも好きだよぉ。一目見た時から絶対お嫁さんにするぞって思ってたんだぁ」
「嬉しい……なる、なります♡ わたし、おじさんのお嫁さんになりたいです♡」
七海の心は完全に陥落し、白旗を上げていた。脂ぎった中年男の全てを受け入れ、愛してしまう。快感に流され、そうすることを選んでしまった。
だが、彼女に後悔はない。あるのは淫靡な未来に寄せる期待と、眼前の中年男への恋慕のみだ。
「ぐひひっ、プロポーズ成立だねぇ。記念のザーメン、たっぷり注いであげるよぉ」
「うん、うんっ♡ おじさんの精液、わたしのおまんこに全部出してっ♡」
男は腰の動きを速めた。せり上がってくる粘っこい白濁汁を最高に気持ち良く吐き出すために、思いやりの一切ないピストンを続ける。
そんな身勝手なペニスを、七海の膣穴は優しく受け止め、全体で愛撫する。子宮口はペニスに何度も吸い付き、恋人のキスのように何度も何度も子種をねだる。
「くっ、出るぞッ! 中で受け止めろッ!」
「お゛ほぉっ♡ お゛っ♡ お゛っ♡ お゛ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉっ♡」
亀頭の先端が、子宮口に押し付けられた。精液は子宮の内壁をばしゃばしゃと叩き、あっという間に満杯にしてしまう。
「おじさんっ、すきっ♡ すきすきすきすきっ♡ キスしよっ♡ ちゅむっ、ちゅぅぅぅぅぅぅっ♡ れろれろれろれろ、ぢゅるるるるるるっ♡ あっ、まだ出てるっ♡ 射精も長いっ♡ かっこいいっ、すきっ♡」
五分以上もかけて精液を吐き出した男は、七海に覆い被さったまま荒い息を整えながら囁いた。
「ふぅ……最高だったよぉ、君のマンコは」
「ありがとうございます♡ それで、あの……さっきのこと、なんですけど♡」
「さっき? どれのことかなぁ」
「えっと…………お嫁さんになりたい、って話です♡」
「ああ。でもオジサン、君の名前も知らないんだよねぇ」
「そっか……わたし、スパイだった……」
七海は、最早自分がなぜここにいるのかすらも忘れてしまっていた。それほどまでに、彼女にとって最も優先するべきことが塗り替えられてしまったのだ。
故に、更に禁忌を○す。敵に名前や素性が割れていないという有利な材料を、自分から捨てた。
「わたしは、在原七海っていいます。橘花学院に通う学生です」
「七海か、可愛い名前だね。オジサンは片丘太志だよぉ」
「太志さん……太志さんこそ、格好いい名前ですね♡」
決してそんな事はないはずなのに、今の七海にとっては平凡極まる名前すらも愛おしい。
(ああ……やっぱりわたし、このおじさんの事、好き♡)
そんな彼女の内心に応えるように、男は七海の目を見つめて告げた。
「オジサン、本気だよぉ。七海ちゃんは一生オジサンが幸せにするからねぇ」
「……っ♡ 嬉しいっ♡ わたし、太志さんに失礼な事ばっかりしてたのにっ、いいんですか?♡」
「過去の事なんて気にしないよぉ、これからはオジサンとラブラブ夫婦なんだもんね?」
「……はいっ♡ わたし、太志さんのことが好きですっ♡」
「嬉しいねぇ……」
どちらからともなく、唇が交わされた。それまでの貪るようなディープキスとは違う、心を確かめ合うバードキスの雨が降る。
男は七海の艶やかな金髪を撫でた。女の命とも表されるそれに触れられて、七海は喜びに身をくねらせていた。
彼女もお返しとばかりに、中年男のだらしなく弛んだ毛むくじゃらの肌を愛おしげに撫でさする。
「七海、愛してるぞぉ」
「わたしも、愛してます♡ ……あの、もう一つ、ワガママ言ってもいいですか?♡」
「いいよぉ、奥さんのワガママだもん。ドンと来なさい」
「やったっ♡」
嬉しさのあまり、頬を緩ませる七海。潜入先の要注意人物を前にしているとはとても思えぬ表情だが、それも当然。彼女の眼前に居るのは調査対象などではない。彼女が心から愛してやまない異性なのだ。
「じゃあ、その……太志さんのこと、『お兄ちゃん』って呼んでもいいですか?♡」
「ほほう。それはまたどうしてだい?」
「わたしにとっては、『お兄ちゃん』は一番好きな人だから……もう暁君のことなんか、好きでも何でもないって証拠にしたいんです♡ わたしの一番は、『太志お兄ちゃん』なんだ、って♡」
「ぐふふ。そそるねぇ、興奮しちゃうよぉ。是非とも呼んで欲しいねえ」
「うんっ♡ 大好きだよ、太志お兄ちゃんっ♡」
こうして、学生とエージェント、二つの顔を持つ少女の在原七海は、冴えない中年太りのエロオヤジの妻に堕ちた。
「こちらレヴィ9。本日の任務、完了しました」
夜更け近く。空がうっすらと白んできた頃に、七海は解放された。
『ご苦労だったな、レヴィ9。随分時間がかかっていたようだが、何かあったのか?』
「えっと……」
逡巡する七海。何かはあったが、それを正直に打ち明けるわけにはいかなかった。
それは、恥じらいだとか悔恨だとか、そういう自分に由来する感情ではなく。
愛する男性に万一があってはいけないという、献身的な考えによるものだった。
「今夜は、起きてる人が多くて。別日にしようかと思ったんだけど、目標地点までもう少しだったから深追いしちゃった。それで、抜け出すのに時間がかかって……安心して、誰にも見つかってないよ」
『そうか。ならいいが……それで、何か証拠は掴めたのか?』
「ううん、全然……」
これは本当だった。あの男の背後に何かあるという証拠は掴めなかった。
本人協力のもと調査したのだから、間違いはない。
片丘太志は、完全にシロ。
それが、彼に対する愛情抜きに、七海が出した結論だった。
「だからね、今後も何度か潜入が必要だと思う」
『だろうな……なら、次は他の誰かを――』
「ううん、わたしがやる」
被せるように言う七海に、通話口の向こうの人物は驚いたような声音で返した。
『どうしたんだ? さっきは「適任が他にいる」とでも言いたげだったのに』
「わたしがここまでやった案件なんだもん。どうせなら、わたしが最後までやり切りたいの」
などと言っているが、その実は男と会う口実が欲しいだけだ。
それを知らぬ通話相手は、不思議がりつつもその意思を汲んだ。
『お前がそこまで言うなら……この件はお前に一任しよう。頼んだぞ』
「うん、任せて。それじゃ、切るね」
『ああ、無事に帰って来いよ』
「了解」
通信を切ると、七海は一つ溜息をついた。どうにか誤魔化せたことを安堵するものだ。
彼女は迎えの車に乗り込み、背後に遠ざかる豪邸に思いを寄せる。
(……またね、太志お兄ちゃん♡)
そして七海は思惑通り、任務を理由に何度も男と逢瀬を重ねていった。
時には男の望むまま、彼女の知る美少女を軒並み男に差し出して。
裏では、男と共に済むための準備を着々と進めて。
そんな関係が続いたある日。
「さ、今日はビデオレターを撮ろうか」
いつものように寝室に構える男であったが、そのベッドの横には三脚で固定されたスマートフォンがあった。
「ビデオレター?」
「そろそろいい頃合いだろう? かつてのお兄ちゃんにしっかりお別れしておきなさい」
「ああ、そういう……♡」
同人文化にも詳しい彼女は、その意味を察知したようだ。
男がタイマーをセットし、ベッドに腰掛ける。七海も服を脱いで男の膝の上に座ると、満面の笑みを浮かべた。
ぽこん、と録音開始を告げる音が寝室に響く。
「暁くーん、見えてるかな? 今日は暁君に、わたしからお別れのビデオレターを送るね」