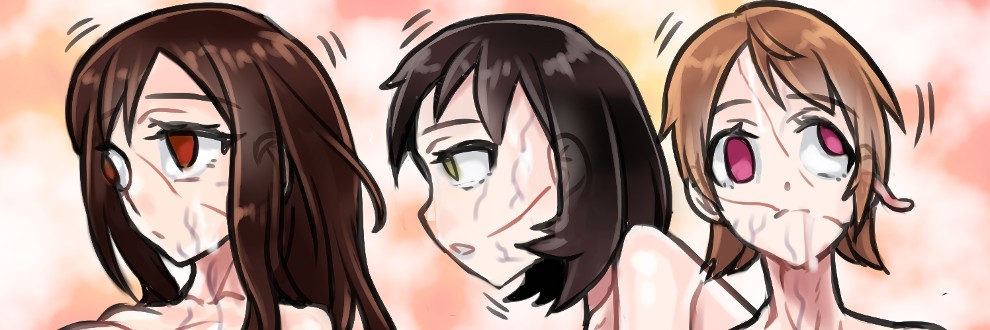『パラサイト新シリーズ(仮)』➀
Ci-enにて先行公開。
加筆・修正して後ほどPixivに掲載予定。
第1章
*
木下翔太は高校の同窓会へ向かうために駅を降りた。まだまだ残暑が厳しい10月ということもあり、じんわりとかいた汗をぬぐいながら、スマホの地図を開いて会場のホテルへと向かう道を確認した。駅からの通り道には木々が並び、それらは少しずつ赤や黄色へと色づき始めていた。
「思ったより暑いな…」
そう呟きながら、歩道を歩き始めた。卒業して2年、大学生になって久しぶりに高校時代の友人たちと再会する。もちろん数人とは連絡を取り続けていたが、ほとんどは違う。みんながどんなふうになっているか、楽しみにしていた。
その時、後ろから聞き覚えのある声が響く。
「おい!翔太じゃん!」
振り返ると、増田健が手を振りながら駆け寄ってきた。彼は中学高校と仲が良かった友人の一人だ。ただ、大学は離れたところに通うことになったので、連絡を取るだけで会うことがなかなかなかった。
健は昔と変わらない快活な笑顔を浮かべていた。それを見るなり、翔太はすぐに喜びと懐かしさがこみ上げてきた。
「健か!久しぶりだな!」
健は少し息を切らしながら、嬉しそうに近づいてきた。
「駅で見かけたから、急いで追いかけてきたんだよ。全然変わってないな」
「そっちこそ、元気そうで何よりだよ。ほんとに懐かしいなあ」
2人は会場に向かって歩き始めた。通りにはカフェやレストランが並び、テラス席では学生やカップルが楽しそうに過ごしていた。その様子をみて、翔太は昔の自分たちをぼんやりと思い出していた。
「大学はどうだ?」
シャツを動かして暑さを紛らわしながら、健が聞いてきた。
「いい感じだよ。勉強で苦労してるけど、新しい友達もできて楽しいよ。お前は?」
翔太は歴史学部に通っている。その学部を選んだ理由はなんとなく歴史科目が好きだったから、というぼんやりとしたものだった。しかし今となっては積極的に好きと言えるくらい、学ぶのは楽しいと感じていた。
「俺も同じ感じかなあ。あ、彼女とかいないのか?」
「いや、いないよ。なんかそういう縁に恵まれなくてな…」
にやにやする健を適当にあしらうように答えた。
「なーんだ。つまんないね。と、いっても俺もいないけど…」
「おいおい、人のこと言えないじゃないか」
こうやってくだらないやりとりをするのは、やっぱり楽しい。そこからお互いが大学で何を学んでいるか、バイトは何をしているか、など話を深めていった。そんなふうに話をしているうちに、2人の間にあった時間の隔たりがどんどん薄れていくようだった。
*
やがて、2人は会場のホテルに到着した。立派なホテルで、中のホールへ向かうと華やかな飾り付けがされており、同窓会の歓迎ムードが漂っていた。すでに多くの過去のクラスメイトたちが集まっており、賑やかな声が響いていた。受付ではホテルのスタッフが名前を確認していた。
「懐かしいなあ、こんなにたくさん集まるとは思わなかった」
健が感慨深げに言うと、翔太も頷いた。
「本当にね。みんな元気そうで何よりだよ」
受付に近づくと、スタッフが温かく迎えてくれた。名前を尋ねられ、2人はそれぞれ名前を告げた。するとスタッフは名簿を確認し、名札を手渡してくれた。どうやら胸につけるらしい。別にたった2年なのだから、顔と名前くらい一致するだろうと翔太は感じたが、みんなそうしているので従った。
2人は改めて会場内を見渡した。懐かしい友人たちの顔が次々と目に入る。
「さ、まわってみようぜ」
「おう」
健が歩き出し、翔太も応じてついていく。広々とした会場には、色とりどりの風船や装飾が施され、各テーブルには軽食や飲み物が並べられていた。そして参加者たちは談笑したり、料理を食べたり、思い思いに過ごしていた。 さっそく見覚えのある友人たちに声をかけ、さっきまで2人でしていたような世間話に花を咲かせた。
たくさんの友人や先生たちとしばらく話した後、翔太と健は用意されたイスに座り、軽食をつまんでいた。
「本当に懐かしいよな、あの時のことがまるで昨日のことみたいだ」
微笑みながら翔太が言うと、健も同意するように頷く。
「ああ、なんだかタイムスリップしたみたいだよ。みんな少し大人になっているけど、根本は変わってないな」
まだ話していない人はいないか、ざっと会場を見渡した。すると、健の視線がふと人混みの中にいる1人の女性に留まった。その様子に翔太も気づき、視線の先をたどると、見覚えのある女性が立っていた。
彼女の名前は水原香織。高校時代、健と香織はどうしても馬が合わず、しばしば口論をしていた。健は香織を嫌っていたし、香織も健を疎んじていた。普段のちょっとしたことで言い争いになったり、グループ活動で意見が対立したりと、二人の間には常に緊張感が漂っていた。あの時のことを思い出し、翔太の表情は一瞬曇った。
しかし健は、不思議そうな顔で話しかけてきた。
「お、おい…あいつ香織だよな…?」
「そうだけど…お前、仲悪かったよな」
「うん…だけどさあ…」
健の様子がおかしい。嫌いな相手を前にしている割に、それほど嫌そうではなかったのだ。むしろ逆ともとれる様子だ。
「めっちゃ綺麗になってないか?!」
「えぇ?…ま、まあ確かに…」
よく香織を見てみると確かに高校の時よりかなり垢ぬけて美人になっている。当時は化粧もしていなかったし、制服姿しか見たことなかったからなのか、違って見えた。
「あいつ、あんなにスタイル良かったんだな」
翔太がぽつりと呟くと、健がおもむろに立ち上がる。
「ちょっと声かけてみようぜ」
「はぁ?大丈夫なのかよ…」
どこか意気揚々としている健に仕方なくついていく翔太。そして人ごみをかきわけ、近づいた。
「お、おい香織か…?」
健が機嫌を伺うように声をかけると、彼女は振り向いた。
近づいてみると改めてその変化に気づく。かつての地味な印象はどこへやら、彼女は輝くような美貌を持つ女性になっていた。長い黒髪は艶やかで、整った顔立ちはまるでモデルのようだった。その様子に2人は驚きを隠せなかった。
「あれ?健くんと翔太くんじゃない」
香織は笑顔で応じた。過去のいざこざはどこへいったのか。
「久しぶり。な、なんか垢ぬけたな…」
そこまで険悪な関係ではなかった翔太が会話を始めてみる。といっても、仲が良かったわけでもない。
「ふふ。そう?ありがと。2人もかっこいいじゃない」
優しいその微笑みは翔太だけでなく健にも向けられていた。それを疑問に思った健は単刀直入に切り出す。
「お、お前、俺とよく喧嘩したよな…」
ちょっと笑ってごまかしながら慎重に話しているのを翔太は察しながら、答えを待った。
「そうね…健くんとはよく意見が合わなくて言い争ったこともあったけど、あれは昔の話。お互い子供だったし」
向こうがそれほど気にしていないことがわかると、翔太はホッと胸をなでおろした。またこの場で火花でも散ろうものなら大変だから。ただ安心しているのは健も同じだった様子で、話をつづけた。
「えっと…香織は大学どこ行ってるんだ?」
「あー。私は高校卒業したあと、専門学校に通って美容師になったの。そして今はエステサロンで働いてる」
当時は翔太も健も彼女の進路を聞いたりする中ではなかったから知らないのも当然だった。
「エステサロンかー。だからそんなに綺麗なんだな」
「あら、ありがと。嬉しいな」
下心はなかったが、ふと口にした言葉に翔太は恥ずかしくなった。目の前の香織の姿を見るとそう思わざるを得なかった。
「あっ…えっと、その…」
「なーに、自分で言っておきながら照れてんだよ」
健が軽く翔太を小突く。それをみて香織はくすくすと笑っていた。しばらくすると、健と香織が穏やかに話している様子をみて驚いたそれぞれの友人が集まってきた。にぎやかに当時のエピソードを話しているうちに、自然と話題が分かれ、翔太と健は同じ部活だった仲間と盛り上がった。香織もまた別の友人たちと近況を語り合い、懐かしさに浸っていた。
*
少しして、翔太は場を離れてトイレに向かった。さっさと用を済ませて、会場へ戻ろうとしたが、女子トイレのほうから何か聞こえてきた。
「ちょっ…!何…!?」
おかしい様子だったが、流石に堂々と女子トイレへ入るわけにもいかなかった翔太はこっそりと聞き耳を立てた。幸いなことにトイレへ出入りする人はいなかった。
「ど、どうしたの…ウゥグッ!」
誰かわからないが、その女性は何か口をふさがれたようだった。そして間もなくおかしな音が聞こえ始めた。
ヌヂュ…ヌヂュ…
気持ちの悪い音が響き、ただ事ではないだろうと感じた翔太はそっと女子トイレを覗き込んだ。
そこには信じられない光景が広がっていた。洗面台の前には2人いたが、その片方は頭がない。というか、頭だったものが割れて、中から生えた触手が、もう一人の女性の口へ入り込んでいた。グポグポと音を立てながら、襲われている女性は白目をむいて苦しそうに痙攣していた。
(…なっ、なんだよ、アレ!?)
翔太は、あまりに非現実的な光景を前にして、どうしたら良いかわからず、固まっていた。しばらくすると頭が割れている女性、あるいは襲っているその化け物は、触手をいれたまま個室トイレのほうへ女性を連れ込み、ガチャリと鍵をかけてしまった。
今、目の当たりにしたものは本当なのか、何か悪い夢でも見ているんじゃないか。よくわからなかった。彼は必死に冷静さを保ち、その場を立ち去るしかなかった。何とか廊下を駆け抜け、会場に戻ってきた。心臓は激しく鼓動しており、冷や汗が止まらなかった。周りの人々は相変わらず楽しく談笑しており、誰も彼の、そしてトイレでの異変に気づいていなかった。
頭を抱えて下を向いていると、ふと声をかけられた。
「どうしたの?翔太くん」
ガバっと顔をあげると、その勢いに驚いた香織の姿があった。
「いや…何でもないよ…」
「そ、そう…?すごい汗だけど…」
香織は心配そうに翔太の顔を覗き込む。思い返せば、香織は高校当時、よく行事では中心になってクラスを動かしていた。それもあって健と言い争うことが多かったのだ。ただ翔太は一方で、クラスメイトのことを気に掛ける優しい一面も持っていることを覚えていた。今の香織の顔は、その時のものだった。
「ありがとな…ちょっと食べすぎちゃったみたいでさ、しばらくしたら治るから」
さっきトイレで目にしたことを言うわけにはいかなかった。せっかく久しぶりに再会した友人たちに、頭のおかしいやつだと思われてしまう。
「ならいいけれど…ゆっくりね」
そういうと香織は会場へ戻っていった。その様子を何となく眺めていた翔太は、あることに気づいた。
彼女は今日、淡いピンクのワンピースを着ている。そして、さっきトイレで女性を襲っていた化け物も同じものを着ていたのだ。
(…ま、まさかな)