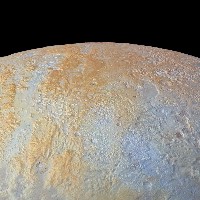「THREESOME」 後編
妹の口からその言葉を聞いた瞬間、メフの全身は凍りつき、目の前が暗くなった。
スピルは、メフの秘密の独り遊びのことを知っていた!でも何故・・・・?
ぐらぐらするめまいの感覚と戦いながら、メフは、会話に耳を傾け続けた。
立ち木を挟んですぐ向こうからは、そんなことはまるで知るよしもないスピルの陽気な声が聴こえてくる。
「ニオイが出てくるとこの先っちょって敏感だから、いじると、あんなにおカタいお姉ちゃんがヘンになっちゃうくらい、ものすっごい気持ちイイみたい。あたしは、やってみても何だか痛いだけなんだけどね。きっとお姉ちゃん、普段あんまりプ~しないでガマンしまくってるからかな。癖になっちゃってて、やめれないみたい。結構よくやってるよ。やってる時は大抵、またやってるなって、すぐピンと来ちゃうの。何でかわかる?」
「・・・えーと」
「ニブいなぁ。お姉ちゃんと一緒だね。お姉ちゃんも自分では何とかごまかせてるつもりみたいなんだけど、実はバレバレなんだよねぇ・・・。だって、お姉ちゃんのニオイ、すごいって言ったでしょ。本人は気がついてなくても、ニオイ、ちょっとずつだけど漏れてたりするのね。くさーーーいって思って目が醒めちゃうことだってあるもん。ね?わかったでしょ。よーするに、お姉ちゃんがそれやってる時に、ウチに来ればいいんだよ。そーっと、お姉ちゃんの部屋の前にでもいれば」
「なるほど・・・そいつはいい」
「でしょー。だけど、何度でも言うけどバレたら一巻の終わりだかんね。お姉ちゃんを本っ気の本気で怒らせたりなんかしたら、とんっでもないことになるかんねっ!それに、あたしまでお仕置きされちゃうかも知れないんだから!」
「バレないさ・・・・キツネの忍び足をなめるなよ」
「それならいいけど。万が一バレたって、絶対の絶対に、あたしから聞いたなんて言っちゃだめよ。約束だからね!」
「よし、約束!スピル、サンキュー」
「絶対、死んでも、お姉ちゃんにすんごくクサいゴーモンされても、あたしのこと言っちゃだめなんだからね!?」
「わ、わかった・・よ・・・ハハ・・」
スピルは、マイクと別れてどこかへ行ってしまったようだった。
おそらく、どこかで道草をくいながら我が家に向かっているのだろう。
それよりも、メフは、これからどうすればいいのかわからなくなった。
混乱した頭のまま、自分でも無意識のうちに、メフはいつのまにかマイクの前へ立ちはだかっていた。
「や、やぁ・・・・メフ。今日も綺麗だね。最高だよ」
思ってもみなかった突然のことで、引きつった愛想笑いを浮かべるのが精一杯のマイク。
「こ、こんなところで会うなんて奇遇だよねえ。うっ、運命のめぐり合わせってやつかも知れないな」
メフは、うつむいてしおらしく目を伏せている。
しかし彼女の尻尾はこれ以上無いほど緊張してピンと張りつめ、ふさふさの毛は扇状に広がって尻尾を実際よりずっと大きく見せており、それがマイクに何ともいえないプレッシャーを与えていた。
一体彼女は、何がしたいっていうんだ?まさか、さっきの会話を聞かれた・・・!?
「ねえメフ・・・・ずっとそこにいたの?」
メフは、うつむいたままこくりとうなずいた。
「じゃ・・・スピルと・・・さっきの話・・・」
しばしの間の後、こくりとうなずくメフ。
マイクは、青くなったり赤くなったりしてうろたえだした。
「何だくそ、メフ、盗み聞きなんて・・・・・ひどいぞ!卑怯だよ!」
「・・・ひきょうで・・・わがままで・・・ざんこく・・・」
「・・・・?・・・と、とにかく、そっちがそうくるなら、こっちにだって考えがある。メフ、単刀直入に言うよ。きみの例の一発のニオイって、信じられないくらいスゴいんだってね?ぼくはねえ、学術的見地から、非常にそいつに興味があるわけさ。是非そいつを、生で体験させてもらえないかなぁ。おおっと勘違いしないでくれ、ぼくの毛皮を汚したりしないでくれよ?スピルもやってくれたことだし・・・・ちょうどいい、そこらの草むらに向かって一丁、頼むよ」
「・・・・・」
メフは黙って、力無く首を横に振った。
「ああ、嫌だっての。うん、そうだよね。何でも言いなりってのはちょっと、プライドが傷つくかもしれないなあ。でも、そうしないと、もっとプライドを傷つけられることになるかもよ。これはあくまで仮の、もしもの話でしかないけどさぁ・・・。ぼくがもし、さっき聞いたばかりのきみの素敵な秘密のことを、この森のいろんな連中に話して回ったりしたら、どうなるだろうね」
「・・・・・・・・・」
「あっ、そうだ。今ここでやってもらおうか・・・。ふふふ。そう、スピルが言ってたその秘密の、臭腺オナニーとやらをさ」
「・・・・!」
メフの尻尾が、その言葉にぴくっと反応した。
「やってくれるね?そしたらぼくもそいつを秘密のままにしとくと約束する。全部忘れてあげるよ。どうする?メフ」
メフは、あたたかな草の上にゆっくりと身を横たえた。
傍らには、固唾を飲んでなりゆきを見守る、マイクの姿。
ちょうど、背の高い草が辺りを囲うようにして密生している場所で、他からの目は届かない。
メフは半身になり、いつものように瞼を閉じて、尻と下腹部に意識を集中させた。
草の擦れる微かな音と共に、白黒の大きな尻尾が背中側にぐっと反り返った。
これで、「おなら」の噴射口は、準備OKの状態となった。
メフは剥き出しになった自分の肛門に、マイクの無遠慮な視線を痛いほど感じていた。
スカンクの肛門は、その用途による発達のため、他のケモノと比べて、段違いの大きさを備えている。
もはやエロティックとさえいえるその迫力に、マイクの目は釘付けとなっていた。
やがて肛門の内側から、何かの塊がゆっくりと隆起してきた。
花の蕾のような皺を押し上げてそこから顔を覗かせたのは、一対の、鮮やかな桃色をした、形も大きさも乳首そっくりの柔らかそうな突起だった。
「んっ・・・・はぁ・・ん・・」
指先が乳首のようなその突起に触れる度に、メフの口から甘い吐息が漏れた。
「んっ・・・・んっ・・・んっ・・!」
甘い声は、どんどん高まっていくようだった。
しかし、一向にそれらしいニオイはしてこない。
しびれを切らしたマイクは、もう少しだけ近くに寄って、メフの肛門を覗き込んだ。
「・・くぅ・・んんんーッ・・あっ、あッ!」
メフの背がぐっと反り、やがて全身が小刻みに震え出した。
きゅうっと、下半身の筋肉が収縮していくのが、マイクの目にも見てとれた。
と、例の乳首に似た突起の周囲を取り巻いていた柔肉がみるみるうちに盛り上がり、一瞬、まるで小型の乳房さながらとなった。
ハッとしたマイクが身を引いた時にはもう、全てが遅かった。
プスーーッ!
突起の先端がはじけ、濃い黄色をした液体が上空に向かって、恐ろしい程の勢いで噴射された。
辺り一面の空中に飛び散った黄色い飛沫は、瞬く間に細かな霧となって、マイクの上にも降り注いだ。
「あっくそ、毛皮に・・」
そう毒づく余裕のあったのもつかの間、やがて、こうなっては逃れられない悲惨な運命がマイクを襲った。
「ふッぎゃあああーーーーああーーーーあーーーーああああーーーーーー」
マイクは絶叫しながら横ざまにぶっ倒れると、半狂乱になって鼻を地面に擦りつけ始めた。
そんなことをしてももちろんメフのニオイからの開放はかなわず、少しすると、臭さのあまりもんどりうってのたうち悶える時間がしばしの間続くのだった。
「ぐあっぷ、くさ、くさ、くさ、くさいぃくさいぃーーー!くさあい、くさあああ!!」
それがおさまると、また鼻を地面に擦りつけはじめる。
無間地獄のような繰り返しだった。
「ごぼげぼ、げおっ、くさァ、くさューーッ!メフ、だずげっ、イキがぐるじ、ふげっ、ギャッ、ヒィーーーッハヒハヒ!!」
これ以上ないと思えるほど苦悶しつつ、マイクの股間の一物は何故か目一杯に勃起していた。
半身を起こし、しっとりとうるんだ目でマイクの暴れようをじっと見つめていたメフは、吐息混じりにつぶやいた。
「ね・・・・?わたしの・・くさくて目が回るでしょ。くさくて息もできないでしょ。すごく、いっそ死んじゃいたいくらい、苦しいでしょ・・・。だからね、だめ・・・なのに・・・・・・・・ぁ・・ン」
「はヒィーッ、はヒィィーッ!」
「・・・あなたをこのままにはできないし、こうなったらもう仕方・・ないよね・・・ンんっ」
「ヒィーッ!ハヒハヒ!ハヒハヒ、ハヒハヒ」
「かわいそうだけど、はぁっ・・はぁ・・・も、もっ、もういっかい、だけぇ・・」
メフはくるりと後ろを向いて尻を突き出し、敵に「おなら」をひっかけるときの姿勢をとった。
「はぁっ・・、はぁっ・・・、あ、あなたに、もっと、ちゃんと、思い知らせてあげるためなんだから、ね・・・?」
ふさふさの尻尾をふわりと持ち上げると、メフはあのピンク色をした尻の穴を、見せつけるかのようにマイクの方へと近づけはじめた。
「・・・ねぇマイク・・わたしの秘密、守ってくれるでしょう?でもね、もししゃべったらどうなっちゃうかは・・んぅっ・・・ちゃんと知っててもらわなきゃ、ぁンっ、いけないよねぇ?ねっ、マイクぅ?ね・・・?」
既に弱り切っていて声もないマイクには、仰向けに転がったままヒクヒクと全身を震わせながら、ゆっくりと後ろ向きで近寄ってくるメフの姿をただ見上げていることしかできなかった。
辺り一帯は液が気化してできたガスの厚い雲にすっぽりと覆い尽くされ、もはやマイクが新鮮な空気を吸うことは不可能だった。
そんなマイクの傍で、メフはしばしの逡巡の後、思い切ったようにその大きな尻をまた一段とマイクの顔に近づけ、
シュー・・・
と、ほとんど音も無く、しかし激烈にくさい一発を浴びせかけた。
涎と鼻水と泥でめちゃめちゃに汚されて今は見る影もないマイクの毛皮へ、新たに特濃の黄色が塗り重ねられた。
「ほぎャァァァーーーァブぶぶブゥーーーーーー!!!ブクブクブクブク」
「ぁ・・っ・・・・ぁはあ・・・。何て顔っ・・ひどい顔・・・どう、くさい?そぅ・・そんなにくさいの。苦しいのね・・ぷぷ・・ふふ・・っ、ハァッハァッ。わ、わかった・・・?ハァ、ハァ、こっ、こうされちゃうの。ペラペラしゃべっちゃうような悪いお口はね、こうやってふさがれちゃうの・・ね?マイクぅ・・ゥンっ」
宙を掻きむしりながら弱々しくのたうつマイクの様子を見守りつつ、メフは今までに無い初めての快楽に火照った顔でうっとりとそうつぶやき、そして背骨を駆け上がる官能に身悶えながら、さらに「おなら」を放った。
シュゥー・・
右から左へなぎ払うように乱れ撃たれた無数のくさい飛沫に口内を直撃され、マイクは繰り返しえずきながら口の端から泡を吹き続け、そのままもう何もわからなくなっていった。
マイクが目覚めたのは、夜の帳の中だった。
昼間と同じ、仰向けの姿勢のまま。
目覚めるきっかけも、気を失った時と同じ、強烈なメフの「おなら」の耐え難い悪臭によってだった。
「ぅ・・・う・・・ゲボッ・・・・ゲホゲホ」
立ちこめる臭気がひりひりと沁みて、まともに目を開けることもできない。
頭がぐらぐらして、ひどい風邪をひいた時のように、まるで体に力が入らない。
多少は慣れてきたものの、メフの残り香は未だに、呼吸のたびに鼻をひきちぎりたくなるほどの臭さだった。
こうして何とか生きていられたのが不思議なほどのスカンク・ショック。
マイクは、うかつにメフにちょっかいを出してしまったことを、激しく後悔していた。
が、その一方で、意識を失う直前に感じた、頭の芯がとろけそうになるほど甘やかな、えも言われぬ恍惚感をも思い出していた。
あれは、何だったんだろう?
倒れたままメフのくさい残り香を嗅ぎ続けているうちに、またもやマイクの股間に変化が起き始めた。
いつかどこかで知った、フェロモン、という言葉がマイクの頭に思い浮かんだ時、ガサガサという音がして、丈の高い草をかき分けつつ、小さな黒い影があらわれた。
「マ~イ~ク~ぅ!!よくも、よくも!」
聞き覚えのある声がした。
「ぁ・・・、ス・・ピ・・・ル」
黒い影と見えたのは、スピルだった。
暗いのと目がよく開けられないので、マイクには彼女の表情が読み取れなかったものの、スピルの声を聞いて、彼女が何の目的で来たのかマイクにはすぐにわかってしまった。
「ぉ、おい・・・ち・・・ちが・・・」
「いいわけはききたくなぁい。よくもあっさりお姉ちゃんにバラしてくれたわね!あたし、お仕置きされて死ぬほどひっっっどいめにあったんだから。まあ、マイクもそうみたいだけど?あたし、そんなの知らなーい。とにかく、このお礼はさせてもらうんだかんねっ、カクゴしてよね!」
「ス、ピ、やめ、なにする、つもりだ」
スピルの後足がサッと宙に舞った。
スピルお得意の、逆立ちポーズである。
スピルは、逆立ちのままトコトコと小刻みに歩きはじめた。
どうやら、目標との距離と角度を調節しているらしい。
「それじゃ約束どおり、想像もつかないほどヒドイめに、あわせてあげるぅ」
マイクは、内心ほっとしていた。
スピルのニオイなら、既に経験済みだ。
スピルの言う”ヒドイめ”があれで済むなら、御の字だ・・・・
しかし、そんなマイクに冷や水を浴びせるようにスピルの笑い声が響いた。
「くふふふふっ。何を安心してるのかな~?マイクって、ほんとにおニブさんねえ。今朝してあげたのは、ぜーんぜん本気じゃなかったの。だって、がっかりしちゃうくらい臭くなかったんでしょ?そーんなゆるゆるなニオイで、牙をむいてハァハァいっちゃってるヤバいやつらをどーにかできるわけないじゃない。お姉ちゃんにかなわないってのは本当だけどさ。でも、あたしだってスカンクなの。マイク、どう?あたしのすごいクサいの、嗅いでみたかったんでしょ」
「や・・・やめろ・・・わああああっ」
「何よ!お姉ちゃんのは喜んで嗅げて、あたしのは嗅げないってゆーの?ほらほら、こーゆーニオイがよかったんでしょ、マイク~?今さら逃げれるなんて、思わないでよねっ!」
そう言ってスピルの尻がグッと斜め上方に突き出されたかと思うと、次の瞬間には、既に無音のまま噴射されていたスピルの臭液が、月光を反射してきらきらと輝きながら、マイクの全身に降り注いでいった。
スピルの本気は、彼女の言葉通り、今朝の時のように生やさしい香りではなかった。
メフの「おなら」が、とてつもなく長い時間をかけてグツグツに濃く煮詰められ熟成された、ニンニクにも似た刺激臭と糞便にも似た腐敗臭のハイブリッドだとするなら、スピルのそれは極限まで腐りに腐った卵臭とでも呼ぶべき代物だった。
スピルに浴びせられた一発に加え、辺りになお濃く漂う、メフの強烈な残り香・・・・
この世にもうこれ以上は無いほど特濃の、ニンニク臭、糞便臭、腐った卵の臭い。
「むぷおっ、ぐぜ、ぐぅぜぇええーっぷぐっ、ごぼっ、むぷっぷぷぷゥ!!」
二匹のスカンクのあわせ技に、マイクはまた、半狂乱になって地面の上を転げまわるしかなかった。
「ど~お?いいにおいでしょ。せっかくご馳走になっちゃったしぃ、もう少しサービスしてあげる。美味し~美味し~ご馳走ちゃ~ん、あたしの中でほらね、こんなになっちゃいましたっ」
スピルの逆立ちした尻がマイクの方にグッと突き出され、再び噴射されたスピルの「おなら」が、きらきら光る霧となってマイクの毛皮を濡らしていった。
腐れたタマゴの悪臭が、ぐんと強くなる。
それから逃れようとして身をよじると今度は突然、メフのあの大きく膨らんだ肛門に鼻をまるごと突っ込まれたような感覚に襲われた。
辺りに漂う猛烈な糞臭を放つメフのガス雲、それが一段と厚く濃く立ちこめる「ガス溜まり」の位置へと、うかつに顔を突っ込んでしまったためだった。
「ゴボゲボ!ゲブーッ!ゴボゲボ!!」
「マイク・・・え・・・何、それ・・・」
スピルはあっけにとられて、とん、と後足を下ろした。
スピルの視線の先には、目を見張るほど大きくいきり立って反り返ったマイクの股間の一物があった。
ニンニク臭、糞便臭、腐乱した卵の臭い。
そしてそれら全部が混ぜ合わされた、嗅いだ鼻がもげ落ちるかと思われるほどの刺激的な極悪臭。
あのおしとやかなメフや可愛いスピルから、何で、どうして、これほどまでにくさいものが・・・!?と、涙と鼻水にまみれながらマイクは思った。
しかしその間にも嗅がされ続ける臭気に頭の中をぐちゃぐちゃにひっかき回され、やがてマイクにはそんなことも考えられなくなった。
永遠に続くかに思える激臭地獄の底でマイクは、ケシ粒のように小さな小さなメフとスピルが鼻の穴を通って自分の頭の中に入りこんできた幻覚を見ていた。
右の脳みそに入り込んだメフは、脳の突起に自分の臭腺を押しつけて悶えはじめた。
スピルは、左の脳みその中で逆立ちをはじめた。
メフの臭腺から黄色い液がまき散らされて、脳がくにゃりと溶けていく。
スピルの逆立ちした尻から黄色い霧が噴き出しはじめ、脳がどんどん腐って落ちる。
いつのまにかメフとスピルは、溶けかけ腐りかけた脳のなれの果てに各々の尻を擦りつけて、甘い声を上げていた。
よく見ればその脳みその残骸は、何だか、そそり立つ柱のような形をしていた。
まるで火山の噴火のように、柱が白濁した奔流を噴き上げる。
マイクは、スカンクたちのくさい毒液に全身を犯されながら、何度も何度も射精していた。
「メ・・・フ・・・・スピ・・・・・ル」
蚊の鳴くような声でスカンクたちの名を呼んだのを最後に、マイクは白目をむき舌を長く垂らしたまま、再び完全に気を失ってしまった。
「・・・マ・・・マイクったら、もうぅ・・・なによ、これじゃお仕置きなのか何なのか全然わからないじゃない!それにしても・・・・すっ・・ごい気持ち良さそーにイッちゃったけどぉ、やっぱり変態さんだったのねぇ・・・・」
スピルは、地面にぐんにゃりと力無くのびたマイクの体を眺めながら、独りほくそ笑んだ。
何かを思いついたらしい。
「お姉ちゃん、世の中って、お姉ちゃんが思ってるより、ずっと広いんじゃないかなぁ」
マイクは夢うつつのなかで、空を飛んでいた。
じつは飛んでいたのではなく運ばれていたのだということに彼が気付いたのは、どこかの家のベッドの上に体ごとドスンと投げ出された時だった。
「・・・あれれ?目が覚めたみたい」
「もう・・スピルが乱暴にするから・・」
マイクの頭上で声がする。見上げると、彼を囲むようにしてあのスカンク姉妹の顔があった。
気がつくとまたあの悪臭がする。
それが自分の毛皮から立ち上っているニオイだとわかると、マイクはまた気が遠くなった。
どれほどの時間が経っただろうか、体の上にふかふかの何かが被せられた感覚で、マイクは目を覚ました。
彼は柔らかい毛布をかけられ、見知らぬベッドの上に寝かされていた。
ここは一体・・・・・・まだ少しくらくらする頭を振って、考えを整理しようとした矢先、マイクはある強烈な違和感を覚えた。
自分の体の上に覆い被さっているのは、毛布だけではない。
明らかに毛布とは別の、しかし毛布に劣らずふわふわの毛皮をもった柔らかな何かが、マイクの股から腹の上にかけてのしかかるように存在していた。
「マイク、起きたの・・・?」
だしぬけに、毛布の中の暗がりから声がした。
「・・・・メ、メフ・・・!?」
「ぅ・・うん。わたし、マイクとね、もう一度お話がしたいと思っててね、それでね・・」
毛布の奥から聴こえてくるメフのくぐもった声がそう言うと、それまでマイクの腹部を柔らかに圧迫していた大きな塊がもぞもぞと動き出し、毛布を押しのけて、姿をあらわした。
マイクにとっては見覚えのある、それどころかもう一生忘れられそうもないその光景・・・・毛布の下からあらわれたそれは、彼の視界を覆い尽くさんばかりに巨大な、メフの尻だった。
マイクを狂乱させ、失神に追いやったあのものすごい悪臭の噴射口が今再び、彼の胸の上でエロティックな収縮を繰り返していた。
あの時の、息もできない苦しさが瞬間的に脳裏によみがえり、マイクはほとんど反射的に、目の前の尻を押しのけようと、まだ力の入らない体で弱々しくもがいた。
「メ、メフ・・やっ・・やめ・・・やめて・・!」
その間もマイクは、一つは恐怖のためと、それとは異なるもう一つの衝動のため、鼻先に迫ったスカンクの肛門から目をそらすことができないでいた。
毛布の奥からまた、メフの声がした。
「マイクあのね、あの後わたしずっと、すごく反省してたの。ちょっとだけ泣いちゃった。あんなにもひどい残酷なこと、もう二度としないって思って」
「・・・・そ・・そうか、だ、だったら・・!」
「でもね、マイクあなたが・・・ああいうのが、好きだっていうなら・・・・。わたしがどんなにほっとして・・・・、ううん、・・・どんなに嬉しかったか、わかる?」
「・・・え、な、な・・・・・」
「わたしたちのこんなにくさいニオイで、興奮するの?イッちゃうの?転げ回って悶絶しちゃうほどひどいことされたのに、それでも良かったの・・・?」
マイクは、頬がカッと熱くなるのを感じた。
あの時のえも言われぬ興奮、天にも昇るような射精の快感・・・!
「あ・・・い、いや」
「また・・同じことされてみたいって、思う・・?」
「そ、その、違う・・ぼくは、ただ、学術的な・・好奇心・・・」
「マイク・・・でも、ほら、もうここ、こんなに・・・」
毛布の奥で、ひそかに膨張していたマイクの一物に、メフの指がそっと触れた。
「ぁ・・・っ」
突然の”襲撃”に衝撃を受けたマイクの喉から、思わず上ずった声が漏れた。
マイクの目と鼻の先に、彼を発狂させ半殺しの目に遭わせたメフの恐るべき肛門がある。
体は押さえこまれて身動きがとれないが、それでも全力で暴れればどうにかなったかも知れない。
しかし、マイクはそうしなかった。
抵抗を試みることすらも無く、彼の体は、ベッドに縫い付けられでもしたかのように微動だにしないままだった。
「マイク」
毛布の奥で、少しトーンを落としたメフの声がした。
「やっぱり、嫌・・・・・・かな?」
「・・・・・」
だしぬけにそんなことを訊かれ、咄嗟に返答につまってしまったマイクが目を白黒させていると、目の前のピンク色をした肛門が、じりっ、とさらにマイクの鼻先に詰め寄ってきた。
メフの哀願するような声がそれに続いた。
「・・それとも・・・・してほしい・・・?はぁっ・・、はぁっ・・、・・・してほしいなら・・・・・う、ううん、・・・・・しても、・・・・いい・・・・・?」
「・・・・・」
「・・・してあげたいの。・・・ぅ、ううん、したいのっ・・!だってわたしね、あの時、本当はすごくっ・・・!あんなの、あんなにまでなっちゃったの、は、初めてで・・!!すごく・・、すっごく、良かっ・・・・」
おもむろにマイクの唇が、メフのそのデリケートな菊座に、そっと触れた。
ぴくっと、メフの尻が震えた。
マイクの舌が、花のつぼみのような肉皺をゆるりゆるりとなぞるごとに、くぐもった喜悦の悲鳴が毛布の奥から聞こえてきた。
マイクの舌の動きはますます速く、大胆になっていった。
いつしかマイクは目の前の尻をわし掴みにし、激しい舌の攻撃をメフに加えはじめていた。
メフは、身をよじるようにして尻を振りたて、悲鳴に近い声で叫んだ。
「ぃっ、ぃいのっ?ほんとにいいのっ?マイクぅぅ!」
マイクは、熱に浮かされたようにふらふらと、鼻先をスカンクの危険な砲門に自ら擦りつけた。
メフはすばやく両脚でマイクの頭部を挟みつけ、両足首を彼の頭の後ろに回して組み合わせると、そのまま抱え込むようにしてぎゅうううっと締め付けた。
マイクの頭は太腿の間に埋まり、顔は半ば尻の肉にめり込み、その鼻先は、先ほどマイクが自ら擦りつけていた肛門に押し付けられ固定されて、もはやぴくりとも動かせなくなった。
メフは両脚にさらに力を入れ、マイクの顔を完全に腿と尻の柔肉で密封するようにがっちりと封じ込めてしまった。
「ペロペロいやらしいことしちゃうような悪いお口はぁ・・こうしてふさがれちゃうの・・ね?」
毛布の奥から、ハァハァと一段と熱っぽくなった吐息に混じって、嘲るような調子の、それでいて妙に色っぽい、メフのくすくす笑いが聴こえた。
マイクは窒息しかけながらも、さらに鼻息を荒くして、力の限りを振り絞って、ぬろぬろと舌を使い続けた。
毛布の奥で小さく、「・・ィクっ、好きぃぃ・・!」という声が聴こえた・・気がした。
「ぁぁあはあぁあああぁっ!!」
メフの一際大きな悲鳴が上がったかと思うと、マイクの顔とそれが埋まったメフの尻や太腿との隙間のあちこちから、猛烈な臭気が漏れ出し、辺りに漂い始めた。
「ンギャヒーーーーーーー!!」
マイクもまた絶叫しながら、拘束のゆるんだメフの両腿の間から頭を力任せに引き抜くと、狂ったように顔を左右に振り立てた。
が、その顔面そのものから次々と気化し、ふんぷんと漂い続ける糞臭じみた濃密な香気は、煙のように鼻先へまとわりつき、どんなに頭を振ったところで決して逃れることはできなかった。
「メフ、メフッめふっ、ごぼげぼ、ぐざハヒハヒ、ハヒ・・ハ・・・ヒ・・・・・・・ヒィ」
鼻水と涎にまみれ、白目をむいて半狂乱になったマイクは、無理に起き上がろうとした挙句、メフの柔らかな尻へ顔面をしたたかに打ちつけ、勢い余って鼻を肛門に突っ込ませた後、全身を激しく震わせ、崩れ落ちるように失神した。
「あらあら・・・そんなによかったの。うふふふっ、何て変態なキツネさん。でも安心して。このことはないしょ。秘密なの。わたしたちきっと、うまくやっていけるよね?」
メフは、指にまとわりついていた生温かい残滓を、愛おしげに舌で舐め取った。
それは、マイクが気を失う数秒前、メフの掌に包まれていた彼の一物から、怒涛の勢いで噴出したものだった。
「よかったね、お姉ちゃん。それにきっと、マイクも」
ドアの外で鼻をつまんでいたスピルはくすっと小さく独笑し、つぶやいた。
「これで、いいのだ」
THE END