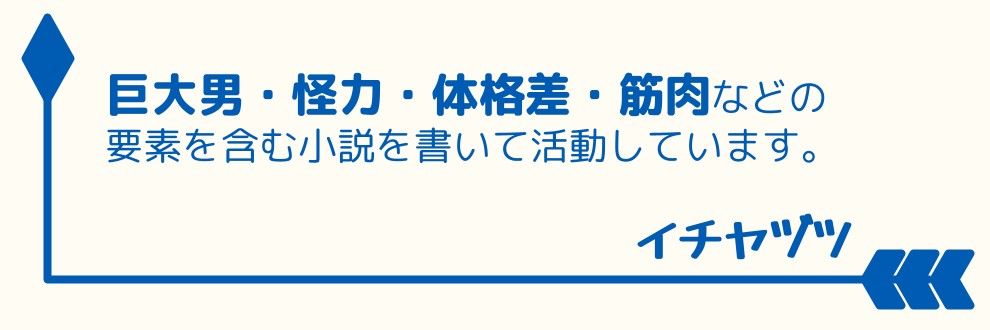1.そうして世界は終わらなかった
もうすぐこの世界は終わるのだろう。
よく晴れた空。適度な白い雲。火薬のにおいが風に乗って流れてくる。絶え間なく聞こえる人々の悲鳴、爆発音と砲撃。そしてそれらをすべてかき消すほどの地鳴り。
(いや、足音、か)
尚樹は自宅の屋上からそれを見上げた。まだまだ遠くにいるはずだけれど、その姿はしっかりと視認できる。巨人だ。近くにあるマンションは十階分ぐらいの高さはあるはずなのに、その巨人の腰よりも低い。ズゴォン、ズゴォンと大地を揺らしながら巨人が歩く。世界は、この巨人によって終わろうとしていた。
突如ハワイ沖に現れハワイを地獄に落とし入れた後、海を越えアメリカを崩壊させ、ヨーロッパとロシアとインドを火の海に変え、ヒマラヤを崩し越えて中国が壊滅。核を含む人類のあらゆる抵抗をまるでゴミのように吹き飛ばし、数十メートルから数千メートルまで大きさを自在に変えて世界を蹂躙する巨人。南半球はまだ無事な国が多いが、それも時間の問題だろう。日本をつぶしたらすぐ、のはずだ。
そんなことをぼうっとかんがえていたら、ずどおおおおおおおおん!!!と、今までで一番大きい爆音が響いた。揺れる地面とともに身体が飛び上がる。次いで爆風が襲ってきてこらえる暇もなく物干し台や鉢植えとともに屋上に転がった。
「………………でっか……」
何とか起き上がって見上げたのは、家の前で仁王立ちをしている巨人、の脚だった。さっきの爆音は、多分斜め向かいの家を踏みつぶして、大地を揺らしたときの音だろう。家を踏みつぶして余りある足が道路にまではみ出している。目の高さにあるのは脛だ。二階建ての家の屋上にいるのに。そのまま顔を上げると、逞しい太腿……と、その間に重々しくぶら下がるめちゃくちゃでっかい男の象徴が視界に入る。車やバスより断然でかい。長さだけで多分普通の家の高さぐらいはある。
(………………)
もっともっと上を向けば、幾多もの砲弾やミサイルでも傷一つつかなかったぼこぼこに盛り上がった腹筋が、そしてその腹筋に影を作るほどせり出している胸板がそびえている。まるで、覆いかぶさるように。
「どんだけでっかいんだよ…………」
もう見上げる首が痛くて、あきらめて地面に寝転がった。家の幅よりある広い肩、太い首の上に、たった一カ月で北半球をほぼ壊滅に追いやった巨人の顔が乗っていた。これがまた精悍で男前な顔で、充分人間のモデルとしても通用するぐらいのイケメン。こちらを覗き込むように背中を曲げていたその男のでっかい眼が俺を見つめていた。特に笑っているでも蔑んでいるのでもなく、じっとこちらを見つめている。
(これでおわりだな)
いつの間にか砲撃の音はしなくなっていた。全滅したか弾薬が尽きたか。ちなみに避難はぜんぜん間に合ってないので、俺がいるからって理由はないと思う。
「………………いまいくよ」
巨人の、家どころかビルさえしのぐ大きな脚が持ち上がり、そして。
***
「…………ゆめか……」
枕元で鳴り響くスマホのアラームで、目を覚ました。薄暗い部屋の中、手探りでスマホを探してアラームを止め、ゆっくりと息を吐く。
「あっつい……」
寝ている間に汗をかいたのか、体中がべとべとしている。着ているTシャツとハーパンも心なしか湿っている。掛け布団を蹴飛ばしたが、こもった熱気はいつまでも散らない。
(いやまて、あつすぎ)
もう暦の上では秋だったはずだ。真夏ならまだしも、最高気温が三十度を超えないこの時期に部屋がこんなに暑いはずがない。
(ていうかまだ夜? 外が暗……ああ)
部屋が暑い原因と外が暗い原因に同時に、というより原因が同じものだと思い当たり、大きくため息をついた。一度目をつぶり、ゆっくりとベッドから起き上がる。窓に近づき、カーテンを勢いよく開けた。ガラス越しに見えたのは夜空でも青空でもなく、ぼこぼことした肌色の壁。少し下には黒いジャングルとふてぶてしく鎮座している車なんかよりずっとでかい、それだけで一軒家ぐらい潰せるだろう肉の棒。
「ったくもう……」
鍵を開け窓を開ける。むわっとした熱気と独特の匂いが外から舞い込んでくる。部屋が暑かったのはこのせいだ。窓から身を乗り出して上を見上げる。
「おはよう! 尚樹!」
はるか上から家が震えるほどの大きな声が響き落ちる。起き抜けからこの大音量は頭に痛い。
「シン!おまえなー!」
家の屋上よりずっとずっと高いところにある顔に届かせるため、精一杯声を張り上げる。
「ウチを股に入れて座るのやめろっていってんだろ!!」
光を遮り、夏のような熱気を放っていたのは予想通り目の前にあるこの巨人の体だった。座っているのに家よりでかいサイズのこの巨人は、まるであぐらをかくようにすっぽりと俺の家を脚で囲んでしまっているのだ。暑いし揺れるし、その筋肉がぼこぼことついた太腿がちょっとでも触れれば家がぶっこわれるとさんざん言っているのに、この巨人……シンはなかなかこれを止めようとしない。ぐぐっとシンがかがむと、目の前の身体が地鳴りとともに迫ってくる。影が濃くなり、シンの顔が少し近づく。
「まあいいじゃんか。いい天気だぜ!」
「お前のせいで天気もわかんねーんだよ……」
そう、あの時世界は終わらなかった。なぜだか俺が、この巨人、シンに気に入られてしまったせいで。
2.二人だけの登校風景
「……とりあえず、俺シャワー浴びるから、その間に小さくなっておけよ!」
上からのぞき込むシンの顔に叫んで、窓を閉める。外でシンが「なんでだよ~」とかでかい声で言っているが知るもんか。替えの服をひっつかんで階下に降りる。汗で湿った服をまとめて脱ぎ捨て浴室に入ってドアを閉めた。
「はーーー…………」
朝から疲れる。鏡に映る自分を見る。シンとは比べ物にならないぐらい貧相な体だ。これでもサッカーをやっていたからそれなりにましなはずなのだが。
(まあ比べる対象が悪いか)
蛇口を捻りお湯が出るのを確認してからシャワーで汗を流す。湯がべたつきを洗い流すと少し頭も冴えてきた。シャワーを止めて身体を拭きながら今日の予定を頭の中でさらう。
(体育……はない……数学の宿題……もやった……昼は購買で買って……ああそうだ。政府の人と会う約束があるんだった……)
着替えてから軽く朝食を食べ、昨日のうちに用意しておいた鞄を持って玄関で靴を履く。起きてから大体四十分。扉を開けて外に出る。
「やっときたな! 尚樹!」
家の前には、学ランに着替えたシンが小さくなってこっちに手を振っていた。小さくなったとはいっても、余裕で二メートルは超えているでかさだ。特注させているはずの学ランが今にも破れそうで、太い腕に引っ張られて持ち上がる黒い生地が多分悲鳴を上げている。鍵をかけてからシンの元へと近寄る。ちょうど目線のあたりが学ランの布地を大きく膨らませている大胸筋の真ん中あたりで、シンの顔を見るにはかなり見上げなければならない。
「お前もうちょっとちっちゃくなれないの?」
「こんぐらいがいーんだよ」
シンが俺の頭にでかい手をおいてぐしゃぐしゃとなでる。本人はじゃれているつもりなんだろうが、俺にとってはたまったもんじゃない。シンはこのサイズでも腕一本で戦車を空の彼方まで投げ飛ばせるし、足踏み一つで地下街を崩壊させることができる。俺の頭を握りつぶしたり首をぽきりと折ることなんて、息をするより簡単にできるだろう。
「やーめーろ」
俺がシンの手を払おうとすると、(俺の力じゃむりやりどかすことなんてできないのだが)シンは頭をなでる手を離す。その顔がまたにやにや笑っているもんだから腹が立つ。
「……学校行くんだろ。行くぞ」
「おう!」
俺が歩き出すとシンも横に並んでゆっくりと歩く。俺とシンじゃ歩幅が全然違う。俺の胸の下あたりにベルトがあるのだから脚の長さは歴然だ。それでもって俺の歩く速度に合わせてゆっくりと歩いているのだ。
「なーやっぱ俺がでかくなって尚樹乗せて運んだほうがはやくね?」
「別にお前は一緒に学校行かなくてもいいんだぞ」
そもそも世界を壊滅させかけた巨人が、日本の学校に通っていることがおかしいのだが、この巨人がそうしたいといえば世界は逆らえない。まあ俺が学校に通い続けたいと言ったのもあると思うけれど。
「俺は尚樹といっしょにいてーの!」
「じゃあいいだろ。通学だって学校の一部だ」
政府から専用車を出すっていう提案もあったけれど、そんな非日常は絶対嫌だったので断った。だから俺を好きらしいこの巨人は、俺の望みどおりに電車での通学についてくるのだ。
「壊すなよ」
「壊さねーって」
既に三回ほどぶっ壊しているから言っている。自動改札もシンにとっては跨げるぐらいに小さい。だからか、どうもICカードのタッチと歩くタイミングが合わないらしい。最近は駅員さんの遠隔操作の努力もあり上手く通れるようにはなったが。
「お、電車くる」
アナウンスと共に電車がゆっくりとホームに入ってくる。乗るのは真ん中付近の四両目だ。滑らかに電車が止まり、ドアが開く。ひょい、と乗る俺に比べてドアが肩までの高さしかないシンは逆手にドアの上枠を掴み、ぐぐっと大きく体を曲げて車内に侵入する。シンの体重で電車が揺れる。つり革や広告がほとんどなくても、シンが身体を起こせば頭は天井に付き、下手するとそのままぶち抜く。だからシンは身体を屈めたまま既に座っている俺の横に腰を下ろした。椅子のクッションがぎぎっと軋み、なんとかシンの体重を支える。脚は大きく開いているが、問題ない。この車両、いや、この電車には他に誰も乗っていないのだから。
(まあ、世界を破壊した巨人と同じ電車には乗りたくないよな……)
別に巨人専用というわけではないが、皆あえてこの時間の電車を避けているのだ。だからいつも通学時はシンと二人きりである。朝はニュースを見る時間がなかったので、この時間を利用してスマホでニュースをチェックする。ニュースサイトを開いていると横からシンが覆いかぶさるように覗き込んでくる。
「何見てんだ?」
「ニュース。……知らないかもしれないけど、まだまだ世界大混乱中だからな?」
シンの大破壊から一カ月。北半球はもちろんだが、直接シンの被害のないところでもテロや紛争が勃発していた。
「ああほら、中東がまた軍事衝突……」
中東あたりはシンの被害を免れた地域だが、もともと軋轢が多かった場所だ。世界のパワーバランスが崩れたおかげでもう火薬庫に火を入れたかのように紛争中である。他にもヨーロッパのテロやアメリカの復興の記事が並ぶ。
「はやく平和になればいいんだけどな」
「でも尚樹にはかんけーねーだろ?」
「関係なくても。ていうかお前のせいだからな!?」
興味のなさそうな顔をしているシンに突っ込むが、全く堪えていない。そうしているうちに学校の最寄り駅に着き二人で電車を降りる。窮屈だったのか、ホームにこれまた特注のローファーを下ろしたシンは、今にも内側から破れそうな学ランでぐぐっと伸びをした。
「あっ……」
気づいたときには遅く、伸ばしたシンの腕が普通の人間なら届きもしない電光掲示板の中程に当たる。それなりにしっかり固定されてるだろうに、シンのたくましい腕は容赦なく電光掲示板を吹っ飛ばす。
「ん?」
シンも気づいたようだが、コードやらなんやらがちぎれた電光掲示板はけたたましい音をたててホームに転がった。そのままその鉄の塊は勢い良く滑り階段に当たって止まる。画面は割れ、中程から大きくひん曲がっている。
「あー、やっちゃった」
「あんなとこにある方が悪いよな」
シンは落ちていた空き缶を蹴ってしまった、ぐらいの軽さだ。あれだって安くないだろうに。
「それより尚樹、早くいこうぜ」
「……うん。あ、でもあれ邪魔だな」
まあ良くあることなので早々にあきらめて改札に向かおうとしたが、先程の電光掲示板が階段を塞いでいる。周りにも割れたパネルやらなんやらが飛び散っているし、下手に歩けば怪我をしそうだ。
「向こうの階段から……」
「なんだよ、こーすりゃいいだろ」
そういうとシンは俺の両脇に手を入れるとひょい、と持ち上げた。
「うわっ!」
「俺が運んでやるよ」
俺も一応六十キロはあるのだが、シンにとっては空気も同然だ。尻に左手を添えられ、流されるままにシンのぶっとい首に腕を巻き付けると体が安定する。
「一言いえよ」
「ははっ、わるいわるい」
シンの頭越しに後ろが見えるが、とんでもない高さだ。ホームにある自販機の上に埃がたまっているのが見える。シンが歩き出すと体がゆらゆらと大きく揺れる。階段に近づくと、シンは壊れた電光掲示板を構わずに踏みつける。メキャメキャバリバリと凄まじい音がして、丈夫なはずの電光掲示板がまっぷたつになる。
「……すげー」
「へへっ、こんなのなんでもねーよ」
そのままシンは電光掲示板を踏み越えると、身体をかがめながら足の長さの半分もない階段を上って改札までたどり着く。俺を下ろすと、シンは改札横でひたすら目立たぬようにたっていた駅員の元へ向かう。
「ひっ……」
何度も言うがシンはこのサイズでも十分でかい。シンが背中を丸めても、駅員の帽子はその肩にも届かない。むしろ上から覗きこまれて恐怖なだけだろう。俺の目線からはシンの背中に全て隠れてしまって駅員の姿すら見えない。
「わりいな、ホームの掲示板壊しちまった」
シンの低い声が抑揚薄く駅員に降りかかる。重ねるがシンは世界を壊しかけた巨人だ。拳銃を突きつけられるよりも確実で強大な「死」を目の前にして、駅員は、なんとか声を振り絞る。
「だだだだい……じょうぶ、です!!」
「そうか、ありがとな。……尚樹ー、いこうぜ!」
許されることが確定していた謝罪が終わると、シンがこちらを振り向いた。屈託のない笑顔と明るい声。さっきまで駅員に向けていたものとはまるきり違う。
「はいはい、いくぞ。改札は壊すなよ」
「わかってるって!」
シンと一緒に改札を抜け、駅を出て学校へと歩を進める。なんのことはない、普通の登校風景だ。
3.大事なものは一つだけ
予鈴までまだまだ時間があるから余裕をもって学校にたどり着く。校門を抜けて昇降口に入ると、途端にシンの大きさが際立つ。天井は高いが、周りのあらゆるものが人間向けの高さにできているからだ。
「スノコ踏むなよ」
「わーってるって」
いわゆる土間から一段あがる框の前には青いプラスチック製のスノコが並べられている。生徒はそこで靴を脱いだり履いたりするのだが、シンが乗ってしまえばたちまちスノコは割れてしまう。かつて並んでいた四つのスノコのうちひとつは取り払われ、そこでシンは右の爪先で左のローファーの踵を押さえてまずは左足の靴を脱ぎ、左足で框に上がりもう片方も器用に脚を振って脱いだ。
五段仕様の下駄箱の向こうを俺は見通すことはできないが、シンにとっては肩にも及ばない低さだ。シンはしゃがんでローファーを持ち上げると、下駄箱の一番上に乱雑においた。三十七センチという巨大な靴は当然下駄箱になんか入らない。隣に置いてある白のスニーカーは上履き用で、ローファー共々特注品だ。
靴を履き替えたら教室まで歩く。二年の、というより俺とシンのクラスの教室は一階にあるのですぐそこだ。教室のドアは、天井までの高さがある特注品だ。シンが三回ほどぶち壊してから、ドア自体が変わった。
「おはよー」
ドアを開けると、既にほとんどのクラスメイトが教室に来ていた。おはよう、と、教室内にいた二十人弱のクラスメイト全員が返す。
「尚くん、おはよう! シン様! おはようございます!」
「おはよう」
「おう」
その中で近づいて挨拶をしに来たのが、友達の裕一だ。シンをめちゃくちゃ崇拝していて、毎回こうやってシンに挨拶をしに来る。身長は俺より大分小さくて、でかいシンと並べばちょうどシンの肘が顔に当たるぐらいの差がある。
「お前も毎回元気だな」
シンがポン、と裕一の頭に常人の二倍はありそうな手を置く。教室の空気が一瞬でピリッと張り詰めた。シンならそのまま裕一の首をねじ切ることも、頭蓋骨ごと頭を握りつぶすことも、食い終わったハンバーガーの包み紙をぐしゃぐしゃと丸めるぐらい簡単に出来るのだ。だがシンはねじ切ることも潰すこともせず、裕一の頭から手を上げた。裕一はシンの手が触れた頭を両手で触り、恍惚の表情を浮かべている。
「シン様に……触れられた……」
自分の世界に入った裕一を置いておいて自分の席に向かう。一番窓側の後ろから二番目が俺の席、その後ろがシンの席だ。シンの机と椅子はこれまた特注で、俺の奴より二回りもでかい。以前椅子に座らせてもらったら脚はぶらぶらと揺れるし背もたれにもとどかないような大きさだったが、それでもシンが座ると金属でできた椅子はギシギシと悲鳴を上げている。
「……ったく、こんなのによく何時間も座ってられるよなー」
俺だと持て余す机と椅子でも、シンにとっては窮屈なものなのだろう。そもそも学校に来たからといって勉強をするでもなし、大体は後ろから俺を眺めているだけのシンに机もなにも要らないと思うのだが、まあ学ランと同じくどうやら俺と同じことをしてみたいらしい。斜め上からの視線が嫌でもわかる。
そのうち予鈴がなって、クラスメイトたちが席につく。世界を破壊したシンと一緒に授業を受ける不思議な光景。シンがこの街、というか俺の近くで暮らすことが決まったとき、当然のごとく街の人たちは逃げ出した。シンがひっかき回して世界中が動乱に巻き込まれる中、シンという核を超える抑止力のお陰で今日本は世界で一番安全な国だ。だがそれでもわざわざ巨人の近くにいたいと思う人はいないだろう。当然かつてのクラスメイトたちも教師もほぼいなくなり、学校自体がなくなりかけた。
だからいまここにいるのは、大体が政府によって用意された人々だ。孤児だったり金が必要だったり、そういう人々が高校生活を送る代わりに、世界でもっとも安全で危ない場所に配置される。裕一なんかはまた別だが。
「おーし全員いるな、授業始めるぞー」
中年の教師が入ってきて、教卓に資料を置く。授業自体は全くもって普通のものだ。面倒なサインとコサインのグラフが黒板を埋め尽くしていく。数学は嫌いだが、問題が解けたときの達成感は気持ちいい。
(シンもおとなしくしてるな…………)
シンとしては俺の反応もなく暇な時間だろうが、授業の邪魔はするなと言ってある。視線はずっと感じるがまあそのぐらいは仕方ないだろう。
「じゃあ最後にプリント配るぞー。次までの宿題な」
えー、という声がそこかしこから聞こえるが、先生は容赦なく一番前の列の生徒に紙束を配っていく。そうすれば皆もしぶしぶ従うしかない。紙束から自分の分を取って残りを後ろの奴に渡す。俺も前の席の優吾からプリントの束を受け取る。
「っ……」
紙束を受け取った右手の人差し指に小さな痛みが走る。紙で切ったのか、ぷくりと赤い玉が指の腹から現れる。優吾の顔が一瞬でこわばる。
「ごっ、ごめっ」
背中の方から響く轟音が、その謝罪をかき消した。何かが爆発したかのような巨大な音が教室中に鳴り響き、飛び上がりそうになるほど床が揺れる。音の反響が少しおさまってから、その元凶であるだろう後ろを向く。
「シン……」
そこには無残な姿になったシンの机があった。厚み五センチはありそうなこげ茶色の天板が、シンが降り下ろしたでかい拳によって真っ二つに割られている。拳はそれだけでなく、下についていた金属の物入れまで引きちぎってぐしゃぐしゃにし、勢いで机の脚まで曲がってしまっていた。もう修理は無理だろう。木くずや壊れた金属が落ちる音以外は何も聞こえない。教室中の誰もが息をひそめている。シンが腰を上げると、椅子が後ろに倒れて音を立てた。でかいシンが立ち上がるとそれだけで風が起きたように空気が動く。俺の首は上へ上へと向いていき、振り向いた体勢もあって大分きつい。身体ごと後ろを向くと、ちょうど目の前にあったのはシンの股間だった。相変わらずでかいな、と、今の状況にそぐわないことを考えてしまう。
「おい」
上からシンの声が降ってきて見上げると、屈んだシンが人間の顔をそのままつかめそうなでかい手をこちらに向けていた。が、その手は俺の左上を突っ切り、太い腕が俺の視界をかすめる。その時後ろで叫び声が聞こえた。
「ひあっ、ご、ごめんなさいごめっいやああああああ!!!」
振り向く前にシンの腕が動いて、俺の真上を何か大きなものが通った。じたばたと動くそれは、前の席の優吾だった。シンがそのでかい手で前の席の奴の頭を掴み、宙づりにしているのだ。優吾はばたばたともがき、頭を掴むシンの指を掴んで外そうとしているが、人間にシンをどうこうできるわけがない。雄吾越しにシンの顔が見えた。ゴミを見るような冷ややかな目で目の前の優吾を見ている。シンの腕は微動だにせず優吾を持ち上げ続けていて、優吾は頭を握られている痛みに喘ぎながらもそのまま頭蓋骨を砕かれないために泣き叫ぶ。
「ごめんなさい! すいません!! わざとじゃないんです!!!!! お願いです許しぎああああああ!!」
「シン! ストップ!」
下から叫ぶと、のたうつ優吾越しにシンがこちらを見た。まだ冷たい目に一瞬身体がこわばる。
「優吾を離して」
「でもコイツ……」
「いいから。早く降ろして。俺そういうの好きじゃない」
重ねて言うとシンは不服そうな顔をしながらも優吾を持つ腕を右へと動かし、ゆっくりと腕をおろして手を離した。支えを失った優吾は、足は床についたものの腰が抜けているのかその場に崩れ落ち、眼から鼻から液体を流してのたうっている。
「優吾だいじょう……」
「尚樹大丈夫か!」
優吾に駆け寄ろうとする前に、シンが俺に覆いかぶさって右腕をつかんだ。俺のはちょっとした切り傷だし、絶対優吾の方が重傷だし、なんなら今掴まれてる腕の方が痛い。が、シンは本気で俺の傷を心配している。
「……大丈夫だから、放して。こんなの舐めときゃ治るよ」
「そんなわけあるか! 保健室行くぞ!」
そんなわけあるんだけど、という俺の想いとは裏腹にシンは俺の腰を掴んでひょい、と持ち上げてしまい、俺はそのままお姫様抱っこの体勢に移行させられてしまう。いや、シンとの体格差からすると、赤子みたいに抱かれているようなものか。
「ちょ、シン!」
シンは有無を言わさず三十七センチの白いスニーカーを踏み出したが、その先には転がっている優吾がいる。シンの体重で踏みつけられればただでは済まないが、シンの脚はなんてことないように優吾をまたいだ。教室の出口へ向かうシンのために教室の後ろの席の奴らが飛びのいて逃げる。ドアまで来るとシンは右足を上げてドアに蹴りを入れた。シンに合わせて二メートルを越すサイズで作られた木製のドアは、すさまじい音を立ててあっけなく真っ二つになり床に倒れる。シンがそのドアを踏みつけながら廊下に出た。
(もう何言っても無駄だな……)
シンに抱えられたまま、諦めて小さくため息をついた。
***
大学病院並みの設備の保健室で、世界有数の名医である保険医の先生に絆創膏を貼ってもらって切り傷の治療は終了した。心配するシンを説得しながら教室に戻ると、真っ二つになったはずのドアは元通りになっていた。教室に入ると、シンがぶっ壊した机はきれいに片づけられており、まったく同じ机が代わりに置かれていた。前の席の優吾の姿はなく、おそらく病院に向かったのだろう。自分の席に座って、後ろを振り向く。
「……大人しくしてろよ」
ギシ、と椅子をきしませながら座るシンは、俺の言葉には答えなかった。
授業が終わっても、まだシンの機嫌は直らなかった。立ったり座ったりの動作がいちいち荒く、備品や校舎が壊れようがかまうものかと言っているようだ。昇降口でローファーに履き替えて外に出ると、学校の前に黒いセダンタイプの高級車が停まっていた。
(あ……)
そういえば政府の人が話したいといっていたのを忘れていた。ちらりとシンの方を見上げてみるが、虫の居所が良くなさそうだ。
(今日はやめとこう)
シンは政府関係者が嫌いなので、下手すると政府の人が車ごと消える。スマホを取り出して政府の人に連絡しようとするが、その前にシンが車に気づいた。
「チッ……」
俺のはるか上で舌打ちしたシンが歩幅を大きくして車に向かう。二メートルを軽く超えているシンの本来の歩幅は相当なもので、俺も慌てて追いかけるけれども歩いているシンに対して小走りだ。手首すら太すぎて握れないので服を引っ張ってみるも、シンが歩みを止める気配はない。
「ねえ、シン」
声をかけてみるも歩く速度は緩まない。じゃあしょうがない、と俺は掴んでいたシンの袖を放した。
「……俺、人殺すやつ嫌いだからな」
届いたかどうかは知らないがそれだけ言ってシンの後ろ姿を見つめる。車と比べてもシンはやっぱりでかい。後部座席のドアの前に立ったシンの、腰あたりに車の屋根がある。車の中の人からはシンの脚や股間しか見えないだろう。政府の人もやばいと感じたのかエンジンをふかして逃げようとするが、その前にシンが車の、窓と屋根の境目に右手を伸ばした。親指は何の抵抗もなくガラスを割り、残りの四本は金属の屋根をぐしゃりと突き破った。そのままシンはフレームを掴んで腕を押し上げる。するといとも簡単に車が斜めに持ち上がり、車が接地しているのは右半分だけになった。運転手がアクセルをふかしているのか、左の前のタイヤが勢いよく空転している。接地している右側のタイヤも動いているはずだが、シンの怪力で車が固定されておりまったく進む気配がない。
「おい」
車が斜めになったことで、シンが車の中の人間を見れるようになった。シンにとってはしゃがむより、車の方を持ち上げる方が簡単なのだろう。中から政府の人の叫び声が聞こえる。
「…………さっさと消えろ」
「はははははいっ!! すぐに!!」
シンが手を離すと車が勢いよく地面に落ちて揺れる。その一瞬後、車は急発進したが、フレームが歪んでいるのか、まっすぐ走れず縁石にぶつかる。だがそれでも構わないとばかりに縁石にバンパーをこすり付けながら、車は走り去っていった。後ろからシンに近づくと、シンが振り向いた。腕に当たって吹っ飛ばされないようにのけぞるも、シンがあっという間にその手で俺の腰を掴み持ち上げて抱きしめる。
「うわっ、シン!」
「なー尚樹~……二人で遊ぼうぜ~」
さっき政府の人を脅したとは思えないほど甘えた声。じたばたあがいてみるも、シンにとっては無抵抗に等しいのだろう。丸太のように太い腕に拘束されては全く動ける気がしない。諦めて力を抜き、ため息をつく。
「またかよ……」
「さっきのアレ殺さなかったしさ、な?」
確かに機嫌の悪いシンなら、あのまま車を蹴とばしてビルにめり込ませたり、はたまたフレームを掴んで空に投げ飛ばしたりぐらいはしたかもしれない。それを思えば窓と屋根を割って脅したにとどめたのは良い方かもしれない。
「……ちょっとだけだぞ」
「よっしゃ! じゃあ……あの家で!」
シンが周りを見渡して目を付けたのは一つの一軒家だ。この辺りはまあシンが通う学校の近くということで、わざわざ住む人はほとんどいない。家やビルはほとんどが空き家だ。シンは俺を腕に赤ん坊のように抱きなおし、その大きな歩幅で道路を渡って家の前にたどり着く。シンが俺を地面に下ろして玄関ドアの前に立った。今時の玄関ドアは背の高いものも多く、二メートルを軽く超すシンでも屈まずに中に入れそうだ。が、ドア幅のほとんどを占めそうな広い肩やでかい背中、太い腕を持つシンの前だと、そんな大きなドアでも頼りなく見える。
シンが少しかがんで低い位置にあるプルハンドルに手をかける。そのまま引っ張るが、もちろん鍵のかかったドアは開かない。ガン、とドアがロックにぶつかる音がして、高い音と共にハンドルがドアから外れた。シンの引っ張る力にハンドルの接合部が耐えられなかったのだ。
「ちっ」
シンは手元に残ったハンドルを投げ捨てると、ドアと壁の境目に手を入れた。もちろんシンの太い指が隙間に入るわけはないが、シンのものすごい力が金属のドアをメリメリと歪ませて指を侵入させていく。ドアや蝶番から不気味な音を響かせながらシンが手を入れドアを引っ張ると、鍵の折れる音と共にドアが開いた。開いたドアを見ると、ドアのずいぶん高いところが情けなく歪んでおり、シンの握った跡がはっきりと残っていた。シンが俺の方を振り向く。
「じゃあ、やろうぜ」
4.そのすべてが規格外
シンがドアを大きく開き、身体を斜めにして家の中に入る。その後ろにくっついて俺も中に入った。暗い。靴のまま廊下を歩くシンを横に照明のスイッチを探す。玄関横のスイッチを押すと天井の照明がついた。電気はきちんと来ているようだ。
「お、明るくなった」
明るくなって見えたシンの姿は迫力ものだった。一軒家の平均からすれば決して狭い廊下じゃないだろうに、その幅全てを埋め尽くすほどでかい背中。すれ違うのすら難しいだろう。頭は天井の照明にこすりそうだし、三十七センチのローファーで歩くたびにフローリングがギシギシと悲鳴を上げている。俺も靴のまま廊下にあがりシンについていく。
「んー……こっちリビングか」
玄関のドアは高かったが家の中はそうは行かないようで、リビングに繋がるドアはシンの肩までの高さしかなく、立ったままじゃシンの首から上は完全にドアの上だ。シンならそのまま進むだけで壁ごと簡単にドアをぶち破れるだろうが、そうするとすごく埃が舞って俺が嫌がるのを知っているので、シンはぐっと体をかがめて股間当たりにあるレバーハンドルを指で押し下げた。金属が折れる音がしてドアのレバーが廊下に落ちる。シンが加減をミスってへし折ってしまったのだ。
「ちっ……」
舌打ちしたシンは折れたレバーのあった辺りを手で押した。無理やりとんでもない力で押されたドアがバギバギ音をたてながら開く。シンはそのまま首を下げて身体を斜めにし、リビングへと入っていった。俺は落ちたドアノブやドアの破片を踏まないようにしてそのあとに続く。目に入った照明のスイッチを押すと、部屋が明るくなった。
(……けっこういい家だな……)
リビングとダイニングが繋がった空間は軽く二重帖以上あって、六人掛けのダイニングテーブルや細かい細工の食器棚、リビングには六十インチはありそうなテレビにガラスのローテーブルと、三人は楽にかけられそうな大きなソファがおいてある。皿や小物が床に落ちたりしているのは仕方ないだろう。シンがこの街に来た時の揺れはすごかったし、その時にはもう住人は逃げ出していただろうから。ただそこまで埃っぽくないのが救いだ。
「来いよ、尚樹」
ソファの近くに学ランの上着を脱いだシンが立っている。学ランを脱いでTシャツ姿になったことでシンの持つ筋肉が溢れんばかりにその大きさを主張している。人間サイズのものが周りにたくさんあるのでそのでかさが一層際立つ。俺は小さくため息をついて荷物をその場に置き、シンの目の前に立った。ちょうど目線がシンのみぞおち辺りだ。Tシャツの上からでもわかる大胸筋と腹筋の段差がすさまじくて、まるで別の生き物みたいだ。そのまま顔を上げようとすると、シンが俺の背中に手を回してぐっと俺を引き寄せた。
「わっ……」
こらえようとしたけどシンの力に逆らえるわけもなく、シンの分厚い大胸筋に顔をうずめる形になってしまう。意外に柔らかいそれに顔を包まれ、シンの心臓の音が骨を通して直接耳に伝わる。ドクン、ドクンと巨大な体に血液を送る振動が頭を揺らす。息が辛くなってきて顔をのけぞらせて空気を確保する。かすかにシンの汗のにおいがした。
「シン~……」
「もうちょっとこうさせてくれ……」
上から覗き込むシンがじっと俺を見つめる。どうしてかは知らないけど、シンは俺が好きだ。シンの力なら俺のどんな抵抗も無にして俺を好きにできるはずなのに、シンはそれをしない。本気で止めてほしいといえば止めるし、俺の大事なものには触れないでいてくれる。そんなシンと接していると、やっぱりどうしても甘くなってしまう。
「……なあ、当たってるんだけど」
「それは……しかたねえじゃん?」
でかいシンが俺を抱きしめると身長差から色々触れ合う場所が変わってくる。俺の頭はシンの胸元だし、肩は腹。そして俺のみぞおちから下あたりには、ちょうどシンの股間が位置している。学ランの厚い布地を押しのけるほどのふくらみが俺の腹をぐりぐりと圧迫している。布越しでも伝わる肉の熱さ、そしてまるで第二の心臓かのように、シンのそれが脈打っている。
「……ズボン破っちまうだろ、脱げよ」
「別に破ってもいいだろ」
「俺、下半身裸の奴とは帰らないからな」
そういうとシンは口をとがらせながらも俺に絡ませていた腕を解き、ガチャガチャと荒々しくベルトを外す。そして勢いよくパンツごとズボンを引き下ろした。
「……あいかわらずでかいな」
俺が少し下を向いた先にあるのが、シンの巨大なチンコだ。股からずろんと垂れ下がっているそれは俺の常識からしたら信じられないでかさだ。コーヒー缶のような太さに、それをはるかにしのぐ長さ。俺の手を当てても簡単にはみ出してしまうサイズだ。
「尚樹も脱げよ」
シンがそういいながらTシャツの裾に手をかける。俺も一歩下がるとシンに背を向けて学ランを脱いだ。近くにあったダイニングテーブルに上着やら何やらを雑に乗せ、パンツ一枚の姿になる。準備して振り向くと、シンは仁王立ちになってこちらを見ていた。
「……ほら、尚樹」
手を広げるシンの元にゆっくりと近づく。近づくにつれシンの顔を見るため顔を逸らさなくてはいけなくなる。あと一歩でシンの身体がくっつく、というところで止まる。そうしてしばらくじっとシンの顔を見つめていると、シンが肩を落としてうなだれる。
「……なあ、ここまできたらやってくれてもいいだろ?」
「言ってくれなきゃわからないよ」
そういうとシンはわざとらしくため息をついた。シンの吐息が髪の毛を揺らす。
「……俺のチンコ、触って、勃たせてくれよ」
「……わかった」
シンに一歩近づいて、シンの股間からだらんとぶら下がっているチンコを左手で掬うように持ち上げる。肉が詰まった、ずしりとした感触。長すぎて手のひらの上でも垂れるそれを、右手で根元から先端に向けて優しくなでていく。上からシンの声が降ってくる。
「……いいぜ……尚樹……」
時折揉みながら撫でるのを続けていくと、チンコがむくむくと質量を増してゆく。左手がずしりと重くなるが、しばらくするとチンコが手を離れて浮いていく。ぐぐぐ、と立ち上がっていくそれは、もう股ぐらから腕が生えているようなもので、一・五リットルのペットボトルと比べたって遜色がないだろう。シンの臍を軽々と超えて立ち上がるそれは、身長差もあって俺の顎の真下に亀頭がきている。もしシンが腰を突き出せば、俺はチンコでアッパーカットを食らう、そんな位置。びくびくと重量感たっぷりに揺れるそれはまるで別の生き物のようだ。
「……気持ちよくさせてくれ」
シンの次のお願いを聞いて、俺はもう一度シンのチンコに手を添える。両手がなんとか回るとてつもないサイズ。両手をゆっくり長く動かして、シンのチンコを擦っていく。あっという間に腕が疲れそうになるが、しばらく擦っていると鈴口からどぷどぷと我慢汁が溢れてくる。亀頭から垂れてくるそれを手のひらに伸ばせばローション代わりになって、ストロークのスピードが上がっていく。
「へへ……やっぱいいな……尚樹にやってもらうのは……」
ぐぐっとシンのチンコがまた一回り大きくなる。下を向きながらチンコを擦っていた俺の頬にべちゃりと我慢汁でぬれた亀頭が当たった。のけぞると亀頭は目の位置に来ていて、チンコを握っている手もどんどん上に引きずられていく。シンを見上げて眉を寄せる。
「……シン……」
「ふっ……悪いな……我慢できねえや……」
真上にあるシンの顔がどんどん遠くなっていく。それと共に床がミシミシと鳴り始めた。シンがでかくなっているのだ。視界を埋めながら巨大化していくシンの圧迫感はすさまじく、照明の光を遮ってシンの影が濃くなってゆく。チンコはもう両手でも握れなくなっていて、手が顔の前に来た時に離した。チンコが揺れて、亀頭から溢れる我慢汁がべちゃりと髪の毛を濡らす。もうチンコすら見上げる位置にある。上からゴン、と音がした。
「っ……っとと……」
シンが身体をかがめる。天井が頭にあたるほどでかくなったから直立できないのだ。シンなら天井をぶち破るのも簡単だけど、俺が埃が舞うのを嫌がるからそうしない。シンが背中まで折り曲げるぐらい屈まないといけなくなったところでようやくシンの巨大化が止まった。
「……ちいせえな、尚樹」
「いやシンがでかくなったんでしょ」
見上げる俺の視界のほぼすべてがシンで埋まっていた。身体を折り曲げているシンは顔どころか胸のほとんどまで真上にあって、その影が俺をすっぽり覆いつくしている。腹筋なんかもはるか高いところにあって、身体に沿って目線を下げていって俺の目線にあるのは、シンのチンコの根元だ。シンの脚は筋肉がすごくて太いがモデル並みに長くもあるので、今ならちょっとかがめば俺はシンの股の間を潜れるだろう。臍を超えるチンコだから亀頭はもうはるか頭上にあり、上からまき散らされた我慢汁がぼたぼたと床に落ちる。ぬっと、俺の顔よりでかい手が接近する。
「俺のチンコぐらいまでしかねえな」
「わっ、ちょ、シン……」
頭を手で半分すっぽり包まれながらシンが俺の頭をなでる。シンはあくまで優しくしているのだろうが、体格差がここまでになると流石に動きが大ぶりになる。手が俺の頭をググっとのけぞらせる。
「もうコレも限界だからさ……本気で抜いてくれよ」
身体に合わせてシンのチンコも巨大化していた。もうペットボトルとかそういう次元ではなく、俺の腕より確実に太く長い。びくびくと我慢汁を吐き続けている亀頭はもう手の届く高さになく、目の前にある根元も太すぎて両手でも握れやしない。
「……この体勢じゃ無理だよ」
「へへっ……まあそうだよな」
シンが俺の脇腹を掴んで空気のように俺を持ち上げる。俺を持ち上げる両手は俺の胴体を掴んでまだ余りあるらしく、シンの指と指がくっついている。
(これでちょっとシンが力いれたら、俺真っ二つだろうな……)
シンは俺を持ち上げたまま天井に背中を擦りながら歩きだす。邪魔なローテーブルを軽く蹴飛ばすと、勢いよく吹っ飛んだテーブルは壁に当たって砕け散った。シンはソファの前に移動すると、その小さな座面に腰をおろした。金属と木材がへし折れる音と共にソファがつぶれる。三人が優に座れるソファは背もたれごと一瞬にしてペチャンコになった。
「つぶれちまったな」
シンはまるで気にせず脚を伸ばし、持ち上げたままの俺を自分の股座に近づけ、くるっと半回転させて座らせた。そこはシンの腹とチンコの間。今俺の股の間からは、顎までもありそうなチンコがそびえ立っている。
「でっか……」
下から見上げるのとはまた違う迫力。まっすぐに伸びるそれはもう両手でも握り切れない太さ。太い血管がうねうねと枝分かれしながら張り付き、触るとドクドクと脈打ちながらチンコに血液を送っている。亀頭の部分はピンと張り詰めながら一層太さを増しており、溢れる我慢汁がぬらぬらとチンコ全体をなまめかしく光らせていた。その圧倒的なオーラにごくりと息をのむ。
「じゃあ、頼むぜ」
はるか上からシンの声が降ってくる。俺の脚より太い腕が近づいてきて、指で俺の手をつまむようにしてシンのチンコに触れさせる。既に我慢汁でドロドロだが、手のひら全体に熱が伝わるほど熱い。
「……わかったよ」
手のひらを滑らせるようにしてシンのチンコを擦っていく。これだけでかいとストロークも長大だ。自分の股座の根元から、胸元当たりのカリまでの距離で腕を動かすが、あっという間に腕が疲れてくる。
(……でかすぎなんだよ……)
「うおっ……尚樹……!」
少し前に出て、チンコに抱き着く。そのまま体を揺らして、身体全体で擦るようにしてチンコをしごく。これは大分気持ちよかったのか、シンが喘ぎ声を漏らす。畳みかけるように腕で裏筋を擦り刺激を増やしていく。
「うっ……あああいいぜ……尚樹……もっとやってくれ……!!」
シンは膝に手を置き、上から俺がチンコを刺激しているのを見下ろしている。俺にやらせたいってのもあるんだろうが、もしシンが自分でチンコに触れようものなら巻き込まれた俺は肉塊になってしまう。それは避けたいのでさっさといかせようと思いっきり身体を揺らす。シンの我慢汁でもう俺の身体もべとべとで、履いたままのパンツは完全に濡れて重くなっている。
(……しぶとい……!!)
チンコを抱えなおして亀頭に顔を近づける。どうせもうここまで体中べちょべちょなのだからと、顔の半分もある亀頭に舌を這わせた。それと同時に脚でぎゅっとチンコを絞める。
「あっ、なお、尚樹っ……! イクっ!!」
亀頭が一層膨れ上がるのを舌から感じて俺はとっさに頭をそらした。瞬間、亀頭の先から勢いよく白い奔流が撃ちあがった。ブシュ、とかドプッ、とかいうレベルではない。人が食らえばそのまま貫通しそうな勢いで精液が噴きあがり、天井に着弾して激しい音を立てる。それが連続で二発三発。四発目は目の前の六十インチはありそうなテレビに当たり、その勢いでぐわんぐわんと揺れる。その後も勢いを失うまで十五発程度射精し、リビングのいたるところが白く染まる頃、ようやくシンの射精が止まった。俺の身体はシンの精液で上から下までべとべとだ。
「ふう~……イったな……」
天井に貼りついたシンのゼリーのような精液がぼたぼたと垂れる音が響く。天井は本当にぶち抜いたのか一部が変な形に歪んでいる。まともに顔で受けていたら怪我ではすまなかっただろう。
「こんなに出しやがって……」
「いや、こんなの序の口だって」
確かにその言葉の通り、あれだけの量を出したのにもかかわらず、シンのチンコは全く萎えていないのだ。いまだにびくびくと震え、尿道に残った精液を溢れさせながら、俺の目の前で第二射の準備をしている。顔をそらして上を見上げると、ちょうど見下ろすシンと目があった。その目はらんらんと輝いている。
「このまま二回目やらね?」
「……無理…………」
はしゃぐシンの声にげんなりしながら、俺は目の前のチンコから離れるようにシンの腹へともたれかかった。
***
結局そのあとシンは五回ほど抜いた。俺は一回手伝っただけでダウンしたので、せめて抜くところを見てほしい、とつぶれたソファに座らされ、床に胡坐をかいて筋肉がぎちぎちに詰まった太い腕で自らのチンコを勢いよく扱く。ぐぐっと腕が膨らんでいるところを見ると多分相当な力で握っている。多分、あれが人間だったらあっという間にひき肉になっていた。射精を直接受けたら死ぬのでシンは天井に放ったが、天井の精液が降ってきて精液まみれになること二回。流石に疲れ切って先にギブアップし、俺がシャワーを浴びている間に三回で合計五回だ。浴室から戻ってきたら、リビングはおろかダイニングの半分あたりまでシンの精液で埋まっていた。
「……気が済んだか?」
「んー……まだいけるけど……今はこの辺にしとくかな」
シンがしゅるしゅるとその背を小さくしていき、元の二メートル強ぐらいの大きさへと戻った。シンもシャワーを浴びて精液を落とした後、服を着て家から出るともう外はとっぷり暗くなっていた。疲れてはいたがシンに抱っこされるのも癪なので、気合いを入れて家まで帰る。家の前にたどり着き、俺は玄関ポーチの前で振り返った。後ろについていたシンはその場で止まって俺を見下ろしている。シンが長い腕を伸ばして俺を引き寄せる。勢いあまって俺はシンの胸元にダイブしてしまう。
「わっぷ」
「尚樹、また明日な」
シンが優しく俺を抱きしめる。車すら潰してしまえるパワーの持ち主が、俺を潰さないように、でも触れるとは違う絶妙な強さで俺を包んでいる。俺もシンの腰あたりに手を回す。
「……明日は家囲むのやめろよ。朝熱くて大変だった」
「んー………………わかった。尚樹が言うなら」
そう上から答えが降ってきてシンは腕を解いた。見上げる俺の頭に手が添えられ、屈んだシンの顔が迫ってくる。口づけだけのキスだ。シンはすぐ身体を起こす。
「じゃあな!」
「…………ああ」
俺はすぐ振り返って玄関の鍵を開け、家の中へとなだれ込んだ。鍵をかけてずるずるとその場にへたり込む。顔が、熱い。
「…………なんなんだよ、もう…………」
扉で隔てた向こうでは、シンが尚樹の入った家のドアを見つめていた。しばらくした後、シンは振り返って尚樹の家を離れていく。そうして尚樹の家が見えなくなったころ、シンは立ち止まる。
「……さて」
シンは空を見上げると、ぐっと膝を曲げた。次の瞬間、ドンッ!!という音が周囲に響く。アスファルトは砕け、シンの姿はそこにはない。地面を強く蹴ったシンは、あっという間に地上五十メートル近くまで跳んでいた。
「尚樹が寝ているうちにやっちまうか」
【 プチ 】プラン以上限定
支援額:200円
ハロウィンをテーマにした二人のSSが読めます。巨大化したシンが尚樹にいたずらをする話。(約1800字)
このバックナンバーを購入すると、このプランの2022/08に投稿された限定特典を閲覧できます。
バックナンバーとは?