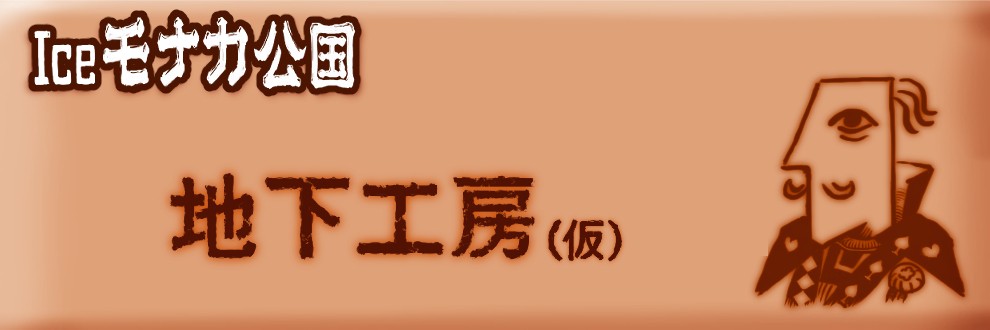動画編集でモザイクと字幕を入れるテスト
前回、エチ動画を作ったはいいが、隠ぺいできず公開不可の話をした。
やむなく元画像を黒塗りして対応、本来ならそのまま…もといモザイクで隠ぺいしたい所だ。
調べると動画編集ツールでモザイク処理するとの事。
エチ界隈では DaVinciResolve(ダヴィンチリゾルブ) を使用との報告複数あり。
矩形や円形、任意の多角形で隠ぺい可能だとか。
しかも無料で有料版から機能制限はほとんど無いとの事。神か?
実は動画編集には使用例も多い廉価な Filmora を考えていた。
だが Filmora は矩形での隠ぺいしか出来ないとの事。
複雑に絡み合う陰部をギリギリを攻めてモザイク化したい要求に、矩形だけでは心もとない。
そのような経緯で DaVinciResolve を試す事に…だがどこまで使えるのか?
そもそも動画編集とは何か?
非力なPCで動作するのか?
動画編集が初めての吾輩の視点で試して行こうと思う。
制作環境
DaVinciResolve 18.6
PC:Surface GO (mem 8GB)
テスト結果
隠ぺい処理のされていない動画を DaVinciResolve でモザイク処理。
またタイトルと字幕のテストも行った。
モザイク処理は自動追尾もできて形状も文句なし、これは使えるな。
初心者には難しいと聞いていたが、処理内容が単純なら問題ないとわかった。
非力なPCでも今回は問題なかったが、長い動画や音声を編集すると問題が出る可能性はある。
以降は制作詳細
DaVinci Resolve 導入
まず気になるのはマシンスペックである。
動画編集には高性能PCが必要だと認識している。
だが DaVinciResolve18 最新推奨マシン環境 を見ると…
・Windows 10
・メモリ 8GB
・Intel内蔵GPU OK
・CPU…かなり不安
HD動画編集の最低限スペックにはギリ足り…ないかな…ふふ
インストール
DaVinciResolve のサイトから最新版をダウンロード。
名前や住所などの入力が求められるが適当で良いらしい。(その辺は別サイトで詳細あり)
zip展開し実行、インストール画面までに結構時間がかかる。
進んでるか不安になるが気長に待つこと。(※非力なマシンの場合)
インストールしたら再起動する。
編集開始
以下のチュートリアルを参考に進めた。
超入門10分でマスターはじめてのDaVinciResolve 18 動画編集初心者向けチュートリアル
プロジェクトの作成
起動後の画面で下段の「新規プロジェクト」からプロジェクト作成。
プロジェクト設定
ファイルメニュー > プロジェクト設定(画面右下の歯車アイコンでも可)
「マスター設定:タイムライン解像度」1280x720 HD 720P
「マスター設定:タイムラインフレームレート」30
「保存」で完了。
作業を進める最低限の知識
作業ページ(エディット、Fusion、カラー、デリバー等)
DaVinciResolve では作業ごとに適したページに切替する。
画面下段にページアイコンが並んでいるので、適宜選択して作業する。
サブウィンドウ?(メディアプール、クリップ、エフェクト、インスペクタ等)
画面上段にページに必要なサブウィンドウ?が並んでいる。
必要になったらウィンドウを開閉して作業する。
タイムライン
エディットページ では、画面下部にタイムラインがある。
タイムラインを作る
「メディアプール」を開く。
「Master」枠の中を右クリック > タイムライン >「新規タイムライン作成」
(もしくは ファイルメニュー > 新規タイムライン)
「新規タイムライン作成ウィンドウ」が出るので「作成」。
素材を取り込む
「メディアプール」を開き、動画や音声ファイルをドラッグドロップ。
(もしくはファイルメニュー > 読み込み > メディア)
動画等のクリップが作成される。
タイムラインに動画クリップを配置
「メディアプール」から動画クリップをドラッグ、タイムラインの「V1トラック」でドロップ。(左端にピタッとつける)
※タイムラインの時間に注意
タイムラインが数時間と巨大になってると、クリップが細い棒になることがある。ズームして適切な時間に変更してから配置する。
タイムラインに音声クリップを配置
「メディアプール」から音声クリップをドラッグして、タイムラインの「A1トラック」にドロップ。
タイムラインを再生
再生ヘッド(オレンジの縦棒)を再生したい位置でクリック。
(※タイムライン上部の時間メモリをクリック)
Spaceキーで再生開始、停止。(画面上部のビューの再生アイコンでも可)
クリップのカット
途中をカット
タイムライン:カミソリアイコン(ブレード編集モード)で、動画クリップを切りたい所でクリックで切れ目が入る。
タイムライン:カーソルアイコン(選択モード)で、選択して DELキーで削除。
右側のクリップをドラッグして左のクリップと連結。
終端をカット
クリップの終端にカーソルをもっていき、カーソルが終端アイコン?になったらドラッグして短くする。(※もう一つ別のアイコンがあるので注意)
タイムラインをクリップとして使える
タイムラインに他のタイムラインをクリップとして配置可能。
(つまりタイムラインの入れ子が可能)
また、Fusionコンポーネント等で「MovieIn」としてもタイムラインが使える。(つまり動画クリップと同じ)
ループする映像クリップを作る
元の動画クリップは1回挿入する尺しかない。当然尺が足りない。
それをトラック上に複数配置しても良いが、必要な尺に合わせてループするクリップを作る。
Fusionコンポジションを追加
エディットページ
「エフェクト」を選択し、
ツールボックス:エフェクト > 「Fusionコンポジション」を
ドラッグして「V1トラック」にドロップで追加。
Fusionページ
「クリップ」を開き「Fusionコンポジション」のクリップ選択。
「メディアプール」から動画クリップをドラッグして、画面左下のノードウィンドウにドロップするとノード「MediaIn1」ができる。
「MediaIn1」の出力(右の■)をドラッグして「MediaOut1」の入力(左の三角)にドロップして接続する。
「インスペクタ」を開き、「MediaIn1」を選択。
「インスペクタ」で「MediaIn1」のイメージの項目「ループ」を有効にする。
これで現在のFusionコンポーネントの長さだけループ再生される。
Fusionコンポジションの長さ変更
エディットページ
Fusionコンポジションの終端をつかんで長さを修正。
Fusionページ
「MediaIn1」のインスペクタで「全体のインアウト」を修正すればOK。
クリップの境目をクロスディゾルブ
エディットページ
「エフェクト」を開き、
ツールボックス:ビデオトランジション > 「ディゾルブ:クロスディゾルブ」をドラッグして、クリップの境目あたり(カーソルアイコンが変わる)にドロップ。
フェードを入れる
エディットページ
タイムラインのクリップ上にマウスを持っていくと、クリップ上に白点が現れる。
これを操作するとクリップをフェードさせられる。
複合クリップの活用
タイムライン上でクリップをまとめたい時がある。
タイムライン上で纏めたいクリップを選択して右クリック > 新規複合クリップ
これでこの複合クリップに編集を加えると、中の全クリップに反映される。
複合クリップをタイムラインに展開
複合クリップの中のクリップを個別に編集したい場合は、
複合クリップを右クリック > タイムラインで開く
元のタイムラインに戻りたい場合は下段に表示されている。
「タイムライン名 > 複合クリップ名」のタイムライン名をダブルクリックで戻る。
テキスト
テキストのフォントはデフォルト「Open Sans」が使われる。
これだと日本語が出ないのでフリーの日本語をインストールして使う。
私は Google Fonts の Noto Sans JP を使った。
タイトルテロップを入れる
エディットページ
「エフェクト」を開き、
ツールボックス:タイトル > 「Fusionタイトル:FadeOn」をドラッグ。
タイムラインの「V1トラック」の上位にドロップする。
(※トラックの上位が表示手前にくる)
「FadeOn」クリップを選択して「インスペクタ」を開く。
ビデオ > タイトル > コントロール でテキストを編集できる。
映画のような字幕を入れる
エディットページ
「エフェクト」を開き、左枠のツールボックス:タイトル >「字幕」。
もしくはタイムライン左で「字幕トラック追加」で字幕トラックができる。
字幕トラック上で右クリック >「字幕追加」で再生ヘッドに字幕が追加される。
字幕は特殊で、インスペクタで全ての字幕を一元管理できる。
また「インスペクタ」の「トラック」で字幕のデザインを決める。
これは全ての字幕に適用される。
- ストローク
文字の縁取りができる。
黒色にしてサイズを付け、外側のみにチェックを入れると良い感じ。 - 変形
字幕の位置、不透明度。 - ドロップシャドウ(使えない?)
文字に影が付かなかった。 - 背景
文字の背後に矩形の枠を表示する。
設定値をデフォルトに戻したい場合、値の右の戻すアイコンを押す。
テキスト+
「テキスト+」はテキスト表示に色々な装飾を施せる。
エディットページ
「エフェクト」を開き、
ツールボックス:タイトル > 「タイトル:テキスト+」をドラッグ、
タイムラインにドロップする。
モザイクの掛け方
カラーページ で作業を行う。
モザイクノードの作成
「クリップ」を開き、モザイクをかけたいクリップを選択。
右上ノード枠の「ノード01」を選択し右クリック > ノード追加 > シリアルノード追加。
「エフェクト」を開き、ライブラリ > ResolveFXブラー:ブラー(モザイク)をドラッグし「ノード02」にドロップする。
これで「ノード02」に「FX」と付き、プレビュー全体にモザイクが掛かる。
(「エフェクト」選択、「設定」で色々調整できる)
ウィンドウで範囲制限
「ノード02」を選択して、画面中央帯の「ウィンドウ」を選択。
右下に形状一覧が出るので形状を選択。
(※アイコン部分をクリックしないとプレビューに形状が表示されない)
- 円
形状一覧で「円」を選択。
プレビューに形状が出るので位置やサイズを調整する。 - 多角形(ペン型)
形状一覧で「ペン」を選択。
クリックで多角形を形成し開始点をクリックすると閉じて形成完了。
プレビューに形状が出るので位置やサイズを調整する。
トラッキング(自動追尾)
「ノード02」を選択。
追尾対象が上記ウィンドウ内に納まっているのを確認、画面中央帯の「トラッカー」を選択。
左下のトラッカーウィンドウで「〇方向にトラッキング」を押すとトラッキングが開始され…ってクリップが無いとエラーが出るな。
※トラックに映像クリップが直接設定されているとエラーが出ない。
※トラックにFusionコンポジションで出力しているとクリップが無いと言われるようだ。
トラッカーウィンドウでキーを打つ
トラッカーウィンドウで「クリップでなくフレーム」を選択。
キーを打ちたいフレームに「再生カーソル?」を移し<◆>クリックでキーが打てる。
部分的に自動トラッキングを掛け直す事も可能
例えばキーを打った以降を自動トラッキングに任せたい場合、
キーまで再生カーソルを移動し、「順方向にトラッキング」を行うとキーから最後までのトラッキングが完成する。
複数モザイク
モザイクを複数掛けるには、モザイクノードを後ろに増やしていくだけ。
動画の出力
クイックエクスポート
ファイルメニュー > クイックエクスポート で「H.264(Master)」で「書き出し」。
ウィンドウに書き出しの進捗が表示され、レンダリング完了したら閉じて終了。
*.mov ファイルが書き出される。
デリバーで MP4 書き出し
デリバーページ
「H.264(Master)」を選択。
「ビデオの書き出し」を有効にし、「フォーマット」をMP4に変更。
字幕を動画に付けたい場合、字幕設定 >「字幕の書き出し」を有効にし、
書き出し方法を「ビデオに焼き付け」とする。
設定が終わったら「レンダーキューに追加」。
右枠「レンダーキュー」にジョブが追加されるので「すべてレンダー」で書き出す。
ジョブはそのまま残るので、一度ジョブを作れば何度でも簡単に書き出しができる。
動作が重いと感じた場合
スペックが足りなくても設定によりパフォーマンスが上がる方法が、下記サイトに書かれているので是非試すべき。
マシンスペックが足りないと悩む前にDaVinciResolve の再生パフォーマンスを上げるために試してみたい10のこと
私が行った設定は以下
DaVinciResolveメニュー > 環境設定 > ユーザー > 再生設定
「UIオーバーレイを非表示」を有効に
「再生中のインターフェース更新頻度最小化」を有効に
「パフォーマンスモード」を自動に
再生メニュー > タイムラインプロキシ解像度 > 1/4
(タイムラインの解像度が1/4に)
上記設定でも足りない場合(※これはプロジェクト作成後に)
ファイルメニュー > プロジェクト設定
「マスター設定:タイムライン解像度」を低く(※ピクセルアスペクト比に注意)
(編集時は低く設定し、最終書き出し時に元に戻す必要あり)
※私のPCの場合、以下の部分で時間がかかる
・インストールに時間がかかる
・ページの最初の切替では数秒待つ必要がある(2回目からは速い)
・その他、反応が遅い所があるが まぁ許容範囲
はっきり言おう、動くことに感謝だ。
中間コーデックには何を使うか
動画編集する際、途中で動画ファイルに書き出す必要に迫られる場合がある。
そんな場合はできるだけ情報ロスの少ないコーデックを選びたい。
では何が良いのか?
・ codec FFV1(可逆圧縮:ロス無)
・ codec DNxHR(可逆圧縮:ロス無)
・ codec GoPro CineForm(非可逆圧縮:ロス少、比較的高圧縮、エンコードデコード高速、編集用に優秀らしい)
(※ちなみに上記コーデックはデフォルトでは動画が見れないと思う)
ファイルサイズ比較(ただし設定によるので目安程度に)
出力動画 1920x1080、30fps、2秒
・Quicktime:FFV1(Intra YUV 422 10bit) 32.7 MB
・Quicktime:CineForm(YUV 10bit、品質:最高) 35.4 MB
・Quicktime:DNxHR(種類:HQX 10bit) 72.6 MB
・Quicktime:H.264(品質:最高) 1.5 MB
うーんたった2秒でこのサイズか…単純計算1分1GBぐらいか。
ストレージも少ないので中間書き出しはあきらめる。