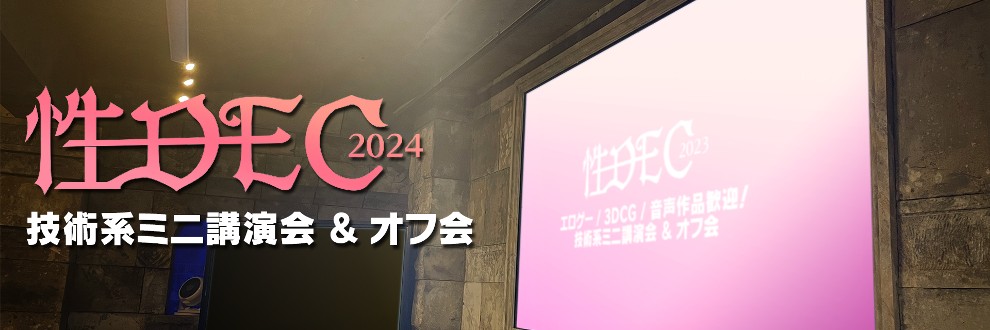音量調整のイロハ
2018/09/17追記: 記事タイトルを「フリーソフトで済ませる音量調整」から変更しました。
「とりあえず正規化」のワナ
BGMや効果音の音量調整の手法としてよく見かけるのが「正規化」です。僕も実は何が正規なのか、invalidやunauthorized、illegalな音量があるのか、よくわかっていないのですが(?)、つまるところ「オーディオのピークを0dBに合わせる」工程を指す言葉です。
この「ピーク」というやつがプロでも厄介なのです。
上の画像はAudacityで適当な音源を開いたときのスクショに説明を付けたものです。
ピンクで示してあるようなトゲトゲ(以後、"ピーク成分"と呼びます)は、波形の中でも音の細かいニュアンスを出す成分です。(本来この部分もひとつながりの波形なので、「成分」という呼び方はふさわしくないかもしれませんが、便宜上。) 数年前のEDMなどではこの部分を極力削減するような音源の仕上げ方が流行っていました。
そこで生まれた余白をオレンジ(以後、"ボディ成分"と呼ぶことがあります)で埋めれば、音の繊細さ、ダイナミクスを犠牲にパッと聞いた感じをデカくでき、カッコいい風に勘違いさせられるわけです。詳しくは「音圧戦争」でググってください。今はいろんな業界の働きかけでこうした傾向は薄れていますが、それでも結構大胆というかなんというか…な人はバカデカい音量で音源を出しています。
あと「音割れポッター」のような音割れ芸の音源はほとんどオレンジの部分しかありません。逆にあんな乱暴な音がピーク成分を保持しながら綺麗に音源に格納されているはずがない。そうそう、音割れポッターごっこがしたくて最近「ハリー・ポッターと賢者の石」のサントラCDを買いました。しかも輸入盤。
正規化は単純にピークを0dBに合わせる処理ですから、ピーク成分が波形のどれだけを占めているかは全く考慮しないのです。
音量ではなく、音量感を整えよう
SoundEngine Freeの「オートマキシマイズ」などでは「音量感の調整」が可能です。SoundEngineにも正規化コマンドはありますがオートマキシマイズを選んでください。
ただしSoundEngine Freeの利用は非営利目的に限られます。僕も癖でFree版を立ち上げがちですがちゃんとPro用ライセンス買っています
あともう少し丁寧にするならオートマキシマイズだけでなく「コンプレッサー」の使用も大事です。セリフの終わり際などあまりに小さい声を少しだけ持ち上げたい、といった場面に効きます
SoundEngineのオートマキシマイズがチェックするのはボディ成分です。例えば音源すべてをそこそこ大きめに揃える場合、ジャズなど元がしっとり目に仕上げてある音源はガツンと音量が持ち上げられ、音圧戦争の兵士たるロック系の音源はほんの少ししか持ちあがらない/むしろ音量を下げられる、といったことが起きるでしょう。
順番が前後しますが、逆に同じ「音量感」に揃えた場合の各音源ごとのピークの違いの例をご紹介します。SoundEngine公式サイト記載の解析タブの仕様も参考にしてください。(僕自身こんなページがあったんだと今更知りました)
後者は音量感を-18dBにしようとした結果ピーク(最大音量)が0dBの天井をぶち破っています。クリッピング=音割れの発生です。特にゲームで使用する場合は気持ち小さめに整えるのがよいでしょう。実際のプレイングで音が割れるのは最悪防げないとしても、元となるオーディオソースの時点でクリッピングしていては話になりません。
最後に(PRを兼ねて)
難しくなってきたら音屋さんに投げるのがいちばんです。
特に音源の数が増えてきたり、音源によって制作者や制作時期が違ったりすれば、ただのオートマキシマイズでは自然な聞こえ方にするのがとても難しくなります。こういった場合には、「整音」を専門的に扱うことのできる人を頼ったほうがいいと思います。
楽曲制作よりも必要な作業の工数が大きくバラけやすいため、KLV Canvasではお見積りにあたり音源の詳細と予算観のご提示をお願いしております。お気軽にご相談ください。