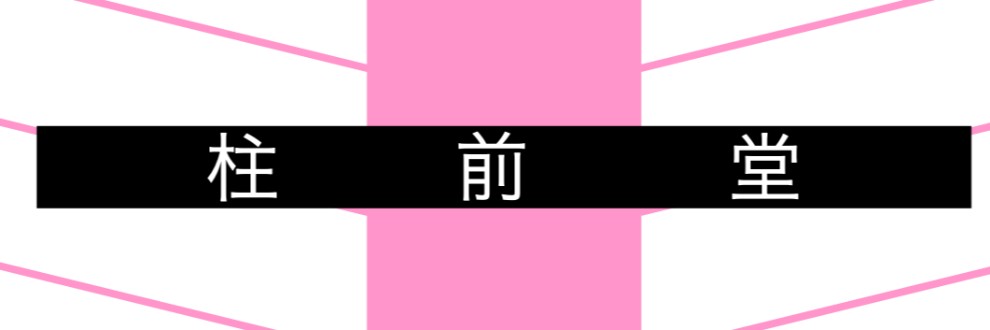【試し読み】幼馴染は妥協しない(復讐ボディブローに絶対負けない幼馴染 第3章)
復讐ボディブローに絶対負けない幼馴染の試し読み、第3章分です。
主人公が5階級上の幼馴染にボディ打ち特訓してもらいます。
―― まずは戴冠おめでとうございます。初めてのタイトルマッチでしたが、いかがでしたか
ありがとうございます。タイトルマッチということで身の引き締まる思いでしたが、実力は発揮できたかなと思います。それ以上に、猫四手選手が強かったですね。
―― ユミナ選手は何度も下馬評をくつがえし無敗で王座につかれたわけですが、そんな新王者にとっても猫四手選手は強敵だったと
確かに戦績上は無敗なんですが、いつ負けてもおかしくない試合ばかりだったと思います。もちろん少しでも勝ちに繋がるように努力してきましたが、全勝という結果は実力というより運と勢いのおかげです。
そういうこれまでの対戦相手と比べても、猫四手選手は別格でしたね。
―― 猫四手選手は再戦を希望しています。初防衛戦の指名挑戦者となると思われますが
私としても、猫四手選手に一度勝っただけでは胸を張ってチャンピオンを名乗れないと考えています。まだまだ技術面では猫四手選手に及ばないと思いますので、挑戦者の意気込みで練習に励みたいと思います。
由実菜に突き付けられた雑誌をそこまで読んで、勇人は顔を上げた。
再会した翌日、ジムの片隅で、二人はグローブを嵌めて向き合っていた。
「ずいぶんとまあ、猫を厚着したな」
「それはインタビューがメールだったから会長達にめちゃくちゃ直されて……じゃなくて! ここ! ここ読んで! 文章はともかく内容は本心だから!」
「猫四手に勝てないかもしれないって? 珍しくしおらしいな」
「言い方! でもまあ、そういうこと。だから本気でやって」
しぶる勇人の背中に、会長が声を投げる。
「勇人! 猫四手のやつ、ボディでノックアウトされたことをかなり恨んでるみたいだからな。試合になれば絶対に狙ってくる。対策は必須だし、うまく防げればチャンスにもなる。しっかりやれ!」
それだけ言うと、勇人が言い返す間もなく他のボクサーの練習に戻った。
反撃を許さない絶妙な間の取り方はリングを降りても往年の名チャンピオンのそれで、勇人はそんな些細なことにも父との、ひいては由実菜との才能の違いを感じてしまう。
「くそっ、親父のやつ。俺の気も知らないで……」
「そういうの今いいから。やるの、やらないの?」
由実菜の練習に付き合うことは勇人にとって「そういう」ことに他ならない。だが、二人の才能を前に拗ねたくなるだなんてダサいことを、幼馴染に言えるわけがなかった。
「分かった。……泣き言言うなよ」
「言ったってゆーくんにしか聞かれないもん」
由実菜は両手を頭の後ろで組み、壁に背をつける。身長差のある勇人が正面に立つと、世界チャンピオンであるはずの由実菜が小さく頼りなく見える。まるで力づくで襲いかかる暴漢になったかのようで、勇人は居心地の悪さを感じた。
勇人は由実菜のお腹にグローブを添えた。鍛え上げた腹筋は厚く、女の子らしくも薄い脂肪の層を盛り上げて割れ目を見せている。由実菜は同階級の選手と比べても背が低く、その分のウェイトを筋肉に回せる。相手選手の攻撃に耐え、チャンスがあれば強引に掴み取るインファイトに最適化した体だ。
勇人は由実菜の腹筋の仕上がりを確かめると、最後におへそのやや上を軽く叩いた。
「……ここ、いくぞ」
「うん、来て」
勇人は由実菜から距離を取り、大きく息を吸う。吐きながら、拳を打ち込んだ。
「んんぶぅぅううっっ!」
20cmの身長差から繰り出されたストレートに、由実菜は目を真ん丸に見開いて悶絶する。硬く閉じられた口から、それでも抑えきれない唾液と苦悶の声が漏れ飛んだ。
由実菜がフェザー級なのに対して、勇人はスーパーウェルター級。性別の違いをさて置いても実に5階級分のウェイト差があり、由実菜の鍛え上げた腹筋もたやすく押し潰した。
「んっ……ぷぷっ……よしこいっ!」
勇人が拳を引き抜くと、由実菜は少しよろけたものの、しっかりと両脚で踏ん張った。気丈に見上げてくる幼馴染の少し潤んだ目に、勇人の心の奥底がざわつく。
「連打いくぞっ!」
「んぶっ! ぶぅう! んんんっ! んぶぅ!? がはぁっ! ぐぶぅぇっ!」
芽生えかけた感情を振り払うように、勇人は拳を振るい続けた。幼馴染の土手っ腹に、同世代の男子を殴り倒すために鍛えた拳が次々と着弾する。
何発か殴りつけると、手応えが変わった。固い壁から、ぐにゃりと不快な肉塊へ。パンチを受け続けた腹筋が保たなくなり、緩んだ瞬間に勇人の拳がめり込んだのだ。筋肉の守りなく内臓を殴られた由実菜は、もはや再び腹筋を固めることなどできなかった。
そんな由実菜に、勇人は手加減しない。柔らかいお腹を次々と抉った。抉りながら、由実菜の様子を注意深く観察する。脚が内股になり、肩が壁から離れかけると、限界と見て次のステップに移る。
「細かくいくぞ」
「んんんんっ! はっ、ああっ! ぐうぅぅ……っ! ああぁーっ!!」
勇人は背中を丸めて由実菜の眼前に潜り込み、サンドバッグにするようにストロークの短い左右のパンチを連打する。手打ちだが、階級差もあり既に腹筋を使えない由実菜には地獄の苦しみだ。絶え間なく襲いくるパンチに内臓を揺さぶられ、呼吸もままならない。
「ラストッ!」
「んぶぅっ!? んんっ……んんんーー!?」
勇人は叫ぶと、一歩脚を引いた。できた空間をフルに使って、拳で半円を描く。太もも、腰、背中の筋肉の力が爆発し、弱りきった由実菜のお腹に渾身のボディアッパーを叩き込んだ。
もはやぐしゃぐしゃになった由実菜の顔が、アッパーの衝撃で押し広げられたかのように膨らむ。涙の滲んだ目は真ん丸に見開かれ、パンパンに膨らんだ頬はすぐに決壊して胃液混じりの唾液の塊を吐き出す。
内臓が押し退けられぐちゃぐちゃと蠢く様子をグローブ越しに感じながら、勇人は拳を抜かない。由実菜の小さな体をジムの壁に縫いつけるかのように、拳を捩じ込んでいく。由実菜の体重の半分は突き上げる勇人の拳に支えられ、由実菜の両脚から力が抜けていく。
「……降ろすぞ、由実菜」
「んんっ……はぁっ、あふぁっ……はぁーっ、はぁーっ、う、ぷ、んんっ! はっ、はーっ!」
ゆっくり由実菜のお腹から拳を抜くと、由実菜はふらつきながらも自分の脚で立ち続けた。お腹と口元をグローブで押さえ、やっと許された呼吸の欲求と込み上げる吐き気とに抗った。
「由実菜、来い!」
「んっ……いくよっ!」
そんな由実菜の前で、勇人は両手を頭の後ろで組んでみせる。攻守交代だ。
ボディに耐えるだけでは駄目、苦しい中で反撃できなければ意味がないという会長の方針で、ボディ打ちの後は打ち込みがセットになっている。
由実菜は今すぐにでもジムの冷たい床に転がってしまいたいはずなのに、声をかけられる前から構えていた。
始まった由実菜のラッシュは、勇人以上に遠慮なくフルスイングだ。だが、勇人は小さく声を漏らす程度で、効いている風ではない。
由実菜が既にグロッギーであることも大きいが、それ以上にここでも階級の差が立ち塞がる。由実菜は彼女の階級では屈指のハードパンチャーだが、そのパンチが平凡なオールラウンダーである勇人に通じない。
由実菜がどれほどボクシングの試合で強くとも、思春期を過ぎた勇人にとって幼馴染はか弱い女の子だった。仮に階級を無視して由実菜とリングで対峙すれば、いくら由実菜のボクシングが巧くとも勝負にならない。一発の重さが違いすぎるため、由実菜の戦略は致命打を貰わないことに重点を置かざるを得ない。一方の勇人は強引に距離を詰めて殴りつければ、ガードの上からだろうと簡単にダウンを奪える。これほどのハンデがあれば、いくら由実菜が天才でも負けるはずはない。
そしてそれは、由実菜が闘わなければならない猫四手 灯歌が相手でも同じことだ。幼馴染が胃液を吐き戻してまで特訓している相手を、勇人ならば簡単に倒すことができる。にも関わらず、勇人がこの幼馴染にしてやれるのはお腹を殴りつけることだけだ。あまりにも歯痒かった。
もちろんこれは、階級を無視すれば、の話だ。ボクシングという競技において、あまりにナンセンスな仮定。第一、勇人が由実菜の代わりに灯歌に勝ったところで何の意味もない。二人はチャンピオンベルトを奪い合っているのであって、手段を選ばない殺し合いをしているわけではないのだから。
そして由実菜にしてやれることを考える一方で、勇人は由実菜との差を見せつけられてもいた。
内臓をめちゃくちゃにやられて地獄の苦しみを味わっている真っ最中だというのに、由実菜は全力のラッシュを放ち続けている。ろくに呼吸もできない中、身体制御に集中しすぎた由実菜の額には冷や汗が滲み、噛み締めたマウスピースから唾液が溢れて口から零れる。
勇人のボクサー人生の中で、ここまで必死に頑張ったことがあっただろうか。
同じジムでボクシングを始めた幼馴染が、片や世界チャンピオンとなって初防衛戦に向けて必死の特訓をし、片や同世代のトップ争いから外れても平気な顔をして遊び歩いている。
勇人にとって、ここまでボクシングに打ち込む由実菜は眩しすぎた。好意を寄せる幼馴染への感情が、歪んでしまうほどに。
「……はぁっ! はぁ、ふっ、ふーっ……! はぁ、はぁ、はぁ……うっ! ……んく、んんん……っぷはぁ」
疲労の限界に達した由実菜がパンチを止める。動き続けることで誤魔化してきた身体の異常が一斉に火を噴く。とくに揺さぶられ続けた胃が収縮し、強烈な吐き気となって由実菜を襲った。
せり上がる胃液をかろうじて収め、飲み下す。きつく閉じられた口の端から、漏れた唾液がつうっと糸を引く。
「い……インターバル……ちょっと……休ませてぇ……」
そう言うと由実菜は、勇人の胸元に寄りかかった。今にも倒れそうな幼馴染の小さな体を、勇人は腕を回して抱き止めた。
短く立たせた由実菜の髪から、汗臭さに混じって甘い匂いが立ち上る。腕の中の小さな体が、活力を取り戻そうと呼吸する大きな揺れが伝わってくる。胸板に押し付けられた顔は柔らかく、唾液が漏れた恥ずかしい跡がひんやりと主張する。
(くそっ……こいつも、人の気を知らないで……)
グロッギーになった幼馴染を、勇人は色っぽいと思ってしまった。日頃からかわいいと思っている女の子が密着しているのだ。その上、由実菜の弱り切った様子は野蛮な本能を刺激する。
勇人の本音を言えば、ちゃんと恋人同士になって堂々といちゃつきたい。由実菜だって憎からず思ってくれているはずだ。
だが、ボクシングに打ち込む由実菜にそんなことを言えるわけがない。カップルらしいことをしたいと思っても、たいやき一つ買ってやることもできないのだから。
だからせめて、練習中の卑怯な接触でもいい、由実菜のことを間近に感じていたかった。
だが、由実菜はあっさりと勇人から離れてしまった。
「はぁっ……はぁっ……ゆーくん、もう一本」
「なっ……はあっ!? 無茶言うな、今にも倒れそう……つーか、さっき吐きかけてたじゃねーか」
「まだ吐いてないもん。本当の本当に限界までやって。私がゆーくんのこと一生許せなくなるくらい」
「……嫌だ」
勇人は由実菜から一歩離れた。
由実菜の中で自分とボクシングが天秤にかけられたみたいで、ショックだった。例えはあくまで例え、由実菜が深く考えて言ったわけじゃないのは分かっている。それでもショックはショックで、そして子供の我儘のような自分の狭量さにもショックを受けた。
「や、やだって……練習、付き合ってくれないの……?」
「もう、十分だろ……」
「まだまだ! ボディは絶対狙ってくるからね、どれだけ耐えられるかが勝負だよ」
「俺は……由実菜がこれ以上苦しむところを見たくない」
「これから試合なんだよ!? 猫四手さんにやられるのはいいわけ!? 私だって、それならゆーくんの方が……」
「そうなる前に、棄権すればいいだろ」
「棄権って……!」
由実菜はコンパクトに身体を締めて勇人の懐に踏み込み、その土手っ腹を突き上げた。
「んぶっ……!」
「ゆーくんのバカぁ! 試合する前から棄権って、それでもボクサーなの!?」
このボディアッパーが効いたのは、由実菜が少し回復したから。そのはずだ。
「俺は……」
「ねえ! 私に勝ってほしくないの!? 偶然で一回ベルトを獲れただけのボクサーで終わっちゃってもいいの!?」
「俺は、由実菜に苦しい目に遭ってほしくない。綺麗な服で出歩いて、好きなもの食べて……」
「それを我慢して試合に備えてるんでしょ! どうしてそんなこと言うの!?」
お前が好きだからだ。とは、勇人は言えなかった。告白するには最悪のシチュエーションだ。
だから、言い返せないうちに、由実菜にキツいことを言われた。言わせてしまった。
「そんな気持ちでリングに上がってるから、ゆーくんは肝心なところで勝てないんでしょ!」
「なっ……負けていいなんて、思ってるわけねーだろ! 一度でも負けたことあったら、そんなこと思わねーよ! 負けたことないくせに!」
「あっ……ごめん……」
「あ、いや……言い過ぎた……」
互いに俯いて、顔を見られない。売り言葉に買い言葉で、つい互いに踏んではいけないところを踏んでしまった。
だが、だからといって、最初の主張を変えるわけにはいかなかった。
「……とにかく、もうボディ打ちの相手はしない。これから寮に帰る」
それだけを絞り出すように告げると、勇人はリングを降りた。
「ゆーくんのバァカ! バカバーカ! そんなこと言うなら応援だって願い下げですー! 試合見に来んなー!」
勇人が更衣室に続くドアを閉めると、ジムの中は静まりかえった。大声で言い争ってジム中の注目を集めていたことに、由実菜は今さら気付いて赤面した。
他のボクサーのサンドバッグ打ちを指導していた会長が、頭を掻きながら声を上げた。
「あー……うちの馬鹿息子がすまん。さ、練習再開だ! 由実菜は顔洗ってこい! 戻ってきたらサンドバッグ打ちだ!」