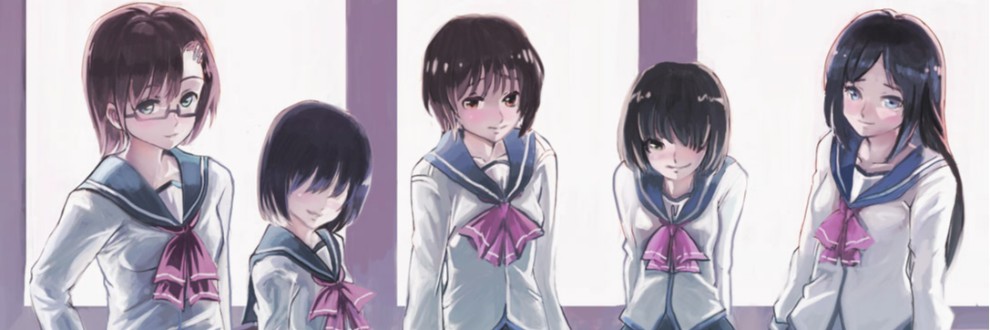幼馴染との恋愛。童貞の僕と、隠れヤリマンの彼女。初めての交尾。
一
気弱で頼りない尻谷柚とは僕のことだ。学力や運動、容姿・家庭の全てにおいて並み以下の位置におり、特に此れと言った特技も持たず、只管に哀れを極めていた。
虐められた経験も多く、入学したばかりの小筒津学園では、良くも悪くも目立たぬように息を潜めて過ごしている。そんなパッとしない僕だけど、最近になって一つ成し遂げた快挙があった。
放課後の教室にて一人で静かに佇んでいると、その快挙が忙しなく現れる。教室のドアが勢いよく開かれ、その者は両手を合わせながら、開口一番に謝ってくれた。
「はぁ、はぁ、はぁ、柚くん、ごめーん! めっちゃ待たせちゃった。思ったより委員会が長引いて……はぁ、はぁ、はぁっ……」
「あっ、唯香っ……だ、大丈夫だよ」
「でも二時間くらい待ったでしょ。ホント、申し訳ないっ!」
「だ、だから良いって。委員会だったんだし仕方ないよ……」
「あははっ、ありがと」
快挙とは、生まれて初めての恋人が出来たこと。相手は晴峰唯香と言い、クラスメイトであり、同時に古くから知る幼馴染でもあった。
成績は僕より悪く、快活な性格とは裏腹に運動神経も優れていない。そこまで可愛いという訳でもなくて、取り柄と言えば、いつも元気なことくらいか。お陰でライバルも少なかったので、割とあっさり付き合うことが出来た。
と言っても、幼少期から片思いしていた事実には変わりないが……
「えっと、帰ろうか?」
「待って。帰る前にさ、部室に寄らない?」
「ドキッ」
「良い? この前の続き……したいんでしょ?」
「うう……う、うん!!」
帰り支度をする僕に唯香が首を横へと振り、代わりに別のお誘いを持ち掛けてくる。部室という単語だけで、僕の心臓が高鳴ってしまう。
これがエッチのお誘いであることが明らかだからだ。
小筒津学園には茶道部があり、立派な和室を構えているも、部員は唯香のみという現状だ。顧問すら滅多に訪れない部室を殆んど唯香が独占していると言って良い。そんな場所に、いまから恋人同士が赴く。もはや、疑いの余地は無かった。
「あはっ、それじゃ、行こっか♪」
「……うん」
「手……握る?」
「……うん」
「ん、そういえば、もう付き合って二か月くらい経つけど、こうして手を握るのって初めてじゃない?」
「そう、かも」
「あはは。順番が逆だよね。前にさ、ほら……」
「う、うん。手コキしてもらった……」
「…………」
「最高の体験だった」
「よ、良かった。今日は、もっと気持ち良いことしてあげるね♪」
唯香の差し伸べる手を静かに握る。いまが夕日の差し込む時間帯で助かった。確かめるまでもなく、僕の顔は真っ赤に染まっていることだろう。世界を灼熱に染める夕焼けが僕の赤面を誤魔化してくれている。けれど、手汗だけは誤魔化しようが無くて……人気のない廊下を歩く中で僕は一人で勝手にしどろもどろしていた。
やがて茶道室に到着する。校舎の離れに有る建物の一室……そこが茶道部の活動拠点だ。唯香だけが持つ鍵にてドアを開錠すると、間もなく畳の心地良い匂いが伝わってきた。
「あの時のままだね」
「先生すら来ない場所だからね。好きな場所に座ってて」
「うん」
「緊張してる?」
「そりゃあ……当たり前でしょ。僕は……初めてなんだから」
「そっか。嬉しい」
「唯香は……初めてじゃないんだよね」
「……うん。いままで二人の男性と付き合ったから……」
「一人は、僕の兄なんだよね……」
「…………」
「なんで別れたんだっけ?」
「いま、その話をしたいの?」
「……止めておこっか」
部室に入ると、すぐに唯香が鍵を掛ける。部屋は本校舎から離れた場所に孤立しており、多少大きな声を出しても誰かに聞こえることはない。邪魔の入らない二人っきりという状況に、早速と煩悩ばかりが溢れてしまう。血液が下半身へと集中してしまい、初めてのセックスということから、心臓もバクバクと鳴りっぱなしだった。
「そういえば、コンドームは……」
「ちゃんと持ってきたよっ! 今日は大丈夫っ!」
「良かった。今日こそ、最後まで出来るね」
「う、うんっ」
「あはは、私も緊張してきちゃった。少し待ってて、手を洗ってくるから。デリケートな場所も綺麗にしたい」
「あ、それじゃあ、僕も……」
なお、エッチを目的に茶道部の部屋を訪れたのは、これで二度目だ。つい先日にも訪ねたばかりであり、その時はお互いに服を脱ぐ所まで漕ぎ付けられた。コンドームが無いせいで惜しくも最後の行為までは至れなかったけど、その代わりに唯香の手コキを味わうことが出来た。
唯香の繊手と甘い肉体は最高の思い出である。だけど、まだ最後の一手が残っている。通販で購入した十二個入りのコンドームパックを取り出すと、突っ張ったズボンをそのままに、正座しながら唯香との一手を心待つのだった。
二
八畳の和室にて僕と唯香の二人きり。お互いに向かい合い、正座の姿勢で見つめ合っている。茶道部員として正座がデフォルトな唯香に対し、僕は単なる緊張感から、自然と畏まった姿勢を取っていた。
どっちから動くことも無く、暫く睨めっこの状態が続いてしまう。
「…………」
「…………」
少し照れたような、はにかんだ顔が眼前にある。見飽きるくらいに馴染んだ顔の筈なのに、どうしてこんなにも心を打たれるのか。目を合わせるだけでも心臓が煩わしい。やたら顔が熱くなり、指先の震えすら感じた。
「柚くん。顔がめっちゃ真っ赤だよ」
「うう……」
「可愛い❤」
「み、視ないでよ。は、早く始めよう?」
「そうだね。それじゃあ、まずはキスから?」
「う、うんっ」
「そういえば、まだキスもしてないよね。柚くん、キスの経験は?」
「……したことない」
「私がファーストキスの相手なんだ……すっごく嬉しい❤」
「んっ……」
僕とは違い、経験のある唯香が事をリードしてくれる。唯香は処女ではなく、それどころか前に僕の兄と付き合っていた時期もあった。
女慣れした兄と童貞の僕を比較されるのが怖い……そんな気持ちを汲んだように、唯香は赤ちゃんを宥めるように優しく僕を抱き締めてくれた。
そして、女子特有の蕩ける香りに魅される暇も無く、唯香の花唇が僕に重なる。お互いに膝立ちした状態で唯香が僕をハグしながら――。
「んっ……」
「ふぅっ、んんんっ……」
……僕の、初めてのキスだった。
唇が触れた瞬間、感動の余りに視界が明滅する。舌を搦めるような濃厚なキスではない。唇が重なっただけのキスである。でも、唯香の唇は想像よりも遥かに柔らかくて、甘くて……僕の理性を剥がすには十分すぎる刺激だった。
十秒くらいが経ち、そっと唯香が離れる。
「柚くん、キス上手だね」
「ぁ、う、そ、そう、かな?」
「柔らかくて気持ち良かった! もう一回しよ?」
「あ、うん……」
「んっ、ちゅっ……」
ファーストキスに心を奪われて曖昧な返事をしてしまう。なにかを言う前に、再び唯香の唇が覆い被さった。
「んっ、んちゅっ……んっ……」
またも唇同士が触れ合うだけのキス。でも、今度はもっと情熱的だ。唯香が両手で強く抱き寄せてのキスである。お互いに密着状態になり、僕の滾りに滾った股間が唯香へと当たってしまう。さり気なくお尻を引いてテントを退けようとするも、唯香は「そんなの気にするな」と言わんばかりに、くっ付いてきた。
「うっ、んっ……ちょ、ちょっと……んっ……」
「はぁっ、んっ、柚くんっ、すっごい興奮してるね。んっ……だって、ずっと勃ちっ放しじゃん……んちゅっ、んっ……可愛いっ❤」
「うぁ、き、気付いてたんだ。は、恥ずかしい……」
「生理現象なんだから気にしなくて良いんじゃない?」
「恥ずかしいものは恥ずかしいんだ……んっ……」
「柚くん、良い匂い……」
「うああ、に、匂い嗅がれるのも恥ずかしい……」
「すんすんっ、ん~っ、柚くぅん❤」
実は、廊下で手を繋いだ頃から既に股間はオーバーヒートしていた。
ズボンがパツパツに盛り上がっており、下着の中は見るまでもなく先走り汁で哀れに濡れている。そんな状態での唯香と密着キスなのだ。テントが唯香の下腹部に擦れたままのキスは、思わずイッてしまいそうになるくらい、かなり気持ち良かった。
このまま射精したくて堪らない気分である。勿論、やらないけど……と、思っていたのに、気付けば密着したまま無意識に腰をグリグリ動かしていた。テントが唯香の腹部に擦れる。
「ふぁあっ、柚くんっ……硬いの、当たってるっ❤」
「あ、ご、ごめんっ。調子に乗り過ぎた……」
「怒ってないよ。寧ろ、嬉しいかな。こんなに喜んでくれて❤」
「うう、唯香が、その……めちゃくちゃ可愛くて……」
「嬉しいよぉっ❤ もっかいキスしよっ! んっ♪」
「んっ、ふぅうっ、ゆ、唯香も、キ、キスが上手だよっ」
「ありがと。柚くん、大好きっ❤」
「うあぁあっ、僕ら幼馴染なのに。唯香とこんなことしてるなんてっ、未だに信じられないよ。あぁあっ、こ、股間が唯香に当たってるっ! あぁああっ、で、出ちゃいそうっ!」
「えっ、本当っ?」
「う、うん。も、もうイキそうかもっ……」
「ん……ちょ、ちょっとストップッ! そこで出しちゃって良いの?男の人って何回も出来る訳じゃ無いし、ズボンの中で出しちゃうのは勿体ないんじゃないっ?」
「う、ううっ……」
「まずはズボンを脱いで、ね?」
「わ、わかった」
抱き合ったまま、お互いに愛し合っていた所で唯香が離れてしまう。
あと少し離れるのが遅かったら、本当に下着の中で射精していたかもしれない。残念だけど、唯香の言う通り何発も放てる訳では無いので、密着キスはこのくらいに留めることに。
でも、衣服越しの触れ合いがこんなに気持ち良いとは……これから唯香の全裸が拝めるというのに、暫く名残惜しさが続いた。
「お互いに脱がせ合いっこしよっか♪」
「う、うんっ」
「まずは私の服を脱がせてみて?」
「わかった」
そうして遂に脱衣が始まる。唯香の嗜好で、それぞれ服を脱がせることに。ブレザーのボタンを丁寧に外して、ワイシャツも脱がせると。清潔感のある白いブラジャーが現れた。
「……はぁ、はぁ、はぁ」
唯香は運動音痴ではあるけど、スポーツが嫌いという訳では無い。合間を見つけては運動を嗜む唯香の、スラリとした肢体が露わとなり、僕の興奮も拍車を掛けていく。極めつけは、年相応に育った瑞々しい乳房だ。ブラジャーで絞められた谷間と、ふんわり甘そうな肉の盛り上がりに、僕は荒々しい鼻息を隠せそうになかった。
現れたブラを、すぐに取り外しに掛かる。フロントホック式のブラだったので、あっさり外すことに成功した。中々外せず焦りに焦った前日とは違い、スムーズな自分に内心でホッとする。
「…………」
「おおっ!」
やがて待ちに待った乳房がお目見えになる。しなやかな肉の恵みと、その山頂には自己主張をする淡い色の乳首があった。
性を目の当たりに、僕の顔が一層に熱くなるのを感じる。この場に恥じらいを感じているのか、唯香の挙動が落ち着かなくなり、確かに顔も赤くなっていた。
全体的に色白な唯香は、ほんのりな紅潮でも赤みが明らかになる。僕に対して緊張しているのが嬉しくて仕方なかった。
「はぁ、はあ、あぁっ……」
「柚くん興奮し過ぎだよ。おっぱいなら、この前も観たでしょ」
「前の時は……緊張し過ぎて全然覚えてない」
「確かに。前は、すっごいテンパってたもんね」
「うん」
「…………」
「乳首、勃ってる……」
「ん、当然でしょ。私だって興奮する」
「触って良い?」
「許可なんて要らないよ」
「あ、ありがとう。じゃ、じゃあ、揉むね」
「……ぁっ」
よく分からないけど、この大きさならDカップはあるだろう。手にフィットし易そうなサイズだ。試しに、両手を双峰へと乗せてみる。
……確かな弾力が伝わり、脳の溶けるような刺激が走った。
そして、何度も圧搾を続けていく。
「柔らかい」
「ありがと♪」
「痛くない?」
「平気。もっと強く揉んで良いよ」
「ん…………気持ち良い?」
「……うん。気持ち良いよ」
「もっと揉んじゃう!」
「……んっ、柚くんの手、温かいっ」
「気持ち良い?」
「……うん。ふぁっ、あっ……」
「可愛い声。もっと気持ち良くさせてあげるねっ!」
次第に唯香から色っぽい声が漏れてくる。感じてくれる唯香に気を良くした僕は、もっと満足させたいと思い、もういくらかおっぱいの按摩を繰り返すのだった。
フォロワー以上限定無料
続き
無料