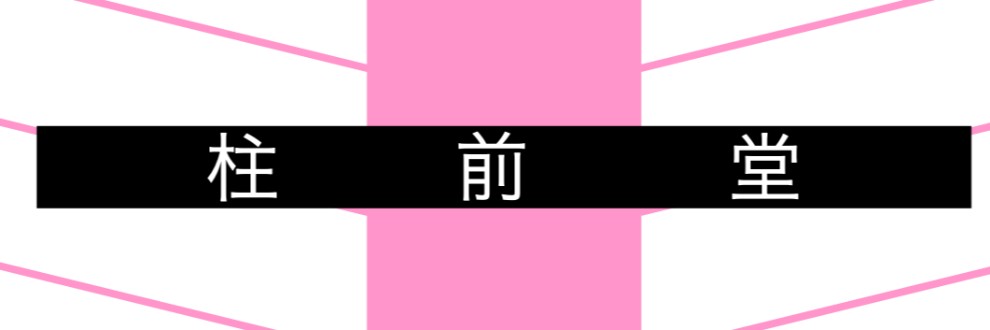【試し読み】幼馴染はチャンピオン(復讐ボディブローに絶対負けない幼馴染 第1章)
復讐ボディブローに絶対負けない幼馴染の試し読み、第1章分です。
主人公の日常風景、幼馴染の関係をお楽しみください。
館林 勇人が改札を出ると、2つ年下の幼馴染の姿はすぐに見つけられた。
目が合った犬芥 由実菜は、ブンブン手を振って勇人に駆け寄った。
「やー、久しぶり! ゆーくん、背が伸びた?」
「一週間で伸びるか、由実菜が小さいんだろ」
勇人の頭頂まで手を伸ばそうとする由実菜の頭をポンポン撫でる。
勇人より20cm以上低い身長は、実に撫でやすい。二人の身長に差がついた数年前に面白がって頭を撫でていたのが、今では定番のスキンシップになってしまった。
前の休みで由実菜と別れてからわずか一週間、されど一週間。大学の寮で過ごし、この町と、由実菜と離れている間に何かが変わってしまうのではないかという不安が、たちまち解けていく。
駅から商店街を突っ切って実家まで、二人で並んで歩く。
身長181cm、大学のボクシング部ではスーパーウェルター級の勇人の体は縦にも横にも大きく、とにかく目立つ。それでなくても、顔を知られた地元なのだ。
だが、155cmの由実菜がそれ以上に目立つ。毎日通っている地元だというのに、初めて来た遊園地のように落ち着きがないからだ。
ボーイッシュに跳ねさせたショートカットは金髪に染めていて、由実菜の丸っこい顔をますます小さく見せている。
シャツの裾を結んでお腹を出し、きわどいクラッシュホットパンツを履いた格好はともすればセクシーになりかねないが、由実菜の場合はやんちゃな印象が先に立つ。短く絞られたシャツが隠すことでかえって強調されている小さな胸やホットパンツの破れた布地に縁取られた締まったお尻よりも、割れた腹筋やよく絞られたくびれ、シルエットからは意外なほどに太く発達した手足の筋肉に目がいくからだ。
シルバーアクセが好きで、チョーカーやイヤリングはなかなかサマになっている。これでカラオケに行くとロックを熱唱するので、小っこいくせにいやに格好いい。
童顔な由実菜の大きな目は何を見ても楽しいとばかりにきょろきょろ動き、太めの眉が追従する。それでいて、歩幅の大きい勇人に遅れるどころか手を引いて前を行く。
今年で高校卒業する歳とは思えないほど、小動物っぽい女の子。
我が幼馴染ながら、尋常じゃなく可愛い、と勇人は思う。惚れた弱味かもしれないが。
「それでね、昨日までは赤羽さんがスパーリングパートナーに来てくれてたの」
「赤羽……って、あのハードパンチャーの」
「そうそう。私と再戦するまで負けたら承知しません、って、すごく熱心につきあってくれて」
「はー……。あんな真面目で大人しそうな人が、そんな好戦的な……」
「なんかね、負けたことはあるけど、あんなに悔しい負けは初めてだって。だから私も、赤羽さんに勝って嬉しかったことは今でもはっきり覚えてるって言っておいた」
由実菜とファイトスタイルが噛み合った赤羽戦は、激しい乱打戦で語り草になっている。間近で見ていた勇人からすれば、とくに心臓に悪かった試合の一つだ。
とくに最終ラウンドで、赤羽が予想外の粘りを見せたときは、どっちかが壊れるまで終わらないんじゃないかとすら思った。頭がいいからか妙に諦めの早いところがある赤羽がああも根性を見せたのは、後にも先にも由実菜戦だけだ。
「まー、あんなに言われたら負けられないよね。責任重大、ってね」
にかっと笑う由実菜は、そう言うわりにプレッシャーを受けた悲愴さは感じられない。爽やかな闘志をぶつけられて、自らの闘志を燃え上がらせている。
そんな話をしていると、通りかかった八百屋のオヤジから声がかかった。
「おや由実ぼう、今日はカレシも一緒か」
「カレ……っ!? ちち、違いますー! 見ての通りのゆーくんですー!」
「まあ、そのタッパは見間違えないな」
「いやあ、ははは……ご無沙汰してます」
地元の大人には由実菜と遊び回っていた頃から知られている。今は勇人の方が見下ろすほどに大きくなったが、だからこそ頭が上がらない。
「今日は迎えに来ただけ! すぐ帰りますー」
「おおそうか、由実ぼう、毎日頑張ってるもんなあ! 次の試合も楽しみにしてるよ」
「あれ、オヤジさんボクシング観ましたっけ」
「いやあ、お前らが出るなら観るだろ。そしたらなあ、由実ぼうが倒されても躱されても諦めないで、最後には勝つんだもの。思わず手に汗握って観ちまって。もうすっかり試合が楽しみになっちまったよ」
「いやーははは……照れるなもう。でもまあ、これからもっともっとすごい試合しますから」
手を振るオヤジさんと別れて、実家への道に戻る。
地元の大人たちは、初期の由実菜ファンと言える。元々顔見知りという条件はあれど、由実菜は自分のファイトでボクシングに興味のなかった大人たちのハートを掴んでいる。
由実菜が進路を決めたとき、どんなボクサーになりたいか聞かれたのを勇人は覚えている。ボクシングに興味がない人にもファンになってもらえる、魅力的な強さを持ったボクサーだと即答したときは、いつまでも子供みたいな幼馴染も案外いろいろ考えているんだな、と思っただけだった。
だが、少し離れて見てみると、由実菜は着実に夢に向かって進んでいるようだった。
などと考えながら歩いていると、由実菜の脚が遅れてきているのに気付いた。見ると、その視線はたいやき屋に吸い寄せられている。
「……食べたいのか?」
「えっ、あっ、いやー……」
「奢るぞ? わざわざ迎えに来てくれたんだし」
「うっ、ぐぐぐ……いや、やめ……とく!」
小さな体で食べたい由実菜と自制する由実菜の二人分を表現するかのように大きく悶え、それから太刀を振り下ろすかのように宣言する。
買い食いの一つもすればデートっぽさが増すし、という勇人の下心は粉砕された。
「まだ減量は始めてないんだろ?」
「そうだけど〜やっぱりカロリーは怖い……」
「そっか」
「それに、ジムに着いたらまたすぐ練習だし。あんまり胃に入れると……ホラ、その」
吐く、と直接的に言わなくなっただけ、やんちゃな幼馴染も成長したものだ。もちろん勇人は乙女にそんなことをわざわざ指摘しない。
「練習の合間にゆーくんの出迎えって言ってやっと休憩時間貰ったんだから。なんだかんだ会長も息子に甘いよね」
親父が甘いのは俺にじゃないだろう、と言えないのは、気配りなのかヘタレなのか。
背後にブンブン振り回される尻尾が見えそうな幼馴染を見ながら、勇人は悩む。
そんな勇人の内心に気付かず、由実菜は続けた。
「やっぱりさ、リングに上がっちゃったら、やっぱり逃げて出直すってわけにはいかないから。練習できるうちには練習しておきたい。あの時たいやきを止めておけば、っていうのは……ちょっと間抜けすぎるよね」
前のめりと呼べるほど熱心な幼馴染の言葉が、チクリと勇人の胸に刺さる。
勇人はたいやきどころか、由実菜と会っていない間に何度も合コンに行った。
勇人の父は元世界チャンピオンにしてジムオーナー。当然のように、小学校に上がると同時にジムでの練習が始まった。
英才教育の甲斐あって、ジュニアのうちはかなりの成績を残した。勇人もこのまま順調に勝ち続け、いずれは父のように世界を獲るのだと、希望と心地良いプレッシャーを感じていた。
ところが、高校生になると思うように勝てなくなった。磨き上げた基礎の動きはまだ優位性を保っていたが、ジュニアの頃ほど圧倒的な武器ではなくなった。フィジカルで押し負ける場面が増えた。多様化する戦術に対応しきれなくなった。
つまるところ、ライバル達も練習を積んできたことで、英才教育のリードが縮んでしまった。そして勇人のもう一つの武器であったはずの才能は、そもそも存在しなかったのだ。
青春の中で悩みに悩んだ勇人は、そう理解した。
勇人の高校での記録は、インターハイ2回戦突破という、肩書のわりには微妙な成績だった。スポーツ推薦で大学に進学し、今は生家のジムを離れボクシング部の寮でボクシングを続けている。
環境を変えればまた伸びるかも、という周囲の期待を裏切り、勇人はやはり同世代のトップ争いから脱落した。
一度自分の才能に見切りをつけてしまった勇人は、実家にいた頃のようにストイックなままではいられなかった。スポーツ推薦で入ったボクシング部の寮生活は厳しかったが、抜け出して遊ぶことを覚え、この半年ほどですっかり”大学生らしい”交友関係を築き上げた。
そんな勇人にとって、今も成長を続け自身の実力に希望を持っている由実菜は眩しすぎた。もう子供の頃からこれが自分の人生だと思っていたボクシングを、止めてしまおうかと思うほどに。
偉大な世界王者のセンスも情熱も、息子に引き継がれなかった。だがそれと同じものが、勇人の真似をして入門した2つ下の幼馴染に秘められていた。
勇人が同世代の中で伸び悩む一方、高校入学と同時に全世代を相手にするプロデビューが決まるほどに。無謀と言われた試合を幾度となく勝ち抜くほどに。
幼馴染の手を引いて商店街を歩く女の子、犬芥 由実菜は世界チャンピオンなのだ。