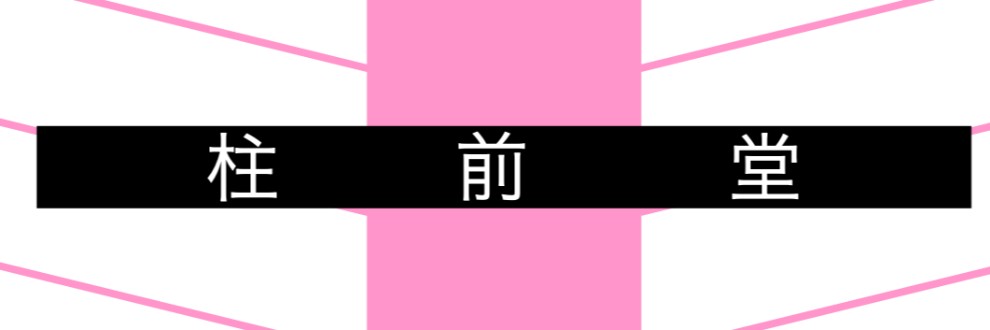【試し読み】幼馴染は立ち向かう(復讐ボディブローに絶対負けない幼馴染 第4章途中まで)
復讐ボディブローに絶対負けない幼馴染の試し読み、第4章の途中までです。
ついに始まる復讐のタイトルマッチ。主人公の由実菜と敵役の灯歌、二人の試合衣装と決意をお楽しみください。
花道へ続くコンクリートの通路は、会場の熱気が届いているのに妙に冷たく思える。
由実菜は、この冷たさが好きだった。どれほどファイトマネーが増えファンが増えても、結局は殴り倒すか倒されるかというボクシングのシンプルさを再確認できるようで。
だが、リングの上が厳しい世界だとは思っていても、リングの上で一人きりだと思ったことはなかった。
これまでは。
「すまねえな由実菜。あの馬鹿息子、まさか本当に帰ってこねえとは……」
「ううん、私があんなこと言っちゃったから……」
由実菜の背中に不安を見て取ったのか、後ろを歩く会長が声をかけてくる。
「いいや、幼馴染の大事なときに駆けつけねえような育て方した覚えはねえ。悩んでるようだからって甘やかしちまったが、こうなったらアマチュアのてっぺんでも獲らねえ限りウチの敷居はまたがせねえぞ」
「……そんなこと言うと、ゆーくん、本当に帰ってこないかも」
先頭を歩いていた由実菜が足を止めた。通路の先では、既に挑戦者がリングインを済ませ、観客がチャンピオンの入場を今か今かと待ち構えている。だが、由実菜の足は止まってしまった。
「ゆーくんのパンチ、効きました。すっごく重かった。けど……本当は、あんなものじゃないはず。ゆーくんはもっと追い込めるはずです」
「アイツがサボってるって? 親父がトレーナーじゃやりにくいかと思って大学に入れたが、逆効果だったか……」
「ゆーくんは、ボクシングが好きじゃないのかも」
「それは……そう、なのかもな。俺も由実菜も、アイツの気持ちを分かってやれるとは言えねえ」
由実菜は今のところプロ無敗。会長は手痛い敗北の経験もあるが、それも世界ランカーになってからの話だ。
同世代や、幼馴染の女の子に差をつけられたまま伸び悩んでいる勇人と同じ立場になれるとは言いにくい。
そんな由実菜が出来ることに思い当たって、会長は俯いていた顔を慌てて上げた。
「だからって、負けてみようなんて考えるなよ?」
「もちろん! わざと負けたりなんかしたら、それこそゆーくんから遠くなっちゃうから。いけるところまでいきます」
「よぉしその意気だ!」
会長が背中を張り手で叩いて気合いを入れると、由実菜は少しよろけながら再び歩き出す。
「いないと心細いけど……ゆーくんが来たくないなら、いない方がいいのかも。私が、ゆーくんのボクシングに邪魔だったなら……」
「そうだな、気にすんな。アイツはアイツでいいようにやるし、それでダメなら自業自得だ」
「あはは、親子だと容赦ないですね」
ついに由実菜がコンクリ打ちっ放しの通路を抜け、花道に足を踏み出す。花道を照らすスポットライトが、試合中継のカメラが、会場中の歓声が由実菜に集中する。
『熱いファイトで連勝街道を突き進む天才女子高生ボクサーが、ついにチャンピオンベルトとともにリングイン!
もう一度猫四手選手に勝たなければ名実ともにチャンピオンとは言えないと、そうインタビューに答えていました。勢いに乗りながら謙虚に成長を続ける怪物が、新時代を築くのか時代の徒花となってしまうのか! その試金石となる試合です!』
観客の歓声に包まれながら、由実菜は花道を行く。リハーサル通り、逸る気持ちを抑えてチャンピオンらしく堂々と歩く。
背後には会長とセコンドについてくれたジムのトレーナー陣が続き、由実菜のチャンピオンベルトを高々と掲げる。がむしゃらに目指してきた目標は、今は由実菜の背中にある。
リハーサルと一番違うのが、観客が入っているところだ。緊張して早く試合を始めてしまいたい由実菜は、ホールを埋めつくす観客を眺めて気を逸らす。
由実菜を迎える会場は、席によって温度差がある。それはそのまま、このタイトルマッチの下馬評でもある。
熱烈に迎えてくれるのは由実菜のファン。若く無敗という由実菜の話題性と、体当たりで勝機を掴むファイトに魅せられた者達だ。彼らは今日も、由実菜の劇的な逆転勝利が観られることを期待している。
一方、比較的抑え目な観客は灯歌のファン。大人の魅力と経験に裏打ちされた堅実なボクシングを評価し、由実菜が勝った前回のタイトルマッチはまぐれだと考えている。彼らは灯歌と由実菜が闘えば10回に9回は灯歌が勝つし、今度こそまぐれの負けはないと思っている。
由実菜は重圧に息を呑む。由実菜ファンの期待に応え、灯歌ファンにチャンピオンにふさわしい実力を見せなければならない。そして、どちらでもない人達にも、ボクシングの世界チャンピオンというものが憧れになるよう魅せなければならない。
由実菜が目指してきたチャンピオンとは、そういう存在だったのだから。
由実菜が指定した入場曲は、カラオケでもよく歌うメタルロック。自らの強さを吼え立てる挑発的な歌詞は、会場スタッフに全国中継に流すにはいささか品がないなどとやんわり止められかけた。だが、試合に勝つためには絶対に必要だと押し切った。
勇人が欠けている試合で、それ以上少しでも普段と違うことは避けたかった。ただでさえ二度目のタイトルマッチ、初めての防衛戦なのだ。
入場曲が終わると同時、会長が広げたロープの間をくぐって由実菜はリングインした。
リングの上から見回す会場は、さらに狹く、迫ってくるかのように見えた。品定めされているかのような緊張感に呑まれかけ、由実菜は小さく深呼吸して体の硬ばりをほぐす。
『ただいまより、WFBC世界フェザー級タイトルマッチ10回戦を始めます。
赤コーナー! 9戦9勝9KO無敗、WFBC世界フェザー級チャンピオン、ユミナ!』
コールを受けて、由実菜は黒いガウンを脱ぎ落とす。
まずフードが外れ、現れたのは金髪の跳ねたショートカット。階級の中でも小柄な由実菜の小動物っぽさを象徴する髪型はファンにも人気だ。
肩口には黄色のスポーツブラがかかる。金髪と合わせ、由実菜のイメージカラーに統一されている。ボクサーらしく控えめに膨らんだ胸は、由実菜のシルエットを崩さずに女の子らしいしなやかさを強調する。肩から伸びた腕は、違和感があるほどに太い。相手ボクサーをことごとくノックアウトしてきたこの豪腕こそ、世界一の女の子の証。
スカートも同じ黄色だが、その下に黒いスパッツが覗く。黒い布地に包まれた脚もまた発達した筋肉が盛り上がり、数々の打ち合いを制してきた由実菜を力強く支える。
そしてその間に、今日のため鍛え上げた腹筋が鎮座する。なだらかな脂肪の層を残しつつ、発達した腹直筋はその層をも押し上げ6つに割れていることを誇示している。その厚くしなやかな複合装甲が、由実菜の深呼吸に従って大きく上下する。
そして、黄色のボクシンググローブ。相手を殴り倒すことだけに専念する誓いの証が、由実菜の両腕に嵌められている。
(……よし、やれる)
由実菜は歓声に応え、小さくシャドーをして見せる。体の軽さ、思い通りに動く動作の正確さに、初防衛戦に向けた手応えを感じる。
タイトルマッチに向けて鍛え、減量し、整えてきたコンディションは過去最高。メンタル面でもほどよく緊張して冷静だ。犬芥由実菜が今出せる全力をぶつけられる。勇人がセコンドにいない心細さも、今は気にならない。
そうだ、ゆーくんなんかいなくったって勝たなきゃ、チャンピオン失格だ。
ほどよいところで手を止め、リングの対角を睨む。紹介を待つガウンの女は、猫四手灯歌。由実菜を含め多くの観客がチャンピオンの実力があると考える、恐るべきチャレンジャーだ。
花道を向かってくるユミナを、先にリングインした灯歌は忌々しげに見つめていた。
「灯歌さん、大丈夫ですか。いくら実力じゃ灯歌さんが上って言っても、冷静さを欠いて勝てる相手じゃないですよ」
「分かってるわよ……」
セコンドの大男が、灯歌の隠し切れない苛立ちを察して声をかける。
結城 八尋は自身も世界ランカーまで登り詰めた才能あるボクサーだった。目の故障で引退したところを灯歌に拾われたことを感謝しているし、誰よりも近くで灯歌のボクシングを見てきた彼は灯歌こそチャンピオンにふさわしいと信じている。
だから、灯歌がこの試合で勝つこと以外の目的を持って臨んでいるのが心配だった。
「あの小娘が油断ならない相手なのは、一度闘った私が一番よく分かってる。でも、私はあのガキに吐かされたのよ」
猫四手灯歌といえば、強くしなやかな、余裕ある大人の代名詞。ただボクシングの世界チャンピオンとして有名なだけではなく、その美貌と自信に溢れた態度でファッションや美容の世界でも知られている。実際、灯歌の名前を使ったブランドやCM出演もあり、タイトルマッチのファイトマネーを軽く越える収入になっている。
八尋もその金で雇われている。彼の指導をはじめ、金に糸目をつけない練習環境は灯歌の実力を支える一端となっている。そうして灯歌は世界チャンピオンというブランドを手にし、この看板によってさらにモデルとしての収入を増やした。灯歌はボクシングとモデルという二足のわらじを履きこなしていた。
もちろん、練習環境に投資して実力となるのは、かけた金を使い切るだけの練習量があってこその話だ。灯歌はそれだけの練習を重ねている。それも、モデル業にも同じだけの熱意と時間をかけながら。その姿を見てきた八尋は、灯歌こそチャンピオンにふさわしい実力者だと信じている。
もっとも、日々指導する彼は、灯歌の築き上げてきた「余裕ある大人」というイメージとは裏腹に、彼女の本性がひどく狭量で自己中心的なことを知ってしまったのだが。
灯歌が初めてボクシングをしたのは高校の部活動だった。既に学内で美人と有名だった灯歌は、美容健康のために入ったボクシング部で、眠っていた才能を目覚めさせた。リングの上で浴びる喝采は、誰よりも目立ちたいという灯歌の本能をひどく刺激した。
大学進学のために上京し、同時にプロデビュー。以来着実にキャリアを積み上げ、世界チャンピオンになり三度防衛するに至った。その間にも女としての美しさを磨くことは忘れず、モデルの仕事で稼いだ資金と自尊心でボクシングに勝ち、ボクシングで得た知名度とイメージで美しさの価値を釣り上げた。
灯歌のボクシングと美容の両輪は、極めて上手く回っていた。
ユミナが彼女のリングに立つまでは。
ユミナに敗れたことで、解約されたり更新されなかった契約が3本出た。うち1つはチャンピオンでいることが条件だったので仕方ないが、残りの2つは明らかに灯歌の嘔吐が放送されたのが原因だった。
だが灯歌は、そんなことはどうでもよかった。失った仕事など後でいくらでも取り戻せる。灯歌は自身の美しさとその価値に絶対の自信があった。
そんな美しさを、公開の場で穢されたことが許せないのだ。ユミナを同じ目に遭わせてやるまでは、ベルトのこともCMのことも考えられなかった。
灯歌が見つめる中、リングに上がったユミナがコールを受けてガウンを脱ぐ。灯歌は自分の前に立った女を、じっくりと品定めする。
ユミナは現役高校生という話題性をさし引いても、まあまあの美少女だ。ショートカットで強調された小顔に、はっきりと見開かれた大きな目。黄色を基調に黒を入れたスカートとスポーツブラも、灯歌の目からすればまだまだ垢抜けないが、かわいらしく纏まっている。
自身の美に絶対の自信を持つ灯歌から見ても、及第点の美少女。だからこそ、同じ目に遭わせる価値がある。
前回のタイトルマッチからさらに鍛えてきたお腹、偶然勝てただけの灯歌との再戦に緊張するユミナの顔を見て、灯歌の口角が釣り上がる。これからこの女が無様に吐くところを、世界中に見せつけるのだ。
そして女王ユミナの紹介が終わり、スポットライトが一度消える。
『青コーナー! 25戦20勝3KO3敗2分け、WFBC世界フェザー級2位、猫四手 灯歌!』
名を呼ばれ、会場中の視線が集まるのを感じながら、灯歌はガウンを脱ぎ落とす。
灯歌のコスチュームは、黒を基調に金のラインが入ったトランクスとスポーツブラ。スポンサーであるスポーツウェア会社の最高級モデルを、灯歌カラーに仕上げた特注品だ。
伸びる手足は細く絞り込まれ、それでいて女性らしい丸みを残している。上下のウェアに挟まれたお腹は、灯歌の強い自我を表したようにはっきりと割れたシックスパック。白く美しい、研ぎ澄まされたナイフのような女体が、過不足ないシックなウェアに収められている。
ヘアトリートメントのCMにも出演する濡れ羽色のロングヘアは、高い位置で結ってポニーテールに。灯歌が動くたび、腰まで伸びる黒髪の束が流れるように追従し、会場のライトを反射してきらめく。引っかかり一つない、手入れの行き届いたしなやかな髪だ。
高く鼻の通った、日本人離れした顔立ちの灯歌が、これから挑む闘いに向けて表情を引き締める。その凛々しさと美しさに、会場に詰め掛けたモデルとしての灯歌のファンから黄色い声援が上がる。
灯歌は黒グローブを掲げてアピールする。一度は負けて追われたタイトルマッチのリングに、女主人が帰ってきたと。
整った顔立ち、豊かな黒髪、白くしなやかな肢体、黒地に金色をあしらった威圧的なウェア。灯歌の立ち姿は既に王座を奪還したかのように絵になった。事実、勝てばこの試合前の写真でフィットネスクラブのポスターを作る契約になっている。
灯歌はこのタイトルマッチにおいて、挑戦者らしく勝ちに専念するつもりなど毛頭なかった。
灯歌の写真撮影を兼ねた名乗りを、由実菜は苦々しく見ていた。
元チャンピオンならチャンピオンらしく、試合のときくらいは試合に集中するべきだ。灯歌と由実菜はあくまでボクシングで一番強いからこのリングに立っているのであって、美しさなんて関係ない。
灯歌は由実菜が憧れてきたチャンピオン像から、最も遠いボクサーだった。灯歌が相手だから、由実菜はより一層負けたくなかった。
もちろん、そんな由実菜の想いもボクシングの強さには関係ない。灯歌は誰よりも――おそらくは由実菜よりも——強いから、タイトルマッチのリングを撮影会にしてしまえる。灯歌にベルトを渡したくないなら、由実菜自身が灯歌を殴り倒してこのリングから追い出すしかない。
そんな意気込みで全身を満たして、由実菜はレフェリーの諸注意に臨んだ。灯歌は由実菜を恨んでいるだろうが、こっちだって灯歌のことが気に入らない。気持ちで負けているつもりはない、はずだった。
「へぇ……男も知らない小娘が、いいカオしてるじゃない」
「……ッ!」
だが、灯歌と間近で向き合い、その視線に全身を舐め回されると、由実菜の背中を悪寒が走った。
ほんの数秒前までモデルとしての撮影で澄まし顔をしていた灯歌が、カエルを前にしたヘビのように酷薄な目をしている。由実菜はこれから酷い目に遭うし、それが当然だから何の感慨も湧かない。そんな強烈な悪意を浴びて、高校生の由実菜が平気でいられるはずがなかった。
「ここ、とっても鍛えてきたのね。もっと鍛えておけば良かった、なんて思い残しはないわよね?」
灯歌は艶消しの黒いグローブで、由実菜のお腹をぽすぽすと叩く。話しているレフェリーが険しい顔をして睨むが、灯歌は涼しい顔だ。
「嬉しいわぁ。……二度と私の前に立つ気がなくなるように、完璧に壊してあげる」
「……立てなくなるのは、そっち。チャンピオンは私」
「みっともなく足掻いて偶然勝っただけの弱い女が、チャンピオンにふさわしいとでも思ってるの」
「に、二度勝てば偶然なんかじゃない」
痛いところを突かれて、由実菜の言葉が乱れる。由実菜の理想は確かな実力で業界を牽引し全ボクサーの実力を引き上げる、強いチャンピオンだ。実力で言うなら自分より灯歌の方がその理想に近いことは分かっている。
それでも、一度掴んだベルトを手放す気はない。いや、そのために必死に特訓してきたのだ。今の自分は灯歌より強いのだと、この初防衛戦で証明してみせる。
由実菜が気持ちを入れ直して睨み返す。だが灯歌はそんな視線もどこ吹く風、正確に一定のリズムで由実菜のお腹を触り続ける。念願叶って買ってきた宝石を眺めるねっとりとした視線のような接触を受け続けて、由実菜は次第に気味が悪くなってきた。
灯歌はそんな由実菜の様子に気付いたようで、それでもペースを変えずに淡々と触れ続ける。
ついにはレフェリーが諸注意を中断し、止めに入った。
「猫四手選手、挑発行為はやめなさい。試合前に相手選手に触れないように」
「はぁい」
「ユミナ選手も、挑発に応じないように」
「……はい」
灯歌のグローブと視線から解放されて、由実菜は大きく息を吐く。こんなところで気圧されている場合じゃない、気持ちを切り換えろ。
由実菜が正面から見つめると、視線はちょうど灯歌の唇にあたる。二人の身長差は10cm、その差はそのままリーチの差だ。灯歌がアウトボクシングに徹すれば、由実菜はパンチの届かない距離から殴られ続けることになる。由実菜が灯歌を殴り倒すには、まずチャンスを掴んで灯歌の懐に入り込まなければならない。
だがボクシングの戦略とは別に、由実菜はまたしても灯歌に圧倒されてしまう。
すらりと伸びた長身、手入れの行き届いた黒髪、自分でプロデュースしたシックなウェア、目立つほどではないが由実菜よりは大きく女性らしい胸の膨らみ。そんな灯歌の姿は全て、高校生の由実菜から見れば眩しいほどに大人びていた。
(ゆーくんも、私みたいなボクシングバカより、あれくらい大人の女性の方がいいのかな……)
視線を下ろすと、鍛え抜かれた腹筋が目につく。灯歌はもともと、モデルとしても絞り込まれた腹筋を売りにしていた。だが今日の灯歌の腹筋は、普段以上に厳つく仕上げられていた。由実菜との再戦を意識して鍛え直したのは明らかだ。
アウトボクサーである灯歌の脚を止めるのに、ボディを叩いてスタミナを削る戦術は有効だ。前回のタイトルマッチではそうして灯歌を仕留めることができたし、今回の防衛戦でも基本戦術はボディ狙いだ。
灯歌が対策してくるのも当然だ。一方の由実菜も、ブ厚くなった腹筋ごとブチ抜くつもりで練習してきた。灯歌の対策が由実菜の想定を上回るか、それとも由実菜の拳が灯歌の鍛錬を打ち砕くか。
激闘の予感に、音がするほどボクシンググローブを握り締める。
「……では、タイトルマッチにふさわしいファイトを期待します」
レフェリーの話が終わり、由実菜は灯歌の腹筋を見つめていた視線を上げた。
口元をニヤつかせた灯歌が、由実菜をじっと見ていた。灯歌は自分のグローブを、今度は自分の腹に当てて見せる。
「鍛えてきたお腹、そんなに見つめられたら照れちゃうわね」
「あっ……」
「私のスタミナが尽きるのが先か、貴女のお腹が潰れて恥ずかしい目に遭うのが先か……正々堂々、勝負しましょう?」
「え、ええ……」
由実菜は返事を絞り出すのがやっとだった。灯歌の顔はニヤついていても、目は笑っていない。そしてボディ狙い宣言。それだけで、先ほどの不気味な悪意を思い出してしまう。
由実菜が重い気持ちを抱えてコーナーへ戻ると、会長がマウスピースを用意して待っていた。
「だいぶやられたみたいだな」
「はい……すみません」
「なんの、こういうのをサポートするために俺がいるんだ。人生もボクシングも、猫四手なんかより俺の方がずっと先輩なんだからな」
「そ、そうだよね」
試合前から景気の悪い顔をしちゃってるな、という自覚はあった。だからこそ、会長がなんでもない態度で迎えてくれたことで気が楽になった。
「世界の頂点に立つようなヤツらってのは、ただ殴り合いが上手いだけじゃねえ。他人を蹴落として願いを掴むエゴの強さも世界レベルなんだ」
「は、はい」
「つまり、現チャンピオンの由実菜も負けちゃいねえはずだ。チャンピオンでいたいんだろ」
「はい!」
「よし、いい返事だ。あとは練習通りやれ。勝てるとは言えないが、負ける勝負でもないはずだ」
「あ、あはは……」
会長の率直な物言いは、それだけ力強い。由実菜は灯歌の気味悪さから抜け出し、体が軽くなるのを感じた。
灯歌がこの試合で何をするつもりであれ、由実菜は由実菜でチャンピオンらしく勝つという目的がある。あとは強い方が目的を叶える、それだけだ。
(でも、こういうときはゆーくんの顔が見たいな……)
普段は勇人が用意するマウスピースを会長に咥えさせてもらうと、試合開始のゴングが打ち鳴らされた。