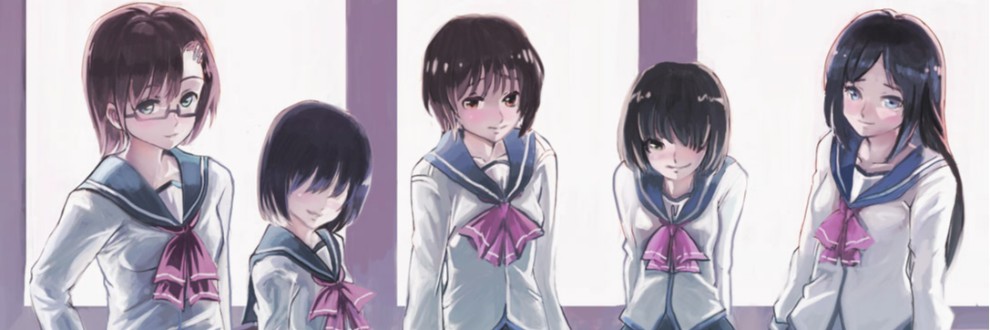【小説】多頭飼いの男、ペットを愛でる
旧:性的少数派の葛藤
支配欲・従属欲
辛島陶冶の人生行路は、全てゲーム理論により成り立っていた。
解に対して、陶冶は客観的な分析・行動を得意とする。ここで言う解を陶冶は「支配者」と規定しており、そこに至るまでの道筋を半ば遊び心で歩んでいた。
夏の残滓が漂う初秋にて、校舎から離れた男子バスケ部の部室より、今日も淫猥な濁音が吹奏する。広さ一坪という狭い室内には、男女の乱れた光景が窺えた。
「陶冶君……今日も……お、お願い……」
「おい。二人きりの時は『陶冶』じゃない。だろう?」
「あ、ご、ごめん、なさい……ご主人様ぁ……」
「ねえ、アレ言ってよ」
「う……は、はい。わ、私に罰を与えてください……ご主人様……」
「淫らな。が、抜けてるよ」
「み、みだ……淫らな私に、罰を与えて、下さい……」
「おお、場に染まってきたというか……棒読みじゃなくなってるな」
「あう~、は、恥ずかしかったよぉ~」
「可愛かったよ」
「撫でてっ!」
「なでなで」
「はわわぁ~❤」
制服姿の男女が二人、室内で主従関係に馳せている。男は辛島陶冶であり、女子生徒の名前を都木菜々美という。股を広げて不敵に座る陶冶に対して、菜々美は不衛生にも地べたに正座をする。相対関係を明確にする行為にて陶冶は然り、菜々美も性的快感を剥き出しにして、うっとりした表情を見せていた。
かしずく様子に陶冶が頭を撫でると、菜々美の陶酔感が更に増す。十分に高まった雰囲気に、陶冶は指で菜々美に脱衣を促した。
「う、うう……恥ずかしい、です……」
「もう三回目だよ。まだ恥ずかしいんだ?」
「う、そ、そんな、簡単に慣れる訳……ないじゃん……」
「敬語」
「あ、も、申し訳、ありません……」
「それじゃ、脱いで」
「はい……」
おもむろに立ち上がり、菜々美が制服に手を掛けるも羞恥が脱衣を阻もうとする。主従関係を結び、三度目となる性行為だが依然として緊張と赤面は隠せないらしい。菜々美は耳や首まで真っ赤に染めつつ、衣服の一枚一枚を静かに脱いでいた。
「うっ、うううっ、うっ……」
パサリ、パサリと、地べたに服が落ちる。全裸へと近づくに連れて菜々美の羞恥も増し、反対に脱衣の勢いが衰えていく。いつの間にか、瞳には小粒の涙が浮かんでいた。
しかし、決して不承不承ではない。菜々美は恥辱に染まりながらも、内心では高揚感に煽られており、とうに方々の性感帯をジワリと蕩けさせていた。
「はぁ……はぁ……んっ、はぁ……」
「大丈夫? 顔が真っ赤だけど」
「……むうっ」
「可愛いよ」
「ぁ、うっ、あっ……❤」
「最後の一枚。早く取って」
陶冶の言葉に菜々美が頷き、局部を覆っていた布を静かに剥いた。
一糸纏わぬ姿が晒され、いよいよ菜々美の顔面から湯気が湧き昇る。全身が燃えるような恥ずかしさに、両手で胸と局部を隠してしまうも、陶冶がそれを許すハズはない。
「隠しちゃダメだ。よく見せて」
「あう、ううう~、恥ずかしい、ですっ、あぁあ~っ!!」
陶冶が首を横に振り、菜々美の覆いがゆっくりと解かれていった。
淫蕩に燻された局部と、鎖骨から伸びた白く美しい湾曲が露わとなり、より一層に菜々美が赤みを帯びていく。陶冶の視線は局部の火照りを堪能すると、続いて程よい美乳へと注がれていった。
「相変わらず綺麗だな」
「あ、ありがとう、ございます……」
「乳首も新品同然にピンク色だ。美味しそうって言ったら、変態かな。けど、そそられるよ。早く、この手で揉んでみたい」
「ど、どうぞ、触って下さ、い……んっ……」
「そうしたいんだけど、もっと菜々美の恥ずかしがる姿が見たくなったから、それは後回しにしたいと思う。まずは乳首を使って、自分で慰めてみて」
「え、ええっ!?」
「早く」
「あ、う、は、はい……」
蒸気を発する茹蛸になりながら、菜々美が両手で左右の乳房に手を掛ける。陶冶の視線に、つい手で顔を隠したくなる衝動に駆られるが、グッと堪えてお椀型のDカップを掌で包み、母指球と手根にて按摩を始めた。
羞恥プレイ
「うう、触って下さいよ、ご主人様ぁ。自分でするなんて……しかも、ご主人様が見てる前で……そ、そんなの、は、恥ずかしすぎますよぉ……んっ、ふぅううっ……」
「菜々美の恥ずかしがる所が見たいんだよ。名案だろぉ!?」
「あ、う……ご主人様のドS……大好き……」
「うわ、菜々美……いまお前、顔から湯気が出ているぞ……」
「い、言わないでぇっ……うあぁあ、ぁっ……」
「おい、手で顔を隠すな。全て、俺に見せるんだ」
「うううっ、ううっ……はぁあっ、ぁっ……」
「汗が凄いな。まだ暑いからな。そこまで赤面してりゃ、身体も熱くなるか。湯気が出て……汗の臭いが俺にまで届いてくるぞ?」
「意地悪です、ご主人様……はぁっ、ぁあっ、あっ……」
いきなり始まる公開オナニーに戸惑うも、陶冶の命令は絶対であり、菜々美は気の毒な程に赤面しながら、恥辱の涙と嬌声を露骨に自慰へと馳せた。
高まる感度から、どうしても声を押し殺せない。自身の乳房を揉み、それを陶冶に視られる屈服感が菜々美を悶えさせている。陶冶もまた、駆け巡る快楽に苛まれて下半身をクネクネと揺らす菜々美の厭らしい様子に感度を促されていた。
「うっ、くっ、ふぅっ、んんっ……」
「はぁ、エロいな。顔真っ赤にケツを振って、涙を流してさ」
「み、視ないで、くださいよぉ……は、恥ずかしい、ですから……」
「とか言って、本当は感じてる顔を見られるのが好きなんだろう?」
「そ、そんな……う、うう、は、はい……」
「素直な菜々美、可愛いよ」
「あううう~っ、んっ、ふぁっ……」
「可愛い」という言葉に、菜々美が輪を掛けて顔を歪ませた。
陶冶は淫乱な菜々美を優雅な気分で眺めつつ、露骨にズボンを盛り上げている。不意に、菜々美の足元に投げ捨てられていたショーツに目が行く。陶冶の目線を察した菜々美は、思い出したように肩を竦め、ショーツを手に取った
「……そ、そういえば……今日はパンツを渡す日でしたね」
「ああ。この下着は貰っておくぞ?」
「良いですよ。どうぞ❤」
「どうも。白いパンツって好きだわ。なんか興奮する」
清潔感を見せる白い下着が陶冶の手へと渡る。陶冶のそれは、特に下着性愛という訳ではない。ペットの下着を貰う行動原理は、本当にただの「なんとなく」だった。
しかし、常に冷静沈着で毅然とした陶冶が実は下着の愛好家であり、夜な夜な一人で萌えているのかと想像を掻き立て、菜々美がうっかり噴き出してしまう。
「不躾な質問ですが……私のパンツでナニをするんですか?」
「え?」
「私のパンツが欲しいって言ってたけど、ナニに使うのかな、と」
「…………」
「ご主人様、もしかして私のパンツでオナニーするの?」
「…………」
「あはっ、なんか嬉しいかも……ってか、ちょっとウケる……」
「ぬう。なんて生意気なペットなんだ。そんな無駄口を叩けるなんて、自慰では羞恥が全く足りないみたいだな?」
「はうっ、ご、ごめんなさいっ!! これ以上はぁ……」
「乳房の自慰は終わり。俺の前に立って、割れ目を広げるんだ」
「ひえぇえ……」
「……心から従順になるまで、徹底的に羞恥責めをする必要がある」
「あう……とっくに従順ですよぉ……んっ、ふうっ……ほら、こんな目の前で、アソコを広げるなんて、彼氏にもしたことないんですから。ご主人様だけ、なのにぃ……❤」
菜々美が陶冶の両膝を蟹股で跨ぎ、自らの指で陰唇を左右に拡げる。
眼前で局部を見せる恥辱が菜々美を官能に焙っている。拡張だけで一切と触れられていないにも拘わらず、陰唇は陶冶の視線にジリジリ焼かれるように溶けて、断続的にヒクヒクと緊縮を乱発していた。
「そういえば、菜々美は昨日も彼氏と会っていたんだよな?」
「は、はい……エ、エッチもしました……で、でも、頭の中には……ず、ずっとご主人様が居ました。彼氏のこと、本当に好きだったのに、もう、ご主人様のことしか考えられなくなって……エッチの最中でも、ご主人様のこと、考えないと……感じられなくなってるん、です……ど、どうしてくれるんですかぁ、ご主人様ぁ……❤ 好きぃ、大好き、大好きです、ご主人様ぁ……❤」
「ほう? 彼氏が居るのに、俺に好きとか言って良いんだ?」
「あう……意地悪……」
心身の全てを捧げ、陶冶への忠誠を露わにする菜々美には、彼氏が居た。他の学校に通う同年代の男と交際しており、いまでも週末にはデートをする間柄である。それを承知の上で、こうして陶冶は主従の関係を築いていたのだ。
陶冶は口達者な上に女性からの人気も極めて高い。クラスメイトの友人として、元から仲の良かった二人が性関係に発展するのは難しくなかった。
「ちなみに、彼氏さんは俺との関係を知ってるのか?」
「し、知ってる訳、ないじゃないですか……」
「もし、俺との関係を全て打ち明けろ。って言ったら、どうする?」
「……ご、ご主人様がお望みなら……そうします……」
「そうか……まあ、冗談だ。俺も他の女と遊んでるしな。『均衡』を保つ為にも、なるべく彼氏と別れないでいてくれ」
「うう、分かりました……」
親交の傍らにて独学のマインドコントロールを用い、対象の女性を自身に依存させるなんて、陶冶にとっては造作もないのだ。気付けば、菜々美は陶冶を神格化して麻薬を帯びたように溺れていた。
なお、陶冶は敢えて「彼氏持ち」の女性をターゲットにしている。
どんな女も想いのままに依存させられる陶冶にとって、恋人の有無は問題にならないのだ。寧ろ、やがてハーレムを叶えたい陶冶にとって、恋人が居るという状況は相手をコントロールし易く、なにかと都合が良いのだった。
「ううう、ご主人様のも彼女、いるんです、よね……しかも、沢山の……ううっ、うっ、ううっ、ヤダ……ヤダァ……私が一番ご主人様を好きなのにぃ……ううううっ……ご主人様ぁ、好き、好き、好き……大好き、ですぅっ……誰よりも大好きですぅ……」
「彼女ではないよ。ただ、ちょっと懇意にしてるってだけだ。嫉妬を感じるなら、菜々美も複数の男と付き合えば良いさ」
「ヤダ、ヤダ、ヤダァ……うううっ、ひっく、うっ、意地悪……本当、意地悪です……私にはご主人様しかいないって……知ってる癖に……私はご主人様しか、す、好きになれないのぉ。ううっ……か、彼氏と別れるから……わ、私と付き合ってくださいぃ。ご主人様ぁ……一対一で、普通の恋愛、しましょうよぉ……だ、大好きなんです……」
「俺は寝取り好きなんだろうな。彼氏の居る菜々美を抱くってことに、異様な興奮を覚えるんだ。もし菜々美が彼氏と別れたりしたら、もう一気に冷めるかも。だから、別れないでくれ」
「そ、そんなぁ……」
「俺のことは、都合の良いセフレと思ってくれよ。本命の彼氏さんを愛しつつ、たまには気晴らしに俺を使って気持ち良くなる……なんてくらいにさぁ?」
「ヤダヤダヤダヤダヤダァ……ご主人様が他の女子と仲良くしてるの見ると、うっ、んんっ、ホントに死にたくなるのぉ……ひっく、うううっ、うわぁああぁああん!!」
束縛しないからこそ、相手の行動を制限させられる。即刻と彼氏を捨てて陶冶と付き合いたいのが菜々美の本音であるも、陶冶へと心酔する菜々美は命令に逆らえず、いまも無理やり彼氏と付き合わされていた。
陶冶が居るのに、他校に彼氏を持っている。だから、陶冶に菜々美以外の女性が居ても文句を言える筋合いがない。このジレンマに相当悩んでいたのだろう。菜々美は堰を切ったように、主人の目も憚らず、主人の前で泣き喚いてしまった。
「菜々美。いい加減に泣き止め」
「うううっ、うっ、うううぅっ、うっ……」
「はぁ……兎に角、抱いてやる。兎に角、それで落ち着け?」
「ふ、ぁっ……❤ う、うんっ……」
陶冶が立ち上がり、やれやれと泣きじゃくる菜々美を抱き締める。主人の温もりにて、菜々美の涙がカラッと引っ込む。「抱く」という言葉を聞き取ると、すぐさま身体を熱くさせた。
フォロワー以上限定無料
続き
無料