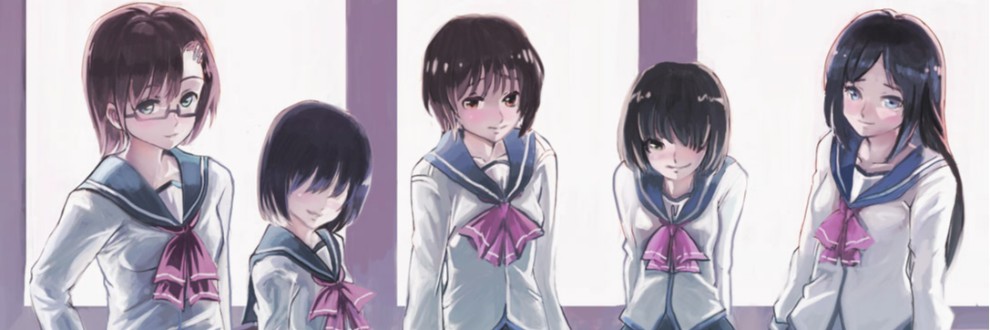【再録】人妻AVデビュー
『36歳です。仕事に興味があります』
物語は、SNSへと届いた一通のメールにより始まった。
明らかな捨て垢のオファーに訝しむも、結局と廣峯勇志は誠実な対応で相手を出迎える。話を聞けば、送信者は結構な年上であり、更には現役の人妻だという。人妻相手ではトラブルが多く、そもそも廣峯にはロリコンの嫌いがあり、年上に興味を持った経験すら無い。案件を断ろうと何度も考えた末の、松浦紗友里との出会いだった。
「あっ、もしもし。ユリです。い、いま到着しました……」
「峰岸です。もう隣に居ますよ」
「あっ……!? あはは……は、初めまして」
約束の日にて廣峯が初めて紗友里と出会う。既に廣峯は待ち合わせの場所にて待機しており、その声に驚いた紗友里が思わずスマホを落としそうになる。
「え、と……早速ホテルでしょうか……?」
「いきなりで良いんですか? 僕としては、打ち解ける為にも、まず軽く食事を考えていました。メールでも、そう伝えていたと思います」
「あっ、そうでしたっ……ごめんなさい」
互いに偽名で自己紹介を交わす。落ち着いて話す廣峯とは対照的に、紗友里は緊張を極めて何度も口を噛む。異性との会話にすら慣れていない印象だった。
自分より7つも年上の、なんとも慌てた様子に、廣峯が一先ずホッと息を吐く。経験の豊富な廣峯でも、初めて会う女性には警戒心や不安が拭えず、それだけに紗友里の初々しい態度は、程良いアイスブレイクとなった。
また、想定よりも整った紗友里の容姿に廣峯が感嘆する。予め紗友里の写真はメールで送られていたものの、写りが悪くてスカを喰らっていたのだ。
(やっぱり、実際に会わないと分からないもんだな……)
しかし、実際の紗友里は顔立ちがきめ細かく、着痩せしながらも存在感を放つ乳房の膨らみや、僅かに赤み掛かった美しい髪など、写真だけでは分かり得ない魅力を多く備えていた。
三十代にも拘わらず垢が抜けない雰囲気も、廣峯の扇情を大いに煽る。廣峯の視線が何度も上下に揺れ動き、その度に紗友里が気恥ずかしそうに萎縮していた。
「好きな物を注文して構いませんよ」
「え、えっと……ごめんなさい。結構です」
「要りませんか?」
「正直に申しますと、不安ばかりで何も喉に通りません……」
「そうですか。大丈夫ですよ。じゃあ、自分だけ注文させて頂きますね」
「はい」
一行は、駅にあるカフェへと足を運んでいた。
これから二人は、ホテルで身体を重ねなければならない。明らかに性的経験の乏しい紗友里は、緊張と不安で食欲が湧かず、赤面を隠すように俯いてばかりだ。
空腹の廣峯は、そんな紗友里に構わず次々に軽食を頼んでいく。一息を吐くと、廣峯は本題を切り出した。
「ギャラは10万円です。宜しいですか?」
「……はい」
「こちら契約書と誓約書になります。よく確認した後に、サインを下さい」
「分かりました」
「大丈夫ですか? 顔が真っ赤ですけど……」
「うああ!? ご、ごめんなさいっ!!」
「い、いや、謝らなくて全然良いですけど」
「うう……」
「あの、一つ聞いても良いでしょうか?」
「な、なんでしょうか!?」
「どうしてユリさんはAVに出演する気になったんですか? 失礼ですが、全然そういうタイプには見えません。ユリさんのような淑やかな女性からオファーが来た時はビックリしましたよ」
「…………」
水耕栽培に携わる廣峯勇志は、副業としてAV制作を営んでいた。
AVと言ってもメーカーに勤める訳では無く、個人によるインディーズである。素人との行為を撮影しては、それにモザイク等の編集を行い、サイトで販売する。大体の相手は、素人と言えどアダルトを生業とする者であり、こうした仕事にも抵抗が無い女性ばかりだ。
しかし、明らかに紗友里は違う。異性への耐性は無く、そもそもが人妻である。話から察するに、旦那には確実に秘密にしての、今日という仕事だった。
アダルトに初心者な上に、旦那には内緒の人妻と来れば、理由は一つしかない。察しは付くものの、廣峯は紗友里の言葉を待った。
「実は、借金があるんです。夫には絶対に知られたくなくて……」
「そうでしたか、すみません。話さなくて大丈夫ですよ」
「ありがとうございます」
紗友里の指先は震えていた。
感情を必死に押し殺すように、声も上擦っている。業界とは無縁の人妻が急にアダルト産業へと首を突っ込んだのだ。借金で精神的に追い詰められた末ならば、紗友里の震えも必然だった。
借金か脅迫か、その辺りを予想していた廣峯に驚きはない。優しい言葉と共に、紗友里の手を握って慰める。この仕事をしていれば、訳アリな女性との出会いも多い。いまにも不安で事切れそうな紗友里に、これでもかと廣峯が慎重に接する。物柔らかい廣峯に、紗友里は初めて笑顔を見せた。
「優しいんですね」
「普通ですよ。どんな僕を想像していたんですか……」
「アダルト関係の仕事には、もっと物騒なイメージがありました」
「なのに、よく来てくれましたね」
「今日の約束を取り付けた時は何度も後悔しました。今朝も後悔で泣いちゃって。だから、峰岸さんが優しい人で本当に良かったです。本当に、本当に……」
紗友里の借金は、完全に私的な理由による破産だった。
専業主婦として暮らす傍らに、趣味の買い物が高じた結果である。その内気な性格から、旦那や家族にも破産を打ち明けられず、一人でカードの請求に怯える日々を送っていた。
そして廣峯がSNSで発信した「高額バイト」のハッシュタグに引っ掛かった次第である。初対面の男と性行為を行い、マスクの着用が可能とは言え、更には撮影もされる不安に、紗友里のストレスは限界に達していた。
そんな現況での温もりは有難く、紗友里の瞼には涙を浮かべていた。
「それでは、そろそろ行きましょうか」
「は、はい。ホテル……ですよね?」
「勿論です」
「……ッ!!」
最後のパンケーキを口に放り込んだ廣峯が言う。時刻は、間もなく夕方に差し掛かっている。旦那にはママ友との飲み会だと伝えており、夜間は丸々と廣峯に費やす予定である。紗友里にとっては仕事でも、旦那から見れば不倫でしかない。旦那ではない異性と肩を並べてホテルへと向かう紗友里は、チクチクと罪悪感を感じながら、不安と緊張で心臓を高鳴らせていた。
フォロワー以上限定無料
無料版の最後まで続きます。
無料