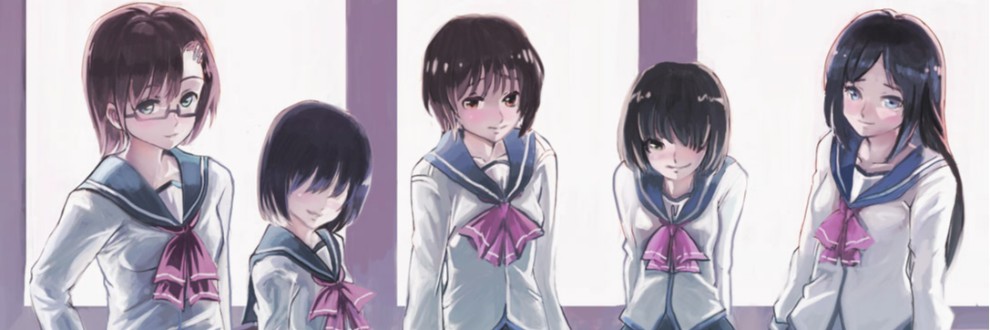とある女子校の体育館にて。残暑も乗り越え、ようやく過ごしやすい季節となった昨今も、体育館だけは女子たちの熱気により、蒸し暑いサウナと化していた。
「はぁ……はぁ……はぁ……はぁ……」
「ん、んはぁあぁっ! はぅぅぅっ、硬くて大きいのぉぉ……私がっ、いっぱい舐めて気持ちよくしてあげますねっ!」
「先生のココっ、すっごく硬くなっててっ……触ってるだけで……下半身が熱くっ、こ、興奮しちゃいますっ!」
「んちゅっ、ちゅっ……全身舐めて綺麗にしてあげますね❤ 私の匂い……全身に塗りつけちゃうから……」
「ちょっとあなた、図々しいんじゃない? 一人で雄世さまの唇を占領しないでよっ! どきなよ、次は私の番でしょう?」
「はぁ、はぁっ……胸っ、感じちゃいます……雄世先生の腕、ごつごつしてるからっ、こうやって挟むだけでも……なんだか気持ちよくなってきます……」
熱気に加えて、女子たちの甲高くて淫猥な黄色い声と、いやらしい粘液音が体育館全体に響いていた。
酒池肉林というより、四面楚歌と表現するべきだろう。館内は女学生で隈なく犇めいており、その中心に立つ一人の男を取り囲んでは、女子たちが我先にと奪い合いを繰り広げているのだ。
「先生っ、ちゃんと耳も気持ち良くしてあげるね❤」
「私は、先生の足の指を頂きます! あむっ、んぁっ、ちゅぷっ、んちゅぅぅ……うぅう、指先もすっごく美味しいよぉ……❤」
「れろっ、んはっ、むちゅっ、にちゃっ❤ 脇の下、めっちゃいい匂いしてるよぉ~っ! はむっ、れろっ、れろっ……」
「首筋にもキスしてあげるっ! ちゅっ……んはぁ……」
「そうそう、先生って耳が弱いんだよね~。左側もいっぱい舐めてあげるから、感じてる顔、見せてね❤ んちゅっ、ちゅううぅぅ……」
「じゃあ、私は唇っ。キスしよ、先生っ……んんっ、ぴちゃっ、んちゅっ、ん……っ、んぁ~、美味しくて堪らないよぉ❤」
男の全身に女子の舌が這う。身体中から伝わる舌の弾力に、男は早くも呻き声を上げて腰を引き攣らせる。やがて押し寄せる官能を塞き止められなくなると、男は背筋を弓なりに撓らせてアクメへと達した。
「きゃぁあ~~っ! 先生のセーシっ、私のぉ~~っ!」
「相変わらず濃くて美味しいわぁっ♪ もう三発目なのにさぁ~。まだまだデキるよね? 四発目はどうかなぁ?」
沸き起こる歓喜の悲鳴。弧を描きながら飛び散る精液を、必死の形相をした女たちが争うように奪い合う。そして、指に付着した精液を舐めとった女子は、みな次々に恍惚の状態に陥っていった。
「臭いだけでも変な気分になっちゃう……今度は嗅ぐだけじゃなくて……飲みたいですっ❤」
「次は私たちだよ。いつまでも浸ってないで早くどいてよ! 」
「やった♪ やっと私たちの番だっ!」
三度目の射精とのことだが、絶頂後の余韻は無いようで、またすぐにペニスが女子たちの手で埋まってしまう。一射精ごとに相手を交代する流れであり、先ほど愛撫していた軍団が引っ込むと、今度は別の女子グループが男へと群がっていった。
この絶対的なハーレムを愉しむ男は名前を雄世といい、何人かが口にしてるように、この者は女子校で教鞭を執る歴とした教師であった。しかし、最早もう雄世の教職員としてのまともな姿など見ることは叶わないだろう。ある日突然に女を意のままに操れる「洗脳」の魔法を手に入れてからは、ずっとこの調子なのだから。
「先生のチ●コ、全然萎えないね。今日は何発出せるかなぁ?」
「まあ、二十発は出したいな。ここの女はみんな可愛いからな。出来るだけ多く相手してやりたいよ」
「この女たらしっ、ホントに教師かよ~! でも好きっ❤」
洗脳により、雄世は女子校に通う全ての女子を好いように操って愉しんでいた。女たちは、雄世という存在に恋焦がれ、欲情と愛情を示すように強いられており、今日も朝から早々に全校生徒が体育館へ集結して雄世に寄り添っていた。
「雄世先生…………いいなぁ、私も、ご奉仕したい……」
ふと、誰かがか細い声で雄世の名を呟く。誰に発したワケでもない、それは、遠くで行為を見つめていた一人の女子による溜息交じりの独り言だった。
その女子こと由梨乃も、当然ながら洗脳の犠牲者であり、雄世に身を捧げて一生を尽くしたいと強○的に切望されている。しかし、洗脳が始まって早一か月余りが経過するも、悲しいことに由梨乃は未だ一度だって雄世に触れたことがなかった。
その背景には、揺るぎなきスクール・カーストが存在していた。雄世を囲む女の巨大な円陣を見れば一目瞭然というべきか、円の内側へと向かうに連れ、女子のランクが明らかに高くなっている。それは即ち、雄世は日頃から容姿や身分、アピールに優れた女子ばかりを相手をしていると謂えた。
相対的に、外径側は容姿の悪い、或いは自己主張が苦手の内気な女子で固められている。これは雄世が意図したつもりもなく、洗脳を全校生徒にかけた結果、必然的にそうなってしまったのだ。
由梨乃は、分厚い円陣の遥か外側に位置していた。地味で内気な上に友人の一人もいない点が、彼女を最底辺のカーストに追いやっているのだ。
「出来るだけ多くを相手にしたい」と宣った雄世だが、多く見積もっても一日の射精は二十五発が限度であり、それでは中層の女子にすら届きはしない。最下層に属する由梨乃たちは、雄世の視界に入ることも儘ならず、ただ女という壁の奥で自慰に耽るのがせいぜいだった。
「んっ…………はっ、ぁっ……」
洗脳で絶え間なく溢れる雄世への情欲に、由梨乃が甘い吐息を漏らしながらスカートを捲って下着越しに陰核を弄る。
脳は完全に侵されており、人目も憚らず濡れた下着を露出させ快楽に溺れていた。
(先生……ぁっ、ふぁっ……雄世さまぁ……んぁっ、はぁんっ❤ 愛してますっ……でも、私だけ愛するなんて不公平です……)
時おりチラチラと垣間見える雄世とカースト上位の女子たちの乱交を肴に、由梨乃が獣のように猛然と官能を貪る。まだ知らぬ雄世のペニスや肌の感触を想像しながら、どうして私はあの場にいないのかと、歯痒い気持ちになりつつクリトリスを指で擦り続けた。
(はぁっ、んぁあっ……雄世さまっ、あんなに大勢の女子に身体中を舐められて、本当に気持ちよさそうっ。私もっ、舐めたい……雄世さまのおちん●んっ……ううん、何処でも良いから……)
どうしても、女子には雄世が絶世の王子様に見えて仕方がないらしい。姿を見れば子宮が疼き、声を聞けば愛液がドバドバと溢れ出してしまう。もし、そんな絶対的な相手に肉壺を貫かれたら――。なんて妄想してしまえば、それだけで女は恍惚状態に嵌ってしまうのだった。
(はぁっ、はぁっ、はぁっ、ゅ、雄世さまのおち●ぽっ……❤)
内気という殻を破り、いますぐにでも女の波を掻き分けて彼の元に行きたい。由梨乃だけでなく、その周りにいる女子たちも全く同じ気持ちだった。しかし、派手な女子が前面にいる限り、そういうわけにもいかない。
そんなことをすればどうなるのか。下層の者にとって、位の高い女子たちの恨みを買うことほど恐ろしいものはないのだ。例え髄まで洗脳されていようとも、それは揺るぎない心情だった。
「雄世ちゃん……んちゅっ、ちゅるっ、ぬちゅ……んはぁ、ぁっ、あああっ、唾液っ、雄世ちゃんの唾、美味しいよぉ……❤」
円の中心――。立ち竦む由梨乃を尻目に、如何にもギャルという派手な女子が雄世にディープキスをする。唾液を交換したようで、唾を飲み込んだ女子は、それだけでオーガズムを迎えてしまった。
スカートからは、氾濫した愛液が光沢を放ちながら床へと滴っている。
「キスだけでイッちゃうなんて、可愛い奴だな、はは」
「雄世ちゃんとのキスでイカない子なんていないでしょぉ~❤ ねぇ、もっとしようよっ! んっ、ちゅるっ、んふっ、んっ」
「ちょっと、キスは一人一回だけ! 次は私なんだから、早くどいてよ!」
「ぁぅ……残念。次は夕方くらいかな? またね、雄世ちゃん」
「やっと私の番ね! ぁ~むっ、んっ、ちゅぅっ、ちゅっ❤」
キス待ちの大行列――。代わる代わる女子が自分に唇を捧げてくれるシチュエーションを、雄世は特に気に入っていた。
顔を真っ赤にしながら、もじもじと身を捩ってキスを待つ女の集団は、一生観ていても飽きがこない。
そうファシズムに酔うと、雄世は射精感を急激に高めていった。ふやけた唇がまた新しい女の口で塞がれると、雄世は苦悶の表情を作り、臀部と膝を震わせた。
(ぁああ……良いなぁ、良いなぁ。雄世さまとキス……雄世さま、唇がふやけてピカピカになってる……私も一度くらいキスしたいよう。好き……大好きっ……)
快楽に溺れる雄世の姿に、由梨乃も胸を熱くする。ジンと下半身が痺れており、僅かに触れると陰核が弾けて肉壺から女汁が滴った。
「わっ、雄世先生のおち●ぽ、また大きくなった❤ ちゅるっ、んっ、ちゅくっ、ちゅるっ……感じてる顔、すごく可愛いっ❤」
「ぁ~ん、次こそ私にも精液くださいねぇっ! んっ、ちゅるるっ、ぬちゅ、ちゅっ……んはぁ、お汁、美味しいよぉ❤」
「雄世さまは、尿道をこうやって舌でくすぐられるのに弱いんですよね。ちゅっ。ほら、こんなに腰が引き攣ってる❤ このまま出して、私の顔面に万遍なく振りかけて下さいね❤」
トリプルフェラをする三人が亀頭の様子から射精を予感する。早くも本日四度目の射精となるが、雄世のペニスに衰えは見えない。
体育館の中央で棒立ちする雄世に数百人の女子生徒が群がり、キスをエンドレスに繰り返されつつ、陰茎には三本の舌が伸び、両方の乳首も女子たちに抑えられ、挙句には耳や肛門にも舌鉾が突っ込まれているのだから、否応なしに絶倫状態となるのも無理のない話だが。
「うっ、くあぁっ、キスに、トリプルフェラに、耳舐め……これは流石にっ、ヤバっ、全身に舌が這って、も、もう、出そうだ」
苦悶する雄世。そんな様子に連ねて、オナニーに惚けていた由梨乃も性感を増長させる。雄世が達しそうになると、決まって連動するように周りの女子たちも高揚していくのだ。
気付けば、由梨乃の周りにいる女子たちも夢中になって自慰に浸り、涙目で淫靡な喘ぎ声を漏らしている。一様にスカートを広げて股間を弄りながら、雄世の名を呟き陶然としていた。
「はぅっ、あぁっ、ひゃっ、ゆ、雄世せんせぇっ……好き、ですっ。はぁっ、ぁっ、私のことも、ぁっ、み、見てください❤」
「それは、ぁっ、な、ないでしょ……日陰者の私たち、じゃあ……でも、一回くらい雄世さまにっ、んっ……触られたいっ……」
「ぅうう、悔しい、ですっ、こ、こうして……み、惨めにオナニーしてて、そ、それで気持ち良くなってる自分にも……んぁあっ、は、腹が立ちますっ、うぁっ、ふぁぁあんっ❤」
由梨乃の付近で、手淫に励む下層の女子たちが口々に想いを吐露する。激しく共感を覚える由梨乃だが、その社交性から口を挟んだりはしない。敢えて言うなら、由梨乃は下層ランクの更に下位、地の底を這う、いわゆるド底辺だった。
それは、由梨乃が最も理解している。だから、嬌声も心の中に留めているのだ。
「見て……雄世さまのお顔……イッちゃうみたい❤ ぁあん、もう可愛いっ。もっと近くで見たいよぉ……ぁああんっ❤」
「ふぁぁあっ、先生っ、先生っ、先生っ!」
と、そうこうしている間にも、場が佳境へと突入する。
雄世が絶頂間近に迫ったことを受けて、みんなの動きも幕引きへと向かう。そして雄世が断末魔のような呻き声を上げると、反り上がった陰茎から白濁液が大きな弧を描いて迸り、近くの女子たちへと降り注がれた。
「うぁっ、あっ、うぁあああああああっ!」
ビュルルルルッ、ビュッ……ドクッ、ドクッ、ドクッ……
「きゃぁあああぁああああ~~~~~~~っ❤」
またも女子の悲鳴が轟く。撒き散らされた精液に触れた者たちが、すべからくエクスタシーに悶えて感情を爆発させていた。
恒例の奪い合いが始まるが、後列で見ている由梨乃たちは相変わらず指を咥えたまま。精液の臭いすら嗅いだこともない彼女たちは、消化不良と言わざるを得ない心境のままオーガズムに達した。
「はぁっ、はぁっ、はぁっ……雄世せんせぇ……っ❤」
「オナニーは気持ちいいけど、私たちも精液、欲しいね……どんな味がするんだろ……ぅぅぅ、想像したらまた疼いてきちゃった……」
「みんな浴びるだけでイッちゃってるし、ほんと気になるよね」
上位の女子たちが余韻で気持ちが浮ついている中、まるで賢者タイムのように下層女子たちが肩を落としている。これもお馴染みの光景と言えるだろう。
一射精毎に交代というルールに則り、余韻を終えた女子たちが恍惚とした目つきで奥へと引っ込んでいく。すると間もなく、また別の女子グループが雄世へと集まっていった。
五組目のグループとなるが、まだまだ上層の女子たちである。雄世が一日に百発は放てる超人でなければ、底辺層の由梨乃たちに届くことはないだろう。今日も相手してもらうのは無理だろうなと、由梨乃たちは落ち込んだ。
美人揃いの本校において、雄世のような女たらしがわざわざ質の低い女子を相手にするハズがない。
と、深く理解する下層女子たちは、いつでも雄世へと触れられる上位の女子を妬み、不満を募らせていた。口にはしないが、由梨乃も全くの同意見を抱いている。
可能なら、雄世の精液を一飲みしてみたい。亀頭の味を確かめ、彼の喉に私の唾液をこれでもかというくらい注ぎ込んでもやりたい。
そんな風に思っていた。
だが、ボンクラな自分に、そんな機会は一生訪れまい。自分という存在が如何なるものか重々に理解している私だから分かる。でも、私はただ、遠くから彼を眺めるだけでも満足だから構わないのだ。
……本当に、そう思っていた。