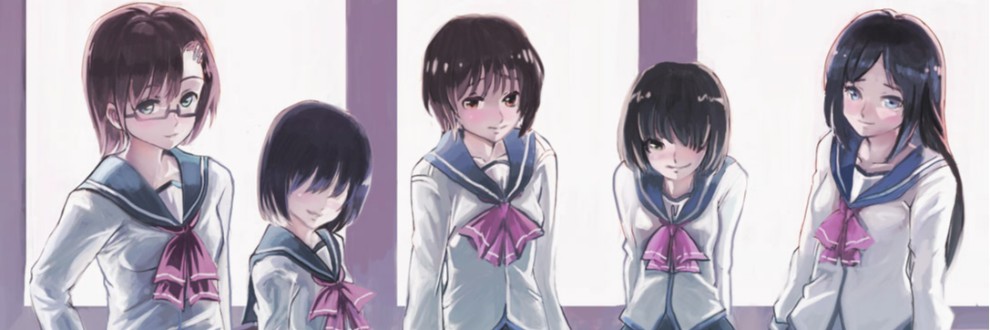【小説】彼シェア!!-男の少ない島では彼氏の共有も当たり前!!-第一話
概要
引っ越した先は、女性率の高い離島だった。
島の名前を鉢割島といい、300人を下回る人口だが、
その内の8割が女性だと言われている。
転入先の学校も、自分以外は全員が女子という。
海陸を興味津々に見つめる、7人のクラスメイト。
教鞭を執りながら、熱い視線を送り続ける女教師。
とんだ出来事にて女教師と肉体関係を結んでから、
海陸を巡る女子達の争奪戦が始まるのだった。
女教師の誘惑-第一話(前半)
「おはよ、海陸くん♪」
「あ、お、おはよう」
「おはよー、海陸くん!」
「おはよう……」
「か、海陸くん。お、おはよっ!」
「う、うん」
「海陸くん、一緒に学校行こ!」
「……うん」
「海陸くん、もう学校には慣れた?」
「えっと、まあ……」
「ってか、海陸くん遠すぎ。もっと近くで話そうよ」
「う……」
「そんなに緊張しなくても良いのにぃ!」
「朱里、嫌われてるんじゃない?」
「そ、そんなことないし! ……だよね?」
「…………うん」
女性を苦手とする海陸にとって、鉢割島での生活は息苦しかった。
鉢割島とは、人口が三百人程度の小さな離島である。閑散とした小島だが、学校や役所、警察といった公共施設は一通り揃っているので、生活に不便を感じる者は少ない。しかし、鉢割島には他に類を見ない珍しい特質があり、そのせいで海陸は酷く悩ましい生活を強いられていた。
「ねぇ、海陸くん」
「な、なに?」
「海陸くんって、女嫌い?」
「そんなことはないけど……」
「ホントにぃ? いっつも、ぶっきらぼうだけど」
「それは、ごめん」
「じゃあ、もっと色々お話しよーよ」
「言ったでしょ。女子が……苦手なんだ」
「あははっ、可愛い~っ!」
「でも、早く慣れないと大変だよ?」
「そうそう。鉢割島は女ばっかりだからね」
「学校じゃ、海陸くん以外、全員女子だし」
「わ、わかってるよ……」
鉢割島には、人口の殆どが女性という特徴があった。
総人口の内、男性は五十人もおらず、夷塚海陸の通う学校も、自分以外は男子生徒がいない現状である。異性に不慣れな海陸は、転校から一週間にして女子ばかりの環境に参っていた。
*鉢割分校
島で唯一の学校だが、それでも全校生徒数は八人しかいない。
内訳、女子が七人で、男子は海陸が一人だった。
「それじゃ、授業を始めるわよ~」
「先生、今日も海陸くんに教わりたいですっ!」
「ダメ、昨日のは特例だから。ほら、みんなプリントやって~」
「え~」
なお、鉢割島における最大の苦痛は授業にある。
生徒数が八人だけの学校では、教員も一人しか在勤していない。
それ故に教室は一つしか使われておらず、全ての授業は学年も関係なしに一緒くたで行われている。
「ね、海陸くん。こっそり、教えてよ♪」
「え、でも……」
「良いじゃん、良いじゃん♪」
「あー、朱里ズルい! 私にも教えてよ~!」
「コラ~、ダメだってば!」
校舎は、こじんまりしたプレハブで造られている。
狭い教室に、男子は自分だけ。
思春期の只中な海陸が居心地の悪さを感じるのも仕方なかった。
「良いでしょ、先生♪ 分からないとこがあるんですー。でも、いま先生は菜津ちゃん達で手一杯みたいだし?」
「それを言われると辛いわね。……分かったわよ。夷塚くん、今日も森江さんと紅音さんの面倒をお願いして良いかしら?」
海陸に、女教師の仲上奈美が仰ぐ。
生徒の年齢がバラバラな以上、鉢割校で一般の授業は行えない。
個別に奈美が対応している訳だが、全員を一人で捌くなんて容易ならざる話である。よって、鉢割校では教師だけでなく生徒も当意即妙に教鞭を執ることがあった。
「わ、分かりました……」
「やったぁ~! よろしくね、海陸くん♪」
「じゃ、私も良いよね?」
「う、うん」
「えへへ、嬉しい! 後でちゃんとお礼するね❤」
「え~? 朱里もぉ?」
「私もお喋り……いや、教わりたいし! 翠、椅子持ってこよ!」
「オッケー」
都会の進学校から現れた海陸は、もはや鉢割校における二人目の教師のような扱いだった。転校初日から、海陸は毎日と鉢割校の生徒に勉強を教えていた。
「海陸くん、よろしく~」
「翠のついでに私までありがと♪ 数学、全然ダメでさぁ~」
翠、朱里が自分の席から椅子を運んでくると、海陸を挟み込むよう両脇にピタリと置いて座った。肩や太腿が触れ、海陸に緊張が走る。
「ね、ねぇ、近くない? これじゃあ、肩がぶつかっちゃうよ……」
「そう? 私は気にしないよ?」
「私も気にならないかな。離れてちゃプリントが見えないし」
「…………」
海陸のプリントを覗き込もうと、朱里と翠が左右から身を乗り出す。
わざとらしく海陸に体重を預け、肩から密着してくる。
女子の確かな重みと馥郁に包まれて脳をクラクラさせるが、海陸の焦燥感など露知らず、二人は顔を近づけて耳元に温かい吐息を吹きかけるように囁いた。
「海陸くん、プリント進めるの早すぎだよぉ」
「ねぇねぇ、ここの答え、なんでそうなるのぉ?」
「ふ、二人とも……顔が近い。もっと、離れて……お願い……」
「え~? 別に良いじゃん。離れてたら、やりにくいよ」
「両手に花の状態で恥ずかしいの? 意識してくれるのは嬉しいけど、そろそろ慣れてよ。いまは授業中なんだしさぁ♪」
「そうそう、私達は真剣に勉強してるんだよぉ? ふふふふふっ❤」
「ううっ……」
二人は真剣と言うが、実際は海陸の慌てる姿が見たくて詰め寄ってるだけである。故意に寄り添い、海陸の腕に胸を押し付けてくる。予想通り赤面する海陸に、二人はクスクスと笑った。
「…………」
傍から見れば、イチャイチャしているようにしか見えない。
女教師の奈美は、そんな光景を横目で窺いながら溜め息を吐いた。
授業中に騒ぐ二人に呆れた訳ではない。
人目も憚らず海陸に迫れる二人が羨ましかったのだ。
(良いわねぇ、翠ちゃんも朱里ちゃんも。あんなにグイグイと積極的になれて。ふふふ、海陸くんってば、本当に女性に慣れてないのねぇ。二人に挟まれて顔が真っ赤になってるわ。いっつも迫られてるクセに、未だに慌てふためいちゃって……ああぁあ~、可愛すぎるわぁっ!)
奈美は、一回り年下の海陸に心酔していた。
教師として島に呼ばれて五年余り。男性の居ない環境で身を焦がし続けていた奈美にとって、海陸は漸く見つけたハイエンドなのだ。
転入前の面接にて、一目惚れだった。
その甘い容姿や純情は、他の島民と比べるまでもない。
歳の差など気にならないくらい、海陸に夢中になってしまっていた。
名前を呼ばれるだけで身体が火照ったり、無意識にチラチラと視線を送ったりと、まるで学生に戻った気分である。
だが、奈美は教師であり、間違っても学生ではない。
教師と生徒に隔たる壁は明らかであり、どうすることも出来ない奈美は、遠慮なく色目を使える翠と朱里に、ずっと羨望の小波を立たせていた。
……今日までは。
「勉強、教えてくれてありがとね。これあお礼だよ、チュッ」
「私も助かったよ。私からもお礼ね、チュゥッ❤」
「あ、あううう……」
不意に、教室が黄色に沸いた。
やり取りを見ていた女子達の歓声である。
手ほどきの対価として、翠と朱里が海陸の頬にキスをしたのだ。
左右の頬に二人の唇が触れ、海陸が飽きもせず血液を沸騰させる。耳まで真っ赤に染めており、いまにも湯気が出そうな様子だ。
行為を遠目から覗いていたクラスの女子が各々に悋気の声を漏らす。
『あぁ~、良いなぁ……』
『朱里ちゃん、海陸くんと毎日キスしてて、羨ましい……』
『私もしたいなぁ~』
『私も積極的に迫りたいけど……ううう』
やはり、たった一人の男子ということで、海陸との熱い親交を求める女子は多い。しかし、殆どは島民らしく異性に慣れておらず、翠や朱里のような積極的なアプローチは掛けられずにいた。
(このままじゃ、二人に海陸くんを取られちゃう。そんなの嫌だわ。絶対に嫌。そうはさせないわ。もう、なりふり構っていられない!)
輪の中で、島外出身の奈美だけが対抗意識を燃やす。
――私は遠くから見守っているだけで良い。片思いだけで幸せだ。
始めこそ静観を決めていた奈美だが、それも懐かしいだけの記憶である。
募る想いは日に日に肥大しており、いまや頭の中は海陸との男女関係についてばかり。道徳のメッキなんて欠片もなかった。
「ねぇ~、海陸くんからもキスしてよ❤ ちゅっ、ちゅっ、ちゅっ」
「そっちからしてくれるまで、ずっとキスし続けるよ? ちゅっ、ちゅっ」
「う、うああっ、や、やめてよっ……」
「コホン! 三人とも、授業中よ。そこまでにして」
「あ、先生」
「あはは、ごめんなさい♪」
未だに頬へのキスを続ける翠と朱里に、奈美が教師として割って入る。
指を咥えて見てるだけではない。二人を引き剥がして海陸を救い出すと、奈美は出来るだけ平静を装いながら要件を口にした。
「……夷塚くん。昼休みに職員室に来てもらって良いかしら」
「は、はい。なんでしょう?」
「えーっと……あー、鉢割島での進路先を纏めた資料とか渡すわ」
「あ、分かりました」
「ええ。それじゃあ、昼休みに」
「はい」
「…………」
話を終えて背を向けると、奈美がホッと一息吐く。奈美には、前々から企てていた腹積もりがあった。海陸と『仲良くなる』為の計画である。
その為には、まず二人きりにならなければならない。奈美は、教師の職権を利用して昼休みに海陸を誘い出すのだった。
それが、何故こんなことになってしまったのか。
(あああああっ、なんで海陸くんの顔が目の前にっ? あぁああ、顔が近いわぁっ。ほんの少し顎を傾けるだけで唇が重なっちゃう! しても良いのかしら? ダメよ、未成年とのエッチは犯罪……あぁあぁあ、止まらないわああぁっ! んっ、ちゅっ、んんんっ……❤)
昼休みの職員室にて、教師と生徒の接吻が披露されていた。
勿論、海陸と奈美の二人である。
椅子に座る海陸へと奈美が圧し掛かり、怒涛の如く唇を奪っていた。
「んっ、ちゅっ、ちゅくっ、んっ……」
箍が外れれば、もう抑えられない。
唇を押し付けたかと思えば、その直後には舌が伸びて海陸の口内を凌○していく。海陸の舌先を搦め取り、無理やり表へと引っ張り出して剣戟を始めていた。
(んっ、はあぁあぁあああんっ! 海陸くんの唇っ、柔らかすぎっ! あああ、穢れの無い未成熟な唇を、私が吸い尽くしているっ! もう、何も言うことない。このまま教員をクビにされても構わない。もっと、もっともっともっともっと味わいたいいぃいっ❤)
口付けを交わしただけで、奈美はオーガズムに陥っていた。
唾液の交換に至ると、もう絶頂の連続である。一目惚れから一週間余り、ずっと思い煩っていた相手と交われたのだから、感慨無量も止む無しだろう。
氾濫する快感物質が脳内を侵しまくっている。生き残った微かな理性が自制を試みるも、一度決壊したダムでは塞き止めようがない。欲望という津波が奈美を襲い、そのまま海陸を犯していった。
(どうして、こんなことになってしまったのだろう……)
朦朧とする思考の中で、二人が同時にそんなことを考える。
奈美も、元々は此処まで迫るつもりなんてなかった。
転校から一週間という時期を逆手に、教師として海陸を職員室に呼び出したのが切っ掛けである。鉢割島での進路先や、学校生活について親身に話を聞きながら、どんどん仲を深めていこうと計画していたのだが、ほんの細やかな味付けに「媚薬」を用意したのが明らかな間違いだった。
教師ではなく、異性として意識してもらいたい。
そう至り、差し出した麦茶に媚薬を混入させたのだ。
『媚薬入り麦茶を飲めば、忽ち淫らな気分になり、海陸くんが私を性的に意識するようになるかもしれない。そうなったら、胸元を露出しておっぱいを強調したり、ミニのタイトスカートで誘惑なんかしちゃおう!』
下策も下策、教師が考えたとは思えない作戦である。
だが、行為に至るまでの煩わしい過程をすっ飛ばすには有効な裏技かもしれない。奈美が使用した媚薬は海外製の危険ドラッグであり、その効果は実際の通り、服用者の理性を破壊して本能を剥き出しにする程のパワーがある。道徳には反するが、これを切っ掛けに、想い人の気が引ける可能性は十分にあった。
しかし、それは海陸が服用した場合に限る。
あろうことか、極度の緊張により、奈美は海陸に用意したハズの麦茶を、自分で飲んでしまうという信じられない失態を○すのだった。
職員室に想い人と二人きりなんてシチュエーションは、奈美にとって思いのほか毒だったらしい。緊張で喉がカラカラに乾ききってしまい、気付いた時には麦茶に手を伸ばしていた。
「んっ、ぬちゅっ、くちゅぅっ、にちゃっ、んっ、ああぁあああっ! なんて気持ちいいのっ、んっ、はっ、た、ただのキスなのに……あっ、ま、またイッちゃうっ……キスだけでっ、あっ、こ、こんなにっ……あぁあぁああああっ、し、幸せぇっ❤ んっ、ぢゅううっ、んっ!」
そして、現在に至る。
媚薬の効果は瞬く間に表れ、後は自制の叶わない結果へと帰した。
椅子に座る海陸へと圧し掛かり、ねっとりと唇を味わい、たっぷり唾液を啜る女教師の姿が見える。息つく間も与えない猛攻は、まるで理性を失った野獣そのものだった。
「はぁっ、はぁっ、はぁあっ、んっ、んふふふふ……海陸くんの股間、勃起したちん〇んが私のお尻に当たってっ、あああぁあ、気持ちいいわぁっ!」
いま、自分が職員室に居ることすら忘れてしまっている。
薬物で感度が底抜けに高まり、全身が性感帯のような感覚に苛まれているのだ。少しの刺激でも、身の浮く快感に溺れてしまう。そんな状態からの濃厚なキスは、奈美を絶頂の渦へと飲み込んでいった。
「あぁっ、海陸くんの唇、柔らかすぎっ、んっ、ちゅっ、ベロも柔らかくて、唾も美味しいわぁっ! しかもっ、海陸くんの勃起テントっ、はっ、はっ、はぁっ、ぁっ、私のお尻に当たってっ、気持ちいいっ! グリグリしてるっ、幸せすぎてっ、死んじゃうぅうっ!」
尻で味わう海陸の股間に、奈美が悶絶と発狂を繰り返す。
タイトスカートを捲り、否応なしに膨らむ海陸の股間を臀部で圧迫する。尻の割れ目に挟むように股間を重ねると、グラインドして官能を貪っていた。
向き合うように相手の股間へと座り、腰を揺らしながら天を仰いで白目を剥くそれは、インドの性の書を彷彿とさせる。
「あああぁっ、はぁあっ、あぁん、海陸くん……❤」
ぐりぐり、ぐりっ、ぬちゅっ、ぐちゅっ……
繊維の擦れる音と、奈美の乱れる声。それと、海陸の下着からは粘液の音が聞こえる。粘液の音は、我慢汁の接着音だ。下着の中にて、奈美の臀部に扱かれたペニスが悲鳴を上げながら噴き出していた。
全身が射精を予感すると、海陸がふと我に返る。
それまで、されるがままだった海陸だが、股間の盛り上がりを指摘されて漸く正気を取り戻す。両手で奈美の肩を押し上げて、せめてとばかりに唇だけでも離した。
「はぁ、はぁっ、はぁっ、せ、先生……い、い、いきなり、なにするんですかっ! はぁ、はぁ、はぁ……」
海陸からすれば、教師から突然の逆レ○プを受けた状況である。当然、何が何だか全く分からない様子である。茹蛸のように真っ赤になって戸惑うばかりの海陸に、奈美が顔を寄せて告白した。
「はぁっ、はぁっ、ご、ごめんなさい、海陸くん……あなたのことが好きで好きで堪らなくて。つい、こんなことを……」
「えっ!?」
「ごめんなさい……教育者としてこんなこと……本当に申し訳ないと思っているわ。んっ、ふぅっ、ふうっ、ふぁあっ! ……でも、身体が止まらないのぉっ! 海陸くんのおちん〇んがお尻に当たってっ、ふあぁあっ!」
謝罪の言葉を陳列するが、奈美の動きは止まらない。
それどころか、腰の動きは益々に加速している。
――信用していた教師に、いきなり逆レ○プされたのだ。きっと、海陸は深く傷ついたかもしれない――
そう思うも、どうしても動きを止められなかった。
溢れる想いが強すぎて。全身に感じる海陸から離れられなくて。
もっともっと、海陸に触れていたかった。
例え、後日に教師をクビになっても。
それくらいに、強い想いが溢れて止まない。
媚薬のせいだと言い聞かせながら、奈美は悔悟の涙を流していた。
「す、好き? せ、先生が、ぼ、僕のことを?」
「うううぅっ、初めて会った時から、ずっと……海陸くん、海陸くん、大好き、大好きなのぉっ! あっ、んはぁあっ、うっ、ううぅうぅっ、ごめんなさぃいっ……」
薬でトリップしてることもあり、奈美の口から本音がボロボロと零れる。美女に面と向かって好意を伝えられた海陸が一層に顔から火を噴き出す。
「う、そ、そんな。えっと、あの、えっと……うっ、あぁあっ!」
「分かってる。付き合える訳ないわよね。なら、一度だけ。一度だけで良いの。一度だけで良いから、触れさせて……」
「う、あ、あ……」
「………………ダメ?」
奈美のしおらしい態度も何処か作為的に見えた。
この状況で断る気概があるのなら、そもそも海陸がクラスメイトの女子に好い様に玩ばれることはない。奈美の予想通り、海陸は涙目で口をパクパクさせるのみだ。それを奈美は強引に肯定と受け取り、再び臀部を揺らしてキスに馳せた。
「海陸くん、大好きっ! ……ぬちゅぅうっ、んっ❤」
「はぁっ、はぁっ、ぁっ、せ、先生ぃ、お、お尻が当たってっ、あっ、はっ、これ、はぁっ、も、もう離れてくださいっ! こ、これ以上されたら……」
「ふふ。良いのよ、イッても❤ 私なんて、さっきからず~っとイッてるんだから。海陸くんとキスをして、お尻で勃起を感じて……はぁぁっ、また身体が熱くなってくるっ。またイッちゃうわぁあっ❤」
「う、うあぁあっ! そ、そんなに強く擦らないでくださっ、ああぁああっ、あっ、あっ、はぁっ、はぁっ、イ、イクッ、うううぅううぅっ!」
奈美にテントの上から座られて、まだ十分も経っていない。
しかし、海陸はとうに限界を超えていた。絶頂の触手が扉を何度も抉じ開けんと這っている。だが、ズボンを履いたままで、しかも女教師の目の前で射精など海陸が受け入れられるハズもない。必死に栓を閉めて、押し寄せるオーガズムに抗っていた。
「あぁあん、海陸くんのおち〇ちん、パンツとズボンを挟んでるのに、熱さが伝わってくるわぁっ。もうイキそうなんでしょう? イッて良いのよ? ほらぁ、我慢しちゃだめぇええっ❤」
「うあぁぁあああっ! ヤバいっ、あっ、あぁあっ、うああああっ!」
「はぁっ、はぁっ、はぁあっ、海陸くん、海陸くんっ、大好きっ、好き好き、大好きぃっ❤ んっ、ちゅぅうっ、んっ、んんんんーーっ❤」
「う、あぁあぁあああああぁっ!」
悪足掻きも空しく、海陸の官能的な絶叫が職員室に木霊した。
海陸が上半身を海老反りに大きく跳ねらせて天を仰ぐ。お互いに離れた唇からは透明色が糸を紡ぎ、ズボンの中では脈打つ肉棒が白濁液を滴らせた。
ドクッ、ドクッ、ドクッ……ヌプゥッ……
「うっ、ぁ……」
下着に不快感が染み渡るが、それがどうしたと言わんばかり。
あまりの快感に、海陸は声も出せなかった。
余韻にどっぷり浸かり、意識が薄れていくのを感じる。
身体を動かす気力もない。
一度の射精で、魂ごと全て吐き出した感覚だった。
「はぁああ……海陸くぅん……❤」
一方で奈美は、かつてない程の愉悦に溺れている。
想い人のイキ顔を眼前で観られたのだ。
しかも、下半身には精液の熱や感触が染み渡っている。
これ以上の幸せがあるものかと、目を反転させてアヘ顔を決めていた。
フォロワー以上限定無料
後半
無料