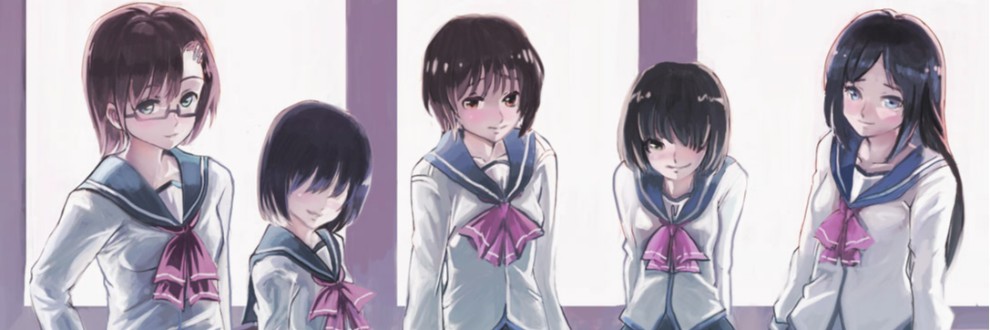【小説】催○アプリで巨乳女教師をコントロール!!
プロローグ-催○アプリの導入
「ふぅっ、ふぅっ……ふぅっ……んっ、はぁっ……」
消灯された真っ暗な部屋から、押し殺したような声が聞こえる。部屋の中央には布団が無造作に敷かれており、小柄な少年が小型電子機器を眺めながら寝転がっていた。
「はぁっ、はぁっ、はっ、し、しずな……しずな先生ぃっ……!」
布団に横たわる少年は、小型電子機器ことスマホの画面を食い入るように睨んでいる。画面には、不自然な角度から撮影された女性の写真が映し出されており、先ほどから、その女性の名前を延々と呟きながら、空いた片方の手で自分を慰めているようだった。
女性の名は羽並しずなという。豊満な乳を持ちつつ、穏やかそうな表情を浮かべた女教師しずなは、少年の通う学園の担当教師であると同時に、想い人でもあった。一目見た瞬間から恋を患ったのだ。
「う、あっ…………!」
そして堰を切ったような喚声と共に、少年は身体を撓らせて果てた。
反った亀頭から精液が迸る。白濁液は、そのまま小さな弧を描いて、しずなが映ったスマホに直撃した。少年が慌てて画面を拭こうとしたとき、それは現れた。
「なんだ、これ?」
スマホの画面が一度プツンと切れたと思ったら、真っ黒な画面の中央に「催○アプリのインストールが完了しました」という文字が浮かび上がる。
「うわっ、ウイルスだっ。なにか怪しいサイトでも踏んだっけか!」
怪しげなアイコンとアプリ名に少年が焦った。青少年らしく、日々いかがわしいサイトにアクセスしている少年には、原因に心当たりがあり過ぎた。すぐにウイルスと予測した少年は、決してアプリを開いたりはせず、そのまま削除しようと試みた。
……しかし、何処を見ても「催○アプリ」と書かれたアイコンを削除するボタンが見当たらない。どんなにアイコンを長押ししても、初期アプリのように、アンインストールするバツ印が出てこなかった。
再起動しても無意味という。少年はサイトで催○アプリについて調べてみた。すると、ネットの奥深くで、このような興味深い一文が見つかった。
『性に選ばれし者へ。十億人に一人の確率でインストールされるそれは、あらゆる人間を意のままに操れる最強のアプリであり――』
如何にも怪しげなサイトの、あまりに的を射ない説明文だった。少年は、なんとバカらしいと嘲笑う。……が、こんな文章を見つけたら、どうしても気になってしまうのが青少年というもの。あれこれと時間を無駄にした後、少年は結局アプリに指を伸ばした。
第一話-羽並しずなとの秘め事
翌日。放課後になると、少年は進路相談という名目で、しずなを進路指導室に呼びつけた。
「早く早く早く。早く来てくれぇ………………」
どうしても逸る気持ちが抑えられない。その理由には、昨夜のアプリが関係している。「あらゆる人間を意のままに操れる」という言葉……それを鵜呑みにするほど少年は出来上がってはないが、やっぱり可能性は捨てきれないということで、少年は昼間にクラスメイトの女子を使って催○アプリの実験をしてみたのだ。
本当に色々なことが出来るらしい。かと言って真昼間の学園で大それたことはしたくないので、とりあえず恋心を擽る機能を使用してみた。……すると、どうだろう。瞬く間に、少年を見る女子の視線が増えていく。周りの女子たちが一斉に顔を紅潮させて少年をジッと見つめ始める。やがて告白する女子もポツポツと現れると、少年はアプリの力に恐怖を覚え、慌てて催○機能を停止した。
「僕は、しずな先生とお近づきになれれば、それでいいんだ」
本当に、思うが儘に世界を変えられる力だと実感するが、欲張ると痛い目を見るのは明らかだろうと少年は自制した。ターゲットを現在片思い中の女教師のみに絞り、アプリを起動させて指導室で待機する次第だった。
コンコン。不意にノックがかかると、ドアが開いて目的のしずなが入ってきた。相変わらずの柔和な微笑みに、少年がドキンと胸を高鳴らせる。ここまでは、いつも通りの光景だが、催○のアプリを起動している今日は一味違っていた。
「あら……待たせちゃったかしら? ごめんなさい……」
少年を見るや、しずなが否や軽く赤面してしまう。素振りこそ落ち着いているも薄く紅潮させて、それを隠そうと片手を頬に充てる。急にモジモジし始めたりと、まるで女子生徒のような反応を見せていた。
もちろん、これには少年はアプリが影響している。チカラを用いて、しずなの恋心を少しだけ弄っていたのだ。
もっともっと過激なことも出来るが、恋愛の過程を尊重したい少年にはこれが限度である。しずなが席に着くと、少年は高鳴る心臓を必死に抑えながら口を開いた。
「まず、謝らなくちゃいけないことがあります。実は進路指導というのはウソでして……今日、しずな先生に話があって呼んだんです」
少年の言葉一つ一つを、しずながゆっくりと噛みしめていく。少告白しようと決意した少年だが、どうしても口籠って真っ赤になってしまう。核心に近づくに連れて、徐々に広がっていくむず痒い雰囲気から全てを察したしずなも、少年と同じく緊張して頬を染めた。
「それで、あの……その、つ、つ、付き合って下さいっ!」
流暢に話せず、どもりっぱなしな少年だったが、ようやく告白まで持っていくことに成功する。しずなは、まるで少女のように俯いてしまう。暫く経った後、しずなは首を小さく縦に振った。
「ええ、良いわ。こ、こんな私ですけれど……」
「そんなことないですっ、先生は完璧ですっ!」
「ありがとう……なんだか、心が温かいわ。記念にハグしてもいいかしら?」
「は、はい、もちろ……っ!」
交際もあっさりと成功する。その記念としてハグを希望する先生ことしずな。少年が赤ら顔で頷いた瞬間、しずなの備える巨大な胸が押し寄せてきた。
顔を丸ごと包み込んでしまうほどの大きさである。憧れだった相手とハグをしている――。少年は、しずなの胸に埋もれながら、アプリに感謝しつつ脳汁を噴き出しまくっていた。
それから数日が経過する。
交際が始まって最初の週末になり、ようやく二人の初めてのデートが始まる。教員と学生の恋愛は世間的に問題となりかねない為、学園内では基本的に接触はしないようにしていた。
「あ、先生っ! こ、こんにちはっ……」
「あら、私ってば待たせてばかりね。これでも早く来たつもりなんだけれど……ごめんなさい。あと、公の場で先生は困るわねぇ」
学園関係者にバレないよう、デートは学園から駅を三つ挟んだ地域で行うことした。念には念をということなのか、それともそれが休日の格好なのか、しずなは眼鏡からコンタクトに変えて、服装も露出度が比較的に高いセクシーな格好となっていた。
胸が強調され、谷間も見える魅惑的な衣服であり、健全な青少年の胸を高鳴らせるには十分すぎる破壊力だ。ただでさえ緊張していた少年だが、しずなの美しすぎる格好に、より落ち着きを失ってしまう。
そんな心境の中、僅かに催○状態にかかった、しずなが――。
「ぁっ……」
少年の腕を取り、絡めてきた。そこまで密着されたら、しずなの豊かすぎる胸を回避することなど出来はしない。更に、風上にいるせいか、しずなの身体から湧き立つ芳醇な香りも漂ってくる。胸の感触と、大人な女性の匂いにより、少年は既に下半身の限界を感じていた。
(こ、これマズいっ……ちょっと、催○を停止させよう……)
膨らむズボンを必死に隠しながらスマホを取り出すと、少年はしずなに罹けた催○をオフにする。
催○アプリの程度には一から十までのレベルが存在するが、これまで一切女性を知らなかった少年には、レベル一でも刺激が強すぎた。催○をオフにすると、間髪を容れずに、しずなの正気が元に戻る。
「あら……流石に腕を組むのは、よくないかもしれないわね」
催○をオフに戻すと、しずなは体裁を気にしてか、組まれていた腕を解いた。少年はホッと胸をなでおろす。
学園内でアプリをアレコレと試行錯誤している内に、分かったことがいくつかある。例えば、催○状態に罹った際の記憶について。
催○アプリを用いれば、如何なる相手も自由自在に操ることが出来るが、相手はその時の記憶の全てを忘れたりはしないらしい。今回の場合で言うと、少年は催○に罹った状態のしずなに告白をして付き合い始めたが、その後に催○をオフにしても、しずなは少年と付き合っている事実を把握しており、それに抗うこともなかった。
つまり、催○状態で起きたことは全て既成事実として処理され、自然に受け入れられるということだ。
いま、アプリを停止したが、それでもしずなは少年とのデートを享受して、ごく普通に振る舞ってくれている。交際してデート中という既成事実が成された故の結果であり、少年を想う恋煩いだけが綺麗に消えた状態になっていた。
(本当は恋人関係が良いけど、こうして近くで一緒に居るだけで幸せだからなぁ……)
アプリを使用せずとも、こうして一緒に肩を並べて街を歩くことができる。現状に大満足をする少年は、もう催○アプリは使用しなくても良いかなとまで考えていた。
…………。
しかし、健全な青少年を相手に、そんな健全な感情がいつまでも続くハズもない。日を重ねるにつれて、しずなを想う少年の愛情はどんどん高まっていってしまい、デートを何度か続けていく内に、少年は「ただ一緒に出掛ける」だけでは満足できなくなっていた。
恋人関係こそ続いているも、催○の罹っていない状態におけるしずなは、教師そのものである。思い切って手を握ろうと誘うも、体裁に問題があるからと断られてしまう。二回目以降のデートからは、もう露出度の高い服装すら見られなかった。
それでも満足していた頃が懐かしい。そう感じた少年は、スマホの奥底へと追いやった催○のアプリに、再び指を伸ばすのだった。
「ねぇ、しずな先生……」
「どうしたの?」
ある日のデートにて、下半身を疼かせた少年がしずなに声を掛ける。もう時は夕方へと差し掛かっており、いつもならこの辺で帰る頃だ。
だが、ただ出掛けることだけでは飽き足らなくなった少年は、これ以上の関係を望もうと試みる。
一ブロック先はホテル街だ。
少年は、まず催○の罹っていない状態で、しずなに迫ってみた。
「ごめんなさい。前にも言ったように、教師と学生、一線を越えるのはイケないと思うの。……分かってくれるかしら?」
案の定、断られてしまう。もう散々聞いた拒否文句だ。しかし、それも想定内。少年は、前日の内に設定しておいた催○アプリを起動させた。
いままでレベル一しか試してこなかった少年だが、これ以上は断られたくないと釘を刺して、アプリのレベルを三にまで上げていた。
アプリが起動する。
すると、スイッチが入ったように、しずなの様子が変わり始める。一見、いつもと変わらない様子に見えるが、急に周りをキョロキョロと見回したりと挙動不審になり、息も絶え絶えというか艶っぽい吐息を漏らし出している。
そんな様子に、少年は久々に胸をドキドキさせる。これなら断られないと確信して、エッチを誘おうとした、そのとき――。
「ァっ………!」
しずなが少年を抱きしめたのだ。スイカ並みに大きい二つの乳房に圧迫されて、健全な少年は一気にデレデレになり、しずなに主導権を渡してしまう。これが漫画なら、少年は鼻血を出すところである。
「ねぇ、今日は、もう少しだけ時間をくれないかしら? いつもはこの辺でお別れしてるけど……なんだか今日はもっと一緒に居たいわ」
少年が口を開く前に、しずなから誘われるのだった。もちろん、断ったりはしない。少年は、顔を真っ赤に染めながら首を縦に振った。
フォロワー以上限定無料
オチまで
無料