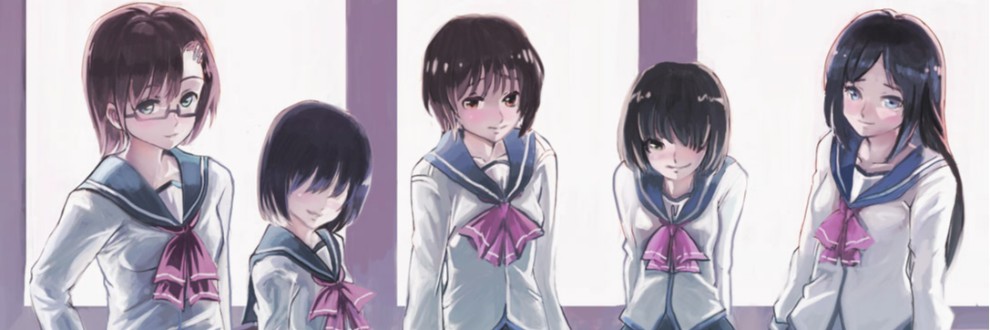概要
英傑は、ひょんなことから三人のお嬢様と知り合う。
彼女たちは根っからの箱入り娘であり、驚くほどに性の知識が無かった。
にも拘らず、性欲は人一倍という。
始めは調教ごっこのつもりで遊ぶ英傑だったが、次第に三人の性欲に圧倒されていく。
第一話-前半
権威主義の家柄にて生を受けた令嬢たちは、権力者の独善的な私情によって人生の多くを支配されていた。上流階級の血筋に恥じぬよう、幼少期から英才教育を叩きこまれては、決められた将来へと歩まされる毎日である。進学先や仕事、結婚相手に至るまで徹底的に管理される彼女たちに自由や娯楽など有りはせず、これからも死ぬまで血筋やらを全うしなければならなかった。
「……そう思ってた時期があったよ~」
頭を艶々に光らせた女学生の、溌剌とした声が聞こえる。名前を杏里といい、髪の毛を金色に染めたり、身体にタトゥーを掘るなど調子の良い奴だが、これでも歴とした名家の娘であり、彼女も生まれながら親に敷かれたレールを直走る存在だった。
……しかし、髪染めや彫り物、それと俺の顔面を踏みつけて悦に浸る様子から、杏里が既に親の望む姿から逸脱しているのは言うまでもないことである。
「ねぇ~、感触ばっか愉しんでないで、ちゃんと臭いも嗅いでよ!」
「はいはい、お嬢様。……すぅ~はぁ~、すぅ~はぁ~」
「ふふっ、くぅう……やっぱり、これ気持ちいいわぁ、ホント❤」
肉付きの良い杏里の足が俺の鼻へと押し付けられる。お嬢様の卑猥な悪臭が俺の鼻を刺すが、不快感なんて毛ほどもない。前足部と踵を両手で支えると、俺は足底から立ち込める饐えた臭いを犬のように嗅ぎ惚けた。
「んっ、くふふっ、んっ……ぁっ……」
土踏まずにキスをしながら露骨に鼻を鳴らすと、杏里が小さな喘ぎ声を零す。足の裏に感じる唇の感触と、足の臭いを嗅がれる羞恥により身悶えている。
「ったく、臭いを嗅がれて興奮するとか、どんなお嬢様だよ」
「は、はぁ? 女の子の足の臭い嗅いで思いっきり勃起させてる奴に言われたくないんだけど?」
「良いんだよ、俺は。お前らと違って下等生物だからな」
「拗ねないでよ。んっ、んぁっ……やっぱり、親指と人差し指の間を嗅がれるの弱いわぁ。なんか、ゾクッとくるよ❤」
「ここの臭い酷いな……んっ、すぅ~はぁ~、すぅ~はぁ~。ヤバい、ここの臭いマジで興奮する……すぅすぅ、くんくん、はぁはぁ……」
「んっ、ふぁあ! アンタの為に、靴下は洗濯しなかったんだ。自分でやっといてなんだけど、やっぱ恥ずかしいわ。んっ、ぁあっ……で、でも、この燃えるような快感……堪んないっ!」
「靴下を取り換えなかったのか。道理で、いつもより臭いわけだ」
杏里の臭いが鼻から脳へと達すると、脳内麻薬が分泌したような心地に陥る。ムンムンと漂う酸っぱい香りを貪るに連れて、俺の股間が火を噴かせていた。
「んくぁあっ! は、鼻が足の裏に当たってっ、臭いも嗅がれて……恥ずかしいっ! 恥ずかしすぎて、変な声出ちゃうっ!」
「ああ。杏里っ、お前の臭い、最高だよぉっ!」
「んはぁあっ、英傑っ、英傑っ! もっと、もっと臭い嗅いでぇっ」
獣のように我欲を全うする俺の姿に、杏里も燃えるような興奮を覚えていた。情欲が極まり、蕩けた瞳で縋るように俺を射抜いてくる。俺も、杏里のそんな視線に魅入られていた。
「あのぉ~、英傑さま。申し上げにくいのですが……杏里さんばかりではなく、私の臭いも均等に嗅いで頂けませんか? 随分待たされて、私のアソコも大変なことになっています……」
「ぇ、英傑さん……あ、杏里さんとイチャイチャし過ぎですっ!」
杏里に理性を刈り取られかける中で、隣から二つの声が掛かった。足を差し出しながら待ちぼうけを喰らっていた少女達である。
「あ……すまん。つい夢中になって」
「最近は杏里さんばっかりですよね。もしかして、英傑さまは、杏里さんを心に決めているのでしょうか?」
杏里と並び、同じく俺へと足を投げ出す女学生が、ムッとした表情で睨んでくる。彼女たちもまた、俺に足の臭いを嗅がれる存在だった。
「そ、そんなわけないだろ! ……ごめん、沙彩さん。ちゃんと沙彩さんの臭いも嗅ぐから。勿論、結衣ちゃんの臭いもね」
「ええ、お待ちしております♪」
「は、はい。あ、あ、ありがとう、ご、ございます……で、でも私は最後でも、ぜ、全然構いません……」
俺を神聖視して「様付け」を止めない沙彩さんと、男慣れせず吃音が目立つ結衣ちゃんに平謝りをする。どちらも杏里と同様に育ちの良いお嬢様であり、天地がひっくり返らなければ、俺のような下民が涎を垂らしながら易々と触れて良い相手ではなかった。
「それじゃあ、次は沙彩さんの足、いきます。……すん、すん、すぅ~~、はぁ~~。……あああ、本物のお嬢様の足の臭い……嗅いでるだけなのに、身体が浮きそうな感覚だよ」
「ありがとう……ございます、英傑さま❤」
「オイ、アタシも本物のお嬢様なんだが……」
だが、天地はひっくり返ったのだ。
杏里のツッコミを他所に、俺は沙彩さんの足を愛でるように抱えて深呼吸を繰り返した。沙彩さんの臭いが鼻から全身に染み渡ると、ぽつぽつと脳汁が迸り、地に足がつかないような気分になってしまう。
「沙彩さんの臭い……た、堪んないっ! はぁっ、はぁっ……」
十歳近く年が離れているのに、沙彩さんと「さん付け」してしまう貫禄が彼女にはある。及ばぬ鯉の滝登というのか、どうも沙彩さんのような上品すぎる子には頭が上がらなかった。
「ぁっ、んあぁっ! 身体がっ、もう熱くなってっ……英傑さまに足の臭いを嗅がれているだけなのに……あ、頭が真っ白になってしまいますっ……はぁっ、はぁっ、はぁあん❤」
高嶺の花は、相当な感度を誇っていた。
鼻柱を足裏へと押し付けて大きく息を吸い込むだけで、沙彩さんが背筋を戦慄させて身震いする。早くも顔を真っ赤にしては、瞳を熱く蕩かしていた。
「すぅ~はぁ~、すぅ~はぁ~。沙彩さん、相変わらず感じやすいね。愉悦に浸ってる顔、めっちゃエロいや……すぅ、はぁ~~っ」
「ひっ、ぁああん! ぁっ、ぁああ……恥ずかしくてっ、なにも考えられませんっ! ゃぁあ……お顔、視ないで下さぁい……いま私、絶対に厭らしい顔してるっ! ……こんな姿を父に見られたらっ、間違いなく勘当されてしまいますっ!」
沙彩さんが涙目で身を捩る。変態プレイを純粋に悦ぶ杏里とは違い、沙彩さんは由緒正しきお嬢様に有るまじき姿勢への背徳感から興奮しているようにも見えた。
「ああ、全くだ。俺みたいな得体の知れん男に隈なく貪られて、こんなエッチに感じてるんだからなぁ。もしこんな姿を両親に知られたら、どうなるんだろうな?」
「はぁあっ……私、いけないことしてます……ぁっ、あああっ、ぁっ……こ、これじゃあ……両親に失望されちゃうぅっ!」
臭気を吸い上げる度に、沙彩さんが壊れた機械のようにガクガクと全身を揺らす。果てには、勢力家の娘として不相応な自分を謝罪しながら、沙彩さんがオーガズムに達した。
「はぁっ、はぁっ、はぁっ……この快感、未だに慣れません❤」
筋肉を弛緩させ、呼吸を整えながら沙彩が口を開く。
「はぁ、はっ、はぁあ。臭いを嗅がれることで、ここまで解放的な気分に浸れるだなんて……英傑さまに出会わなければ、絶対に知り得ないことでした❤」
「礼を言うのは、確実に俺の方なんだけどね。どうも、沙彩さんは俺を高く見過ぎる傾向があるんだよなぁ」
「ホントだよ、沙彩。コイツなんて、ただの不法侵入者じゃん。まあ、いまの環境には私も感謝してるけど、こんな変態にそこまで畏まる必要なんてないんだよ」
「その通りなんだが、言われるとグサッと来るな」
さっきまで足の臭い嗅がれて善がってた癖に。
「杏里さん、失礼ですよ。英傑さまは私の恩人なのですから。英傑さまは窮屈にしていた私に数々の素晴らしい世界を教えてくれました! ……私、本当に感謝しているんですよ?」
「は、はぁ。どうも」
沙彩さんが目を輝かせながら俺との出会いを思い浮かべている。しかし、身分も年齢も大きく異なる我々……その邂逅が良いものであるハズがない。杏里が言ったように、俺は不法侵入を働いて三人との出会いを果たしたのだ。
定職にも就かず、四畳間のワンルームにて一人暮らし。女との面白い話もなく、日々をストレスと性欲で詰まらせてしまった結果、気づいた時には、俺は近所に聳える超お嬢様学園に不法侵入していた。
まるでゾンビが人間の血肉を求めるように、或いは砂漠のど真ん中でオアシスを探すかのように学園を徘徊して、お嬢様の私物の一つでも盗んでやろうと考えていた。
そして、学園で真っ先に出会ったのが、俺に足を差し出している三人のお嬢様だった。杏里たちは、俺が学園の関係者だと思ったらしい。敷地内を不審にうろつく俺に、なんの警戒心も抱かずに声を掛けてきたのだ。
それから、何故このような関係にまで発展したのかは覚えていない。いつの日からか、彼女たちは放課後になると、わざわざ学園の外出許可を得てまで俺の住むボロアパートに足繁くようになっていた。
「不審者だった俺からエッチを教わりたいだなんて、お嬢様ってのはホントに変わってるよな。まあ、そのお陰で俺は警察に捕まらずに済んだんだけどさ……」
「本当だよ。英傑なんて捕まっちまえば良かったのに」
「杏里さん、またそんなこと言って。英傑さんが嫌いなんですか?」
「い、いや。嫌いじゃあないけど、さ……」
一つ言えるのは、彼女たちが性に対して強い関心を抱いていたということ。全寮制な上に、ネット環境は厳しく制限され、外出の際にも一々許可が必要という牢獄的な学園に通うお嬢様方は、井戸の外に広がる世界が恋しくて堪らなかったらしい。ロクに働きもせず、日々をエロサイトの物色に費やしては、いつもオナニーに耽ってる俺のことが神々しく見えてしまうほど俗世に憧れていたのだった。
「その議論はまた今度にしよう。早く続きに移らないと結衣ちゃんが退屈しちゃう。待たせちゃってごめんね」
「い、いえ。と、とんでも、ない……です。ょろしくお願ぃします」
無駄に回想に浸ってしまったが、まだエッチの途中である。沙彩さんがエクスタシーの余韻を味わっている間、俺は最後の相手こと結衣ちゃんに食指を伸ばした。
「……んっ!」
ハムのように瑞々しくプルプルで、ムダ毛の一切ないツルツルな脹脛を抱えて優しく撫でると、結衣ちゃんが小さな呻き声を上げる。未成熟で童顔の、性に悶える結衣ちゃんのエッチな表情が俺の官能を天井知らずに突き上げていく。
俺は、覚悟を決めて足の裏に顔を埋め、目一杯に深呼吸をした。
「すぅ~~~~っ……………………………………」
「ふあぁあぁっ、え、英傑さんがっ、私の臭いをっ……❤」
「さーて、今日は何処まで耐えられるかな?」
「シッ、杏里さん」
俺は、可愛い女の子が相手なら尿だって飲める自信がある。足から放たれる臭気など、俺にとって官能以外の何物でもない。そんな俺だが、結衣ちゃんの臭気だけは別腹だった。
「ぅ、うう、ぇ、ぇいけつ、さん……」
臭いが鼻から脳に行き渡り、俺は結衣ちゃんの脹脛を抱えたまま固まってしまう。結衣ちゃんの足からダダ洩れる香味……それは、強烈な悪臭と破竹の苦味を伴う「えぐ味」だった。
催す吐き気を必死に堪えて、なんとか笑顔を浮かべる。そう、結衣ちゃんには、体臭があまりにもキツいという難点があった。
「…………くぅ、相変わらず……」
「ぁ、あぅ……ご、ごめ、さい……足が、その、臭くて……」
「い、いや。いつも言ってるだろ。結衣ちゃんの臭い、俺は好きだよ。……コンプレックスにするほどのもんじゃないってさ……」
涙目で謝る結衣ちゃんに、俺が精一杯の擁護をする。結衣ちゃんの臭いを初めて嗅いだ時、俺は思わずトイレに駆け込んでしまった逸話がある。
ただでさえ劣等感に苛まれやすい性格の結衣ちゃんだ。俺の、あの防衛本能は彼女を強く傷つけたに違いない。だから、俺は償いとして結衣ちゃんの悪臭に興奮を覚えるまで堪能する使命があった。
「……すぅ、はぁ、すぅ、はぁ……」
しかし目に染みるほど臭い。杏里や沙彩さんのような、臭くて酸っぱいけど何処か淫猥で、つい嗅ぎたくなってしまう臭いとは違う。なんだろう、昆虫の死骸から発するような、腐った臭いに近い気がする。
……決して口には出さないが。
「すぅ、はぁ……んっ、ぺろっ…………ぅぇっ」
「なんだ、英傑ってば、もう結衣の臭い克服しちゃったんだ」
ただ、人形のように均整の取れた愛らしい少女が臭いの発信源であることは事実なので、如何な腐臭だろうが、やはり俺の股間の滾りは避けられない。先ほどから、下着が先走り汁による不快感に見舞われ、ズボンを突き破る勢いで下半身を盛り上げていた。
「ぁぅ……ぇ、英傑さんのおちん〇ん……すごいことになってます……わ、私の臭いを嗅いで……あんなになっちゃう、なんて……」
「今更ながら、英傑ってホントにキモいな。あの結衣の足の臭いでも興奮しちゃうとか。一説じゃ、結衣の体臭を利用して化学兵器を作ろうって話も持ち上がってるくらいなのに」
「そ、そんなの持ち上がってないよぉ……」
「でも虫は殺せるよね?」
「殺せないよう……」
「ははは。まあ、確かに……ちょっとアレな臭いだよね」
噂に名高い結衣ちゃんの足を愛でる俺。露骨に勃ったテントを前に、結衣ちゃんの視線が釘付けになる。自他共に認める悪臭を大の大人が喜々として貪っているのだ。結衣ちゃんは、湯気が出るくらい顔を真っ赤にしながら、止め処ない羞恥で下着を愛液でジワリジワリと濡らしまくっていた。
「はぅっ、やっ、ふぁああっ! え、英傑さんっ、も、もう止めて下さいぃいっ。わたっ、私のっ、臭いですからぁ! ぅううっ、うっ……ひくっ、ひっ、ひぁああ、ぁっ、ふああぁっ! 私、英傑さんの傍に居られればそれで満足です。嗅がれなくても、別に気にしませんから……沙彩ちゃんと杏里さんの臭いだけ嗅いでいて下さいよぉ。ひっ、はぁあぁっ!」
「なに言ってんだ。俺が嗅ぎたいから嗅いでるんだよ」
「う、嘘、だぁあ……だって、最初の頃……わたしの、臭いでっ……英傑さん、ゲロ吐いて、悶絶してた……」
「あれは本当に悪かったって。不意だったからな……でも、大丈夫! 確かにちょっとアレだけど……割と癖になる味だぞ」
「そんなこと……ぁひっ、ひゃぁあっ! 鼻の先っ、あ、足の裏に擦られるの……と、とっても擽ったいですっ! はぁっ、あぁっ❤」
鼻先をグリグリと押し付けて肉感を味わう。ついでに、暇を持て余した口から舌を伸ばして後足部を舐め始めた。
「ぁっ、ゃああっ、ひぎっ、ぃいっ! 踵、あったかいっ! 英傑さんの舌の感触、すごく伝わってきて、き、気持ちいいっ! ぁああっ、だめっ、そこ……弱いんですっ……イ、イッちゃうっ……❤」
「結衣さん、羨ましいです♪ 英傑さまに舐められて……私の足は舐めてくれなかったのに……」
「良いだろ、結衣ちゃんは特別なんだ……ちゅっ、ちゅくっ、れろっ、ぺろっ……あああ、マジで興奮してきてヤバい。なあ……今日も、靴下、貰って良いか? んっ、ふぅっ、はぁあっ!」
「ちゃんとアタシらの足も舐めたらね」
「分かってるって。でも、まずは結衣ちゃんのを堪能してからだ」
ぺろっ、ちゅっ、ちゅぱっ、んっ……ぷちゅっ。
「はぅ……」
さっきよりも沙彩さんと杏里の息遣いが荒い。
「はぁ、はぁ……観てるだけで身体が熱くなってきました。局部もジンジンと火照っています……❤ ふぅ、ふぅっ、ふぅっ……」
「ぁあもう、変態の、変態行為を観て興奮するとか、アタシっ……! 熱っ! 股間、めちゃ熱いっ……んっ、うくっ、ふぁあっ!」
場が過熱する。耐えられないといった様子で、沙彩さんと杏里が己の指を使い局部をパンツ越しに触り出す。湿っていた下着が、その水気をより広げていく。やがて快感を肥大された二人のエロい声が俺の部屋に響き渡り、淫靡で蒸れた臭いも充満していった。
「はぁっ、はぁっ、はぁっ、みんなの汗や、アソコの臭いが漂ってて、めちゃくちゃエロいっ! お、俺もう舐めるだけじゃ物足りないっ! 結衣ちゃん、アレいくぞっ!」
「はぁん、ぁっ、やぁあっ! アレって、アレですかっ? ぁっ、だめっ、やっ……はぁあああんっ❤」
そこら中に漂う牝の臭いに耐えられなくなった俺は、こいつらの性感帯でもある足の指先を力いっぱいに齧った。
「ぃっ、痛ぁああぁああっ! 指っ、足の親指にっ、英傑さんの八重歯っ、ふぁっ、ぁっ、思いっきり食い込んでっ! ダメッ、ダメッ! イクッ、痛くて、イッちゃううぅうううっ!」
官能の極まった状態での痛烈な一撃は、結衣ちゃんを最高潮へと轟かせた。甘噛みのレベルではない、噛み千切らんとする勢いで歯を突き立てると、結衣ちゃんは上半身を弓なりにして、断末魔のような金切り声を上げた。
「ひ、ひぁああ……ぁっ、ぁぁあ……」
軽く達した、なんてもんじゃない。結衣ちゃんは、虚空を見つめて恍惚に酔い痴れていた。ボケっと口を開けて下半身をヒクヒクと揺らす。その様は、まるで魂が抜けたようだった。
「ホント、すごい感度だな。足を齧られただけでマジでイクなんて」
「結衣さん、とても気持ちよさそうです。私も、見ていて疼いてしまいました。英傑さま、次は私の足をお願いします❤」
「沙彩、順番から言えば次はアタシでしょ。ほら、早く私のも嗅いでよ。それとも、一発抜いてからにする?」
「抜くのは最後で良いよ。それより、ちょっと休憩が欲しいんだが……まあ、無理か。順番に嗅いでくのも疲れたし、今度は二人同時に嗅いでやるっ!」
「は~い、ど~ぞぉ♪」
結衣ちゃんの両隣から二本の足が伸びてくる。両手でそれを掴むと、貪るように自分の顔面へと宛がった。足裏の弾力を味わいつつ鼻から息を吸うと、苦味のある芳醇が体内に広がっていった。
「あぁ~、二人の臭い、めっちゃ興奮するううぅっ!」
女子が三人もいる以上、俺に休む暇はない。三人が満足するまでエンドレスに相手取るのが専らである。
だが、如何せん彼女たちの性欲に底はなく、結局は俺がノックアウトするまでエッチが続くのがデフォルトだった。