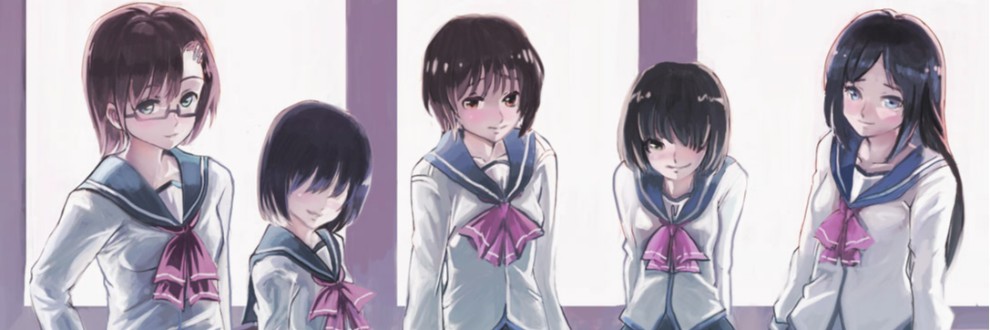2017年の初夏。偏差値から部活動の功績、立地に至るまで話題性がまるで無いと言われてきた栄耀学園(仮名)に、前代未聞の事件が発生した。
【2年A組在籍の女子20名がクラスメイトの男子一人を集団レ○プか?】
【20名の女子全員が妊娠という報告も!】
【被害の男子が廃人に? 現在も精神病院に入院中?】
渦中の男子は名前を林道 鈴江(りんどう すずえ)という。
整った容姿や繊細な性格から異性に注目されていたが、皮肉なことに鈴江は女性が大の苦手だった。
まともに話せないどころか、女子の視線が掛かるだけで赤面してしまう程であり、2年A組の教室では絶えず身を丸めて過ごしていたという。
対して、鈴江の反応により加虐心を煽られた女性陣は、目の前で故意にスカートを捲りあげたり、不意にハグをしたりと過激なセクハラの温床にあった。
・下着を見せつける
・抱き着く
・耳に息を吹きかける
・股間や臀部を触る
・集団で包囲する
事の発覚により女子20名が書類送検、という形で物語は終了する。
第一話 三人衆の痴女
「鈴江ちゃん、おはよ~❤」
「あ、ぉ、おはよ……」
「鈴ちゃん、今日も可愛いぃ~っ!」
「おはよう、鈴江ちゃん!」
「鈴江、おはよう❤」
「鈴ちゃ~ん!」
早朝の教室にて女子達の元気な挨拶が響く。二年A組の女子達は、教室に入るや否や誰もが一直線に鈴江と呼ばれた人物の元に向かい、「おはよう」と声を掛けながら頭を撫でていた。
一人、二人、三人と続き、最終的に計二十人の女子が鈴江の頭をナデナデする光景は、二年生に進級してから事件発覚まで欠かさず見受けられていた。
「鈴江ちゃん、おはよ。あっ、宿題やった?」
「…………うん」
しかし、当の本人は、乾いた声で素っ気ない相槌を打つばかりである。授業の課題について話を振るクラスメイトに対し、鈴江は視線を明後日へと逸らして苦い表情を浮かべていた。
クラスメイトを嫌っているわけではない。これは単に、異性に対する鈴江の免疫が著しく足りないだけだった。
林道 鈴江(りんどう すずえ)
栄耀学園二年A組に所属する男子学生である。低身長・気弱・童顔という三拍子の特徴をコンプレックスとしているが、そんな控えめな要素がウケるのか、女子からの人気は意外と高かった。
だが皮肉なことに、鈴江は女性を大の苦手としている。まともに話せないどころか、視線を交わすだけで顔を茹でタコにしてしまうほどだった。
「ねぇ、鈴江ちゃん、どこ見てるの。私の顔はコッチだよ」
不意に、クラスの女子が鈴江の頬を両手で押さえ、自分の方へと無理やり向けさせる。
「…………ッ!」
「きゃぁ~っ、お顔真っ赤っか! カワイィ~❤」
途端に、鈴江の頬が急激に熱を帯びていく。肌を触られ、目を見つめられた鈴江が瞬く間に頬を染めると、教室全体に女子の金切り声が響いた。
「話してる最中でしょ~、顔伏せないでよ~!」
「や、やめ……さ、触んないでっ……」
クラスメイトが鈴江の性分を知らないハズがない。女子達は、鈴江を揶揄って慌てふためく反応を毎日と愉しんでいるのだ。
「あぁもう、可愛いなぁ❤」
「ぁ~っ、私も鈴ちゃんの頭撫でたい~っ」
次第に鈴江の周りに女子が集まり出す。机に顔を伏せて耳まで赤くなった鈴江に、女子が手を伸ばして頭を撫でていく。
「…………ッ!」
「あっ、鈴江ちゃんが逃げた! みんな、捕まえて!」
「待ってよぉ~。一緒に遊ぼうよぉ~❤」
鈴江が逃げるように教室を飛び出すと、それを女子達が楽しそうに挙って追いかけていく。
これも、いつもの光景だった。
気の毒だけど、少しだけ女の子達の気持ちも分かるかもしれない。幼い顔立ちの鈴江は非常に中性的であり、容姿だけ見ても、とても男子とは思えないほどに可愛いのだ。
目が合うだけで赤面しては顔を伏せる姿も、さぞ女の子達の心を擽ることだろう。女子は、小動物のような弱々しい様子を晒す男子が大好きだ。正直なところ、私(女性取材班)も鈴江くんのような男子と相対した日にはトキメキを感じてしまうかもしれない。しかし、幼少の頃から嫌と言うほどに女子からちょっかいを受けてきた鈴江だが、クラス替えの運がなかったのか、二年生に進級してからは特に扱いが過激になったという。
「ねぇ、鈴ちゃん。こっち視て!」
「ほら、どぉ~ぞ❤」
「……ッ!」
廊下を歩いていた鈴江に、妖しい笑みを浮かべた三人組の女子が正面から近づいてきたと思ったら、突然スカートを捲り上げて下着を見せ付けてきたことも。この三人はクラスのカーストでいうと中位に属する存在であり、より積極的な女子達の陰に隠れて鈴江を誘惑していた。
目の前に並ぶ三人の可愛らしい下着に、鈴江は早速とばかりに顔を背ける。相変わらず紅潮する鈴江だが、自ら露出している三人組も、頬を染めて擽ったそうな表情を浮かべていた。
「だ、だからソレ、や、やめてってば……」
「私達に慣れてもらいたくて❤」
「そうそう。もっと仲良なりたいのに、鈴江ちゃんってば、いっつも私達を無視するじゃん。結構傷つくんだよー?」
「で、でも、僕は本当に女性が苦手……」
「だから、私達が克服の手伝いしてあげるんだってば!」
「ふふふ、ちょっと荒療治になっちゃうけどねぇ~❤」
そう言ってスカートをひらひらと舞わせてパンツを見せてくるのは如何だろうか。羞恥に耐えられなくなった鈴江が踵を返そうとするも、三方向から包囲され、否応なしに立ち往生してしまう。
極端に女性を不得手とする鈴江は、こうして数人に囲まれるだけで動くことすら出来なくなるのだった。
「ね、ねぇ、そこ通りたいんだけど……」
「私達のパンツ、じっくり視てくれたら通してあげる」
「出来るわけない……そ、それに、そんなことして……は、恥ずかしくないの?」
「もちろん、恥ずかしいに決まってんじゃん。でも、これは鈴江ちゃんの為だからねぇ? それに、なんか……こうしてると、めちゃくちゃ興奮するし、き、気持ちいいの……❤」
三人組も赤面して恥ずかしそうにモジモジしている。三人組は、慕情を抱く相手に下着を見せつける羞恥だけでなく、公の場で露出する背徳感にも性的な悦びを感じていた。
「さ、触ってみても良いんだよ? 私、彼氏いるけどさ……鈴江ちゃんなら、触ってくれても全然オッケーだよ❤」
「私も良いよぉ~。興味はあるんでしょ? ほら、触ったり……な、舐めたり……んっ、ぁっ、そ、想像しちゃった……❤」
進退窮まる状況に鈴江が膝を抱えて両手で顔を隠してしまうも、これまた女子達には逆効果である。鈴江の反応に三人が更にテンションを上げると、スカートを捲りあげたままジリジリと距離を縮めてきた。
「ちょっ、ち、ちかっ、近す、ぎっ……」
そして、鈴江の頭部に触れるギリギリまで股間が迫る。あと半歩でも踏み込めば、鈴江の頭部を股間が三方向から締め付る距離である。
「ちゃんと視て……ふぅっ、ふぅっ……勿体ないよ? クラスメイトのココ、三人同時に拝めるチャンスなのに❤」
「やだ……これ、すごく興奮する……みんなで鈴ちゃんを囲んで、パンツを見せつけて、誘惑するの……か、身体、すごく熱くなってきちゃった❤」
パニックで塞ぐ鈴江を尻目に、三人は本格的に情欲を高めていた。その表情はトロトロに蕩けており、口の中は唾液で溢れ、飢えた獣のように涎を垂らさん勢いである。
「ね、ねぇ。これって、どこまで行くの? わ、私、なんかマジでちょっと……その、ぬ、濡れてきちゃったんだけど……」
「う、うん。そろそろ止めないと、引っ込みつかなくなるかも」
「でも、もっと過激なことやってる人もいるよね?」
「優美さんのグループとか? 噂では鈴江ちゃんにクンニさせたり、もっと激しいプレイもやってるって色々噂を聞いてるけど……鈴江ちゃん、それってホントなの?」
「…………」
「否定しないってことはマジか。ん、でもまあ、優美さん達なら、ねぇ? あの人達、いっつも激しいし……」
優美とはクラスのリーダー的存在であり、骨の髄まで鈴江に心酔していると知られている。大層なお嬢様のようだが「鈴江は私の肉奴○」と身勝手に公言しており、人当たりの良い三人組からも「傲慢に足が生えた存在」と揶揄られる存在だった。
「………………」
三人組の一人である加菜実は、そんな優美に蟠りを抱き続けていた。持ち前の権力を存分に行使して鈴江を独占し、人目も憚らず教室でイチャイチャとする暴君には負けたくない……と、加菜実が呟く。加菜実は、無言で股間を鈴江の頭部へと押し付けた。
「加菜実っ?」
「私も……もっと鈴ちゃんと深い関係になりたい……」
そう言って、両手で鈴江の頭部をガッチリ掴んで離さない。
「ンンーーッ、ンッ、ンンンッ!」
湿りっ気のある下着で顔面を圧迫された鈴江がなにやら抗議をしているが、もはや加菜実の耳には入っていない。炙られた官能と溢れる鈴江への想いにより、加菜実はタカが外れたように正気を失っていた。
「…………」
「…………」
一呼吸置いて、他の二人も鈴江の後頭部に股間を押し付け始めた。三方向から成る、いわゆる擬似クンニである。
「私も、もっと鈴江ちゃんと触れ合いたい……」
「優美さんにも負けたくないしね!」
鈴江の頭部を三人の股間が雁字搦めにする。そのまま鈴江の頭を握り潰さんとばかりにギュウギュウに締め付けていた。
「はぁぁ……鈴ちゃんにこんなことしてるなんて、夢みたい❤」
「うんうん。いつも妄想ばっかりだったからね……こんなことなら、もっと早くやってればよかったね」
「一回やっちゃえば、もう恒例行事に出来る?」
「ふふふ、鈴ちゃんになら毎日だってやってあげちゃう!」
トランス状態に入って異なことを言い続ける三人組に、鈴江が背筋を凍らせて心底怯える。力づくで振り切ろうと頭を振り回そうとするが、三人組のスクラムを決壊するには至らない。
「ぁんっ、ぁっ、ちょっ、鈴江ちゃん❤ そ、そんなに頭振ったら髪の毛が……んっ、股間にスリスリしてっ、んぁっ❤」
「これ、マジで気持ちいいっ……鈴ちゃんの頭で擦るの……癖になっちゃいそう……」
「鈴江ちゃん。次は下着じゃなくて直接オマ○コで擦りつけてあげるからね。今日は、まだちょっと恥ずかしいからこのままで」
「んっ……はぁ……❤ ヤバい、鈴ちゃん可愛すぎるよぉ❤」
「ね~、目ぇ開けてよ。私いまキミの頭に股間を押し付けてるんだよぉ? 私のココ、ちゃんと視てよ。はぁ、はぁ、はぁ。んっ、ふぅっ……❤ こんなに濡れたのって、生まれて初めてだよぉ」
「三人からこんなことされちゃって……究極の荒療治だよね。毎日やってあげるね。これなら、絶対に女を克服できるよ❤」
「ふぅ、ふぅっ、んっ……す、鈴江ちゃんの髪の毛に擦りつけて下着がぐちょぐちょだよぉ……❤」
理性を失った女子達は、鈴江のガラスな心もお構いなしに局部を押し付けて腰を振りまくり、ひたすら官能を貪っていた。これはもう誰がどう見ても完全な逆レ○プである。茹でタコという表現がピッタリなくらい、鈴江の頬は気の毒に染まっていた。
なお、鈴江は女性を極めて苦手としているが、性欲がないわけではない。寧ろ、女性陣の日常的なセクハラのせいで、毎晩欠かさず三回は自分を慰めているほどである。
三人のクラスメイトに濡れた秘部を三方向から押し付けられて無頓着で居られるハズもなく、とうに鈴江の股間は限界まで突っ張って下着の中は我慢汁が氾濫していた。
「ぁ、ぅぅううっ、んっ……」
亀頭がテントに擦れて快感が高まっていく。加菜実のオマ○コに下着越しでクンニをしながら、後頭部では二つの局部の感触が伝わる淫猥っぷりに、もはや吐精感は限界ギリギリだった。
「ぁんっ、ぁっ、ぁああっ……鈴ちゃんのお顔、赤面してて、超熱いっ……熱が私のアソコに響いてくるっ! なにこれっ、めっちゃ気持ちいいっ! んっ、んんんんんっ! はっ、だ、だめっ、気持ち良くて……も、もうっ……❤」
「はぁっ、はぁっ、はぁっ……髪の毛、気持ちいい……鈴江ちゃんの髪の毛でっ、クリトリス、じょりじょりするの、すっごく気持ちいいよぉ……❤ イ、イ、イッちゃうぅぅっ……」
「鈴江ちゃん、好きっ、大好きっ❤ こんな、オマ○コでスリスリしてるだけで、幸せだよぉおっ、んぁああああっ❤」
廊下のど真ん中だというのに、三人組が絶頂の官能を恥ずかしげもなく口にする。女子達の下着は鈴江以上に濡れきっており、大きな染みを作っては、溢れた愛液が太腿を伝って床に滴っていた。
「イクッ、イクッ、イグッ……あっ、んぁあっ、ぁあああっ!」
「イッちゃうぅっ、鈴ちゃんの顔に擦りつけて、イグッ、んっ、はああぁあんっ!」
「ふぁああっ、鈴江ちゃんの髪の毛、気持ちいい……こ、これヤバぁ……脳みそドロドロしてて、全身が熱い……こんなに気持ちいい感覚、生まれて初めてだよぉ……❤」
そして、絶頂に。三人が空を見上げ、甲高い声を上げてオーガズムへと達した。虚空を捉える瞳は生気を失ったようにトロンとしており、下着の奥で膣口がヒクヒクさせるに連動して、背筋をピクピクと戦慄かせる。
「…………ッ!」
同時に、三人の与り知らぬ所で、鈴江も射精に至っていた。
三人から発せられたムンムンとする淫猥な臭いや、押し付けられた股間の弾力で興奮が臨界点に達すると、鈴江は無意識にズボンより盛り上がるテントを慰めていたのだ。
ドクッ、ドクッ、ドクッ……
テントを撫でまわして間もなく射精に達する。下着の中が一瞬で不快感に満ちていくが、鈴江は猛烈な快楽に恍惚を味わっていた。
「はぁ、はぁ……ふぅっ。鈴ちゃん、ごめんね。私達だけで盛り上がっちゃって。息苦しくなかった?」
加菜実の声に鈴江がすぐに意識を取り戻す。三つの股間に埋もれた頭を上に向けると、心配そうに鈴江を見つめる三人が見えた。
吐精を悟られぬよう、屈みながら鈴江が頷く。
「…………私のこと、嫌いになってない?」
理性を取り戻した加菜実が一歩距離を取って聞いてくる。パンチラを見せるだけのつもりが、擬似的なクンニまで発展したのだ。流石にやり過ぎたかもしれないと怯えていた。
そんな表情に、鈴江の胸は別の意味で高鳴っていた。
「……う、うん。だ、大丈夫……」
「ありがと! 大好きだよ❤」
加菜実が鈴江の言葉に全力で安堵する。
と、加菜実は鈴江の額にキスをして軽くハグをした。
「ああっ、いいなぁ~。鈴江ちゃん、私のことは嫌ってない?」
「だ、大丈夫」
「ありがとぉ~。私も鈴江ちゃん大好きっ! ……ちゅっ❤」
「私のことは?」
他の二人も鈴江にキスをする。人知れず射精して多少は落ち着いた鈴江だったが、三人に好意を伝えられてはキスをされ、再びテントを作り上げてしまう。
「…………ッ!」
これに三人が気付き、もし射精したこともバレたら……と、焦り、鈴江はその場から逃げるように立ち去ってしまうのだった。
「あっ……逃げちゃった……」
「う~ん、さっきので、だいぶ距離が縮まったと思ったのに……まだまだなのかなぁ?」
「でも鈴江ちゃん、可愛かったぁー❤」
「うんうん! あぁーもう、もっと色んなことしてあげたいっ」
「……また、やっちゃう?」
「う~ん……」
「でも、鈴ちゃん、途中からは嫌がってなかったよね?」
「そこ重要だよね! でも、次から廊下はナシで」
「わかった。じゃあ、次は、こういうのはどう――?」
鈴江が立ち去った後、三人衆は再び鈴江に迫る計画を立てるのだった。
後の展開があまりにも抜きん出ているせいで印象は薄かったが、出会い頭に女子が集団で股間を擦りつけてくるなんて、これだけみても尋常じゃあない話である。進級してからは、こんな光景も全然珍しくなかったというが……。
日によっては、下着ではなく局部そのものを見せ付けることもあったらしい。他にも、唇を無理やり奪ったり、自分の体液を鈴江のペットボトルに入れたりもしていたとのこと。
『……あなた達は、何故そんなことを?』
『あなたも、鈴江ちゃ……鈴江くんに会ってみれば、きっと分かると思います。口じゃあ……「堪らなく興奮していたから」としか言えません』
『…………』
性別が逆なら、似たような事件は山ほどあっただろう。いつまで経っても本件の話題が収まらないのは、女性から男性を集団でレ○プするって事例が珍しいからだ。でも、本能という観点で考えてみれば、今回の件もそんなに囃し立てられるような話じゃないのかもしれない。
女性の潜在的な性欲は男性より遥かに濃密だという説もある。それでいて女性から男性への性的虐○が比較的に少ないのは、単純に男性を物理的に抑え込むのが難しいからだろう。
だが、もし女性よりも女性的な気弱な男性がいたら――?
今回の事件も、ディテールは多分に漏れない例かもしれないと、私は思った。